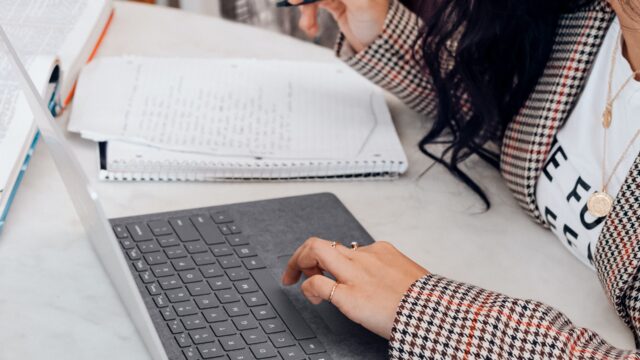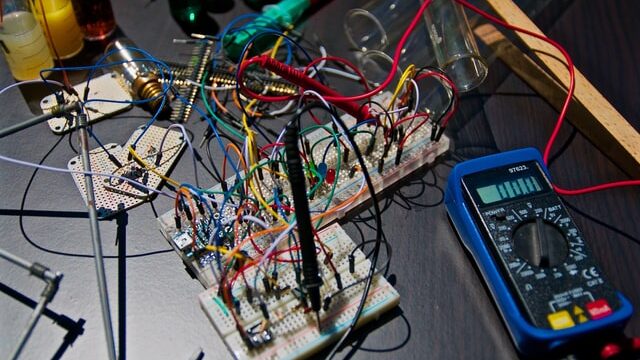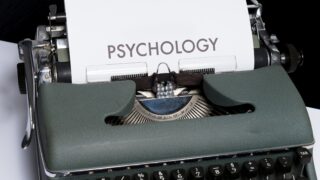公認心理師及び臨床心理士試験、臨床心理士指定大学院受験を目指す人のための用語説明コーナーです。今回はゲシュタルト心理学です。
ゲシュタルト心理学とは?
ゲシュタルト心理学は、ヴントやティチナーの構成主義(要素主義)的な考え方への反論としてヴェルトハイマーによって提唱されました。ヴェルトハイマーは、人間の精神は要素の寄せ集めでは無く、全体性が重要であるとしました。
ゲシュタルト心理学は、ドイツで誕生しましたが、後に活動拠点をアメリカに移しています。さらにゲシュタルト心理学の考え方は、後に実験社会心理学の基礎となったり、認知心理学の誕生にも影響を与えています。
ゲシュタルト心理学の重要人物
・M.ヴェルトハイマー:ゲシュタルト心理学派を確立した人
・W.ケーラー:ヴェルトハイマーの協力者その1「洞察学習」の人
・K.コフカ:ヴェルトハイマーの協力者その2英語が堪能でゲシュタルト理論を英語圏に紹介した人
・K.レヴィン:「場の理論」、「ルビンの盃」の人
ゲシュタルト心理学の主なキーワード
仮現運動
実際には動いていないものが動いているように見える現象のことです。電光掲示板で文字が右から左に動くように知覚(実際には小さなランプが消灯・点灯を繰り返しているだけ)したり、パラパラ漫画も同じ原理です。ヴェルトハイマーは、光の球をある程度の間隔(60ミリ秒)で提示すると、左右に移動しているように見えることを発見し、ファイ現象と呼びました。
プレグナンツの法則
群化の法則とも呼ばれており、ヴェルトハイマーは人が図を知覚する時、より単純で分かりやすいまとまりとして捉えるとしました。プレグナンツの法則の例を以下のような例があります。
・近接の法則:近くにあるものがまとまって知覚される
・連続の法則:つながっている物の方がまとまって知覚される
・類洞の法則:同じもしくは似ているものがまとまって知覚される
・閉合の法則:閉じた形はまとまって知覚される
また、ケーラーはプレグナンツの法則は心理現象だけなく、脳にも同じように起こっているとし、心理現象の法則であると同時に生理的現象の法則であると考えました。ケーラーのこのような考え方を、心理物理同型説と言います。
図と地
絵や風景を眺めた時に注意を向けている部分を「図」、背景として認識した部分を「地」と呼びます。ルビンの盃では、この図と地が入れ替わりやすくなっており、「図地反転」が起こりやすい絵柄になっています。
場の理論
レヴィンは、人の行動は環境との相互作用の中で決定するとしました。レヴィンは特に、他者との相互関係の中で人がどのように影響を受け、行動を決定していくかに注目していました。このような考え方は後のグループダイナミクスに影響を与えています。
洞察学習
ケーラーはチンパンジーが高い所にあるバナナに対して、近くにある棒や踏み台を使ってバナナの取り方を発見していく過程を目にし、目的と手段を適切につなぐ状況に気づく学習を洞察学習と呼びました。
ゲシュタルト心理学を実践応用されたのが、パールズのゲシュタルト療法です。その他にも、ハイダーのバランス理論、アッシュの同調研究、フェスティンガーの認知的不協和理論などもゲシュタルト心理学から影響を受けています。