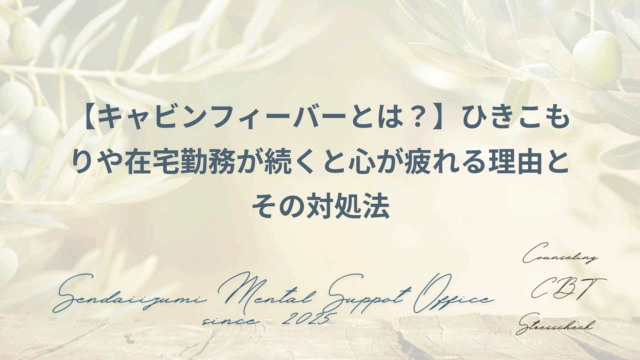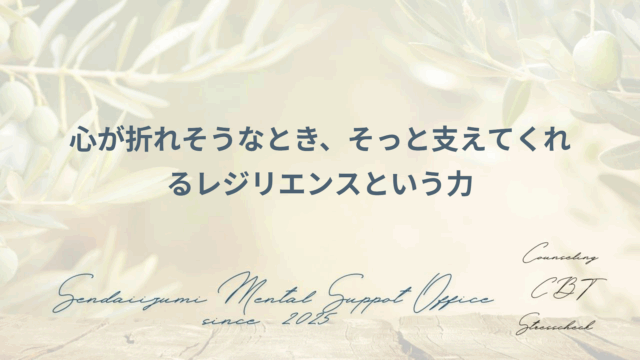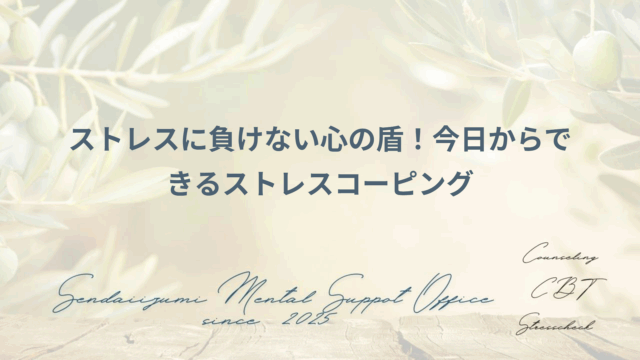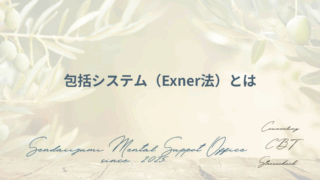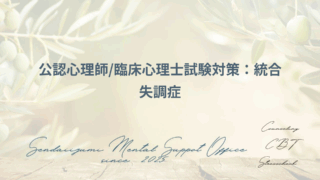心の苦悩に光を当てる:PTMFとは
もくじ
1. はじめに:診断名だけでは語れない心の物語
漠然とした生きづらさや、説明のつかない心の疲弊を感じることがあるかもしれません。
心の不調を感じると、つい「病気なのだろうか?」と考えてしまいがちです。しかし、心の苦悩は、必ずしも診断名で割り切れるものではありません。経験や感情には、もっと深い背景や意味が隠されていることがあります。
今回ご紹介するのは、そんな心の苦悩を「病気」という枠に収めず、より包括的で人間中心的な視点から理解しようとする新しい考え方、PTMF(パワー・脅威・意味のフレームワーク)です。
2. PTMFとは?:心の苦悩を「病気」ではない視点から捉える
PTMFは、Power Threat Meaning Frameworkの略で、英国心理学会が中心となって開発されました。これは、従来の精神科診断(DSMやICDなど)が、症状を「病気」として分類・診断することに焦点を当てるのに対し、「なぜこの人がこの苦悩を抱えているのか」という問いを、その人の人生の文脈や経験から深く探求しようとするフレームワークです。
PTMFは、心の苦悩を、以下の4つの基本的な問いを通して理解することを提案するものです。
- どんなことがその人に起きましたか?(パワー)
- その人の人生に影響を与えてきた「力」や「権力関係」は何だったでしょうか?
- 例えば、社会の期待、家庭環境、人間関係、過去のトラウマ、経済状況など、その人を取り巻く様々な影響を指します。
- それによって、その人はどのような影響を受けましたか?(脅威)
- その「パワー」によって、その人はどのような「脅威」に直面したでしょうか?
- 身体的、精神的、社会的なストレスや危険、自己肯定感の低下、孤立感などがこれにあたります。
- その経験は、その人にとってどのような意味を持ちましたか?(意味)
- その「脅威」や「経験」に対して、その人はどのような「意味」を見出したでしょうか?
- 例えば、「自分が悪いんだ」「誰も信じられない」「強くならなければ」といった、生き残るための適応や、内面化された信念などが含まれます。
- その脅威に、どのように対応してきましたか?(応答)
- その「脅威」に対して、その人はこれまでどのように「反応」し、対処してきたでしょうか?
- 感情を抑え込む、過剰に努力する、引きこもる、特定の行動を繰り返すなど、従来の「症状」として捉えられてきたものが、この「応答」として理解されます。
PTMFは、これらの問いを通じて、心の苦悩が、単なる「病気の症状」ではなく、特定の状況や経験に対する「理解可能な反応」であることを示します。そして、このフレームワークは、その人が持つ「強み(Strengths)」や、支援を通じて得られる「安全(Safety)」のリソースにも焦点を当て、未来への希望を見出すことを促します。
3. 「生きづらさ」の背景をPTMFで紐解く:具体的な心の物語
日常生活で感じる「生きづらさ」や心の苦悩は、多種多様です。例えば、職場での人間関係のストレス、過去の辛い経験、漠然とした将来への不安、あるいは自己肯定感の低さなど、その背景は人それぞれ異なります。
PTMFの視点から見ると、これらの「生きづらさ」は、以下のように紐解くことができます。
- パワー: 競争の激しい社会、家族からの期待、特定の人間関係、あるいは過去の出来事など、その人にとって負担となる「力」に常にさらされている。
- 脅威: そのパワーによって、過剰なストレス、疲弊、自己否定、不安感といった「脅威」に直面する。
- 意味: 「自分は能力が低い」「周りに合わせなければならない」「この感情は出してはいけない」といった「意味」を見出し、自己を否定的に捉えたり、特定の行動パターンを繰り返したりする。
- 応答: 刺激から身を守るために距離を置く、感情を抑圧する、完璧を目指す、といった「応答」をする。これらが、従来の「適応障害」や「不安症」のような診断名で捉えられてしまうこともあるかもしれません。
PTMFは、心の苦悩を「病気」とラベリングするのではなく、その経験が、どのような「パワー」に触れ、どのような「脅威」となり、その結果どのような「意味」を見出し、どう「応答」してきたのか、というその人自身の物語として理解することを可能にします。
そして、その人が持つ本来の「強み」を見つけ出し、それを活かしながら、より安全で自分らしい生き方を見つけるためのサポートへと繋がっていくのです。
4. なぜ今、PTMFが注目されるのか?:カウンセリングに活きる理由
PTMFが今、心理専門職や心のケアを求める人々から注目されているのは、以下のような理由があるためです。
- 差別化の強化: 精神科診断とは異なる視点を提供することで、「診断名に囚われたくない」「もっと深く自己を理解したい」と考える方々に強くアピールできます。これは、医療機関では得られない、カウンセリングオフィスならではの価値となります。
- 共感と安心感の提供: クライエントの苦悩を「病気」としてではなく、「人生の経験と意味づけ」として捉えるPTMFの視点は、スティグマを感じている人や、自分の問題に名前をつけられないと感じている人に大きな共感と安心感を与えます。
- 専門性と権威性の向上: 最先端の心理学的な枠組みであるPTMFについて分かりやすく解説し、それをカウンセリングに活かすことで、カウンセラーとしての専門知識と学習意欲を示すことができます。これは、クライエントからの信頼性向上に直結します。
当オフィスでは、WAIS-IV検査でその人の知的な特性を理解し、それをPTMFの「強み」や「応答」の視点と結びつけることで、より包括的な自己理解と問題解決へのアプローチを提供しています。その人の「生きづらさ」の背景にある特性を深く理解し、それらを活かして自分らしい人生を歩むお手伝いをいたします。
5. おわりに:PTMFで、その人らしい未来へ
PTMFは、心の苦悩を、その人自身の物語として深く理解するための強力なツールです。診断名に囚われず、その人の経験や感情に寄り添い、その背景にある「パワー」や「脅威」を紐解き、新たな「意味」を見出すことで、その人らしい「応答」を見つけることができます。
もし、診断名では説明できない心のモヤモヤや生きづらさを抱えているなら、PTMFの視点を取り入れたカウンセリングが、心の奥底にある物語を紐解き、その人らしい未来を築くための第一歩となるかもしれません。
当オフィスは、心の物語に真摯に耳を傾け、共に歩むことをお約束いたします。お気軽にご相談ください。