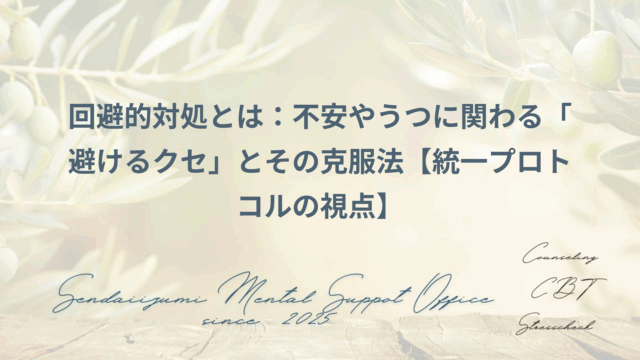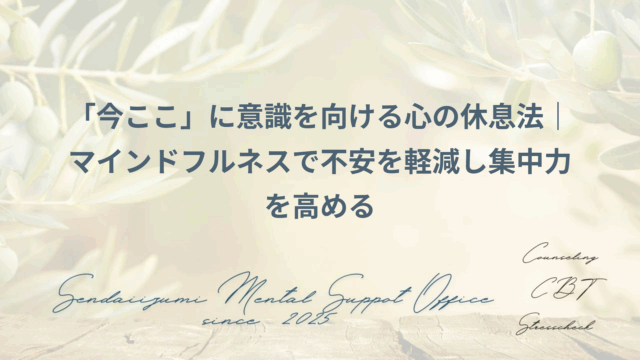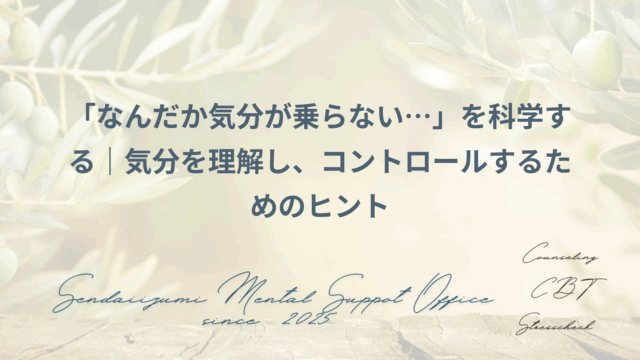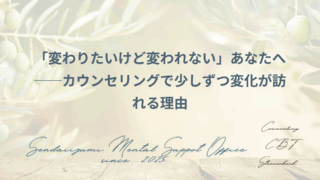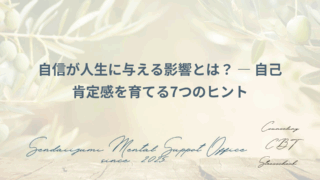現実的な人ほど疲れやすい? 心の健康を守る考え方とは
カウンセリングの現場ではよく、「同じような出来事があっても、人によって感じ方や反応がまったく違う」という場面に出会います。
たとえば:
- Aさんは仕事でミスをして上司から注意を受け、落ち込み、やる気をなくしてしまいました。
- 一方、Bさんも同様にミスをして叱責されましたが、「良い学びになった」と前向きに受け止め、次の業務に意欲的に取り組んでいます。
このように「出来事の受け止め方」によって、その後の気分や行動が大きく変わってくるのです。
この“捉え方の違い”に注目したのが、心理学者のラザラス。彼は「ストレスの正体は出来事ではなく、それをどう捉えるかにある」とする「認知的評価理論(cognitive appraisal theory)」を提唱しました。
もくじ
気分と捉え方の関係 〜 拡張形成理論とは?
ポジティブな気分でいると、物事を柔軟に捉えられるようになります。心理学者バーバラ・フレドリクソンは、「拡張形成理論(broaden-and-build theory)」を提唱し、ポジティブな感情が思考や行動の幅を広げ、長期的な心理的資源を育むことを明らかにしました。
ポジティブ感情がもたらす3つのリソース
- 身体的リソース:運動や健康習慣を通して、活力や免疫力が高まります。
- 心理的リソース:楽観性、自信、自己効力感などが育まれ、ストレスに強くなります。
- 社会的リソース:人間関係や信頼関係が深まり、孤立を防ぎます。
これらのリソースは、日常の中でポジティブな出来事や感情を積み重ねていくことで徐々に育まれます。
実は「非現実的な自信」が心の健康にいい?
ここで少し意外な心理学的知見をご紹介します。
ある研究によると、精神的に健康な人は「非現実的にポジティブな自己認識」を持っている傾向があることがわかっています。
一方で、「現実的で正確な自己認識」を持っている人ほど、精神的疲労や抑うつ傾向が強いという結果も出ています(Taylor & Brown, 1988)。
たとえば、こんな2人がいたら…
- Cさん:「私は大きな失敗もするけれど、周りにいい影響を与えているし、将来もきっと大丈夫」
(実際にはそこまで成功していなくても、自分に対して温かく楽観的) - Dさん:「自分には足りないところが多い。これ以上うまくやれる気がしない」
(事実に即して自己評価しているが、その分、気分は落ち込みやすい)
この研究は、ある程度「現実離れした自信」や「前向きな自己像」が、心の健康に役立つことを示しています。
ポジティブ思考を育てる日常のヒント
ポジティブな思考は、才能ではなく「習慣」で少しずつ育てていくことができます。以下のような実践を、日々の中で取り入れてみてください。
1. 趣味にいそしむ
楽しい時間は、自然と前向きな気持ちを生み出します。小さな楽しみを「自分の時間」として大切にしましょう。
2. 軽い運動を取り入れる
散歩やストレッチなど、無理のない運動は気分転換に効果的です。ポジティブな感情を育てる下地になります。
3. マインドフルネスを試してみる
瞑想や呼吸法を通して「今、ここ」に注意を向ける練習は、ネガティブ思考のループを和らげてくれます。
4. “良かったこと”に目を向ける
その日の中で「良かったこと」を3つ挙げてみる「スリー・グッド・シングス」などは、ポジティブ思考の定番トレーニングです。
カウンセリングでできること
仙台圏内でカウンセリングの利用をご検討中の方へ。
仙台泉メンタルサポートオフィスでは、ストレスや気分の落ち込みを軽減し、「自分をどう捉えるか」を一緒に見直していくサポートを行っています。
ポジティブ思考とは、「無理やり明るくふるまうこと」ではありません。
自分に対するまなざしを少しずつ柔らかくし、前向きな可能性に目を向けられるようになること。
そのための“こころの習慣”を育てていくことが、カウンセリングの目的でもあります。
最後に:現実と前向きさの“ちょうどよいバランス”を
自己認識が正確すぎることで、逆に心が疲れてしまうこともあります。ときには「少し楽観的なくらいがちょうどよい」のかもしれません。
「自分なんて…」と思ってしまう日も、「でも、できていることもある」と目を向けてみる。
その小さな視点の切り替えが、ストレスとうまく付き合う第一歩になります。
仙台泉メンタルサポートオフィスでは、こころの捉え方を丁寧に見つめ直し、前向きな変化をサポートしています。ご相談はお気軽にお問い合わせください。