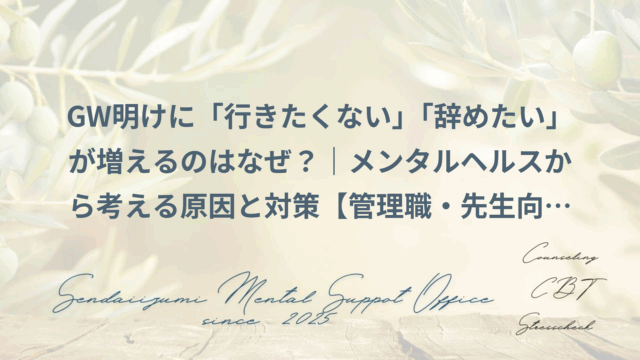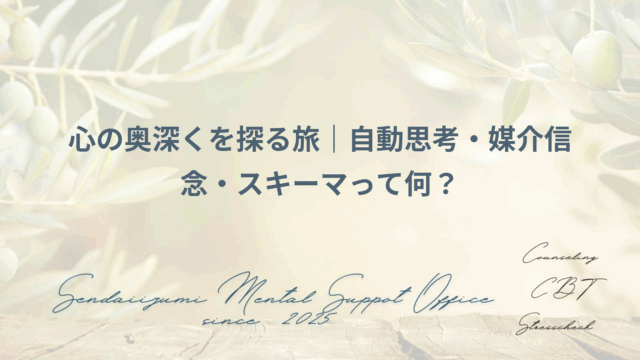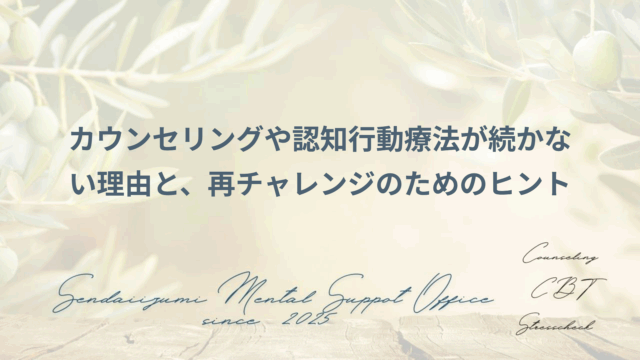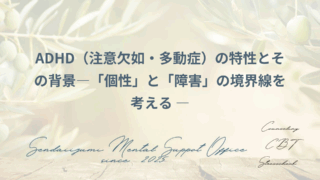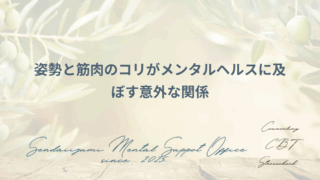ASD(自閉スペクトラム症)の特性と多様性
もくじ
ASDとは?― DSM-5-TRに基づく基本理解
ASD(自閉スペクトラム症)は、アメリカ精神医学会の診断基準DSM-5-TRにおいて、以下の2つの領域における持続的な困難を主な診断基準としています。
- 社会的コミュニケーションと対人関係の困難
- 限定された反復的な行動や興味、感覚の偏り
また、発達早期から症状がみられ、日常生活や社会生活において“明確な支障”がある場合に診断されることが前提となります。
しかし近年では、この“明確な支障”が診断レベルには至らないものの、「傾向はある」「困りごとはある」という、いわゆるグレーゾーンの方も増えており、注目されています。
日常に見られるASDの特性とは?
ASDの特性は、「できない」「障害」という固定的な視点で捉えるべきではありません。特性のあり方は人によって異なり、程度もさまざまです。ここでは、実際に日常生活でよく見られる3つの特徴を紹介します。
■ 対人関係の困難
- 暗黙のルール(空気を読む、あいまいな表現)を理解しづらい
- 相手の気持ちを汲み取ることが苦手
- 会話のキャッチボールが一方的になってしまう
- 雑談や世間話が苦手
■ 強いこだわりや興味の偏り
- 予定やルールが変わると混乱しやすい
- 自分なりの手順や方法に固執する傾向がある
- 興味のあるテーマに対して驚くほど集中するが、他に目を向けづらい
■ 感覚の過敏・鈍麻
- 音や光、匂いに敏感で、日常生活に支障が出る
- 触覚や食感に強いこだわりがあり、衣服や食べ物の選り好みが極端になる
- 感覚の刺激に反応しやすく、集中力が乱れやすい
診断名がつかなくても「困りごと」があれば支援の対象に
ASDの特性があっても、診断に至らない方々、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれる人たちの中にも、日常生活において対人関係や感覚刺激で困りごとを抱えている方は少なくありません。
こうした方々は、「自分は診断されていないから相談してはいけない」と感じてしまうこともあります。しかし、診断の有無にかかわらず、困っていることがあれば、それは十分に支援の対象となります。
ASD傾向がある方にとって重要なのは、自己理解を深め、自分に合った環境や対応方法を見つけることです。
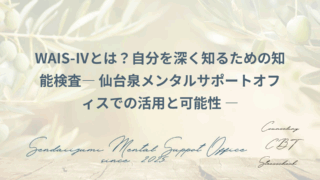
自己理解と周囲の配慮でできる支援
ASDの特性と付き合うには、本人の工夫と周囲の理解がカギになります。以下に、セルフケアと周囲ができる配慮を整理してみます。
■ 本人ができること
- 自分の「苦手な場面」や「ストレスのもと」をメモして傾向を把握
- 刺激を調整するツール(ノイズキャンセリングイヤホンやサングラスなど)を活用
- タスクを視覚化したり、予測可能なスケジュールを組むなどの工夫
■ 周囲ができること
- 指示を具体的に伝える(抽象的表現を避ける)
- 特性を否定するのではなく、「困っていること」に着目する
- 予定変更や環境変化がある場合は、事前に丁寧に説明する
専門家と一緒に整理するという選択肢も
ASDの傾向があっても、「うまく説明できない」「まわりにどう伝えればいいか分からない」と悩むこともあるでしょう。
当カウンセリングルーム(仙台)では、ASDを含む発達特性に関するご相談を承っております。WAIS-Ⅳなどの知能検査を通じて、認知特性の傾向を把握することで、自分自身の理解が深まり、必要な支援の方向性が明確になることもあります。
診断名の有無にとらわれず、「困っていること」「過ごしやすくなる工夫」を一緒に考えてみませんか?