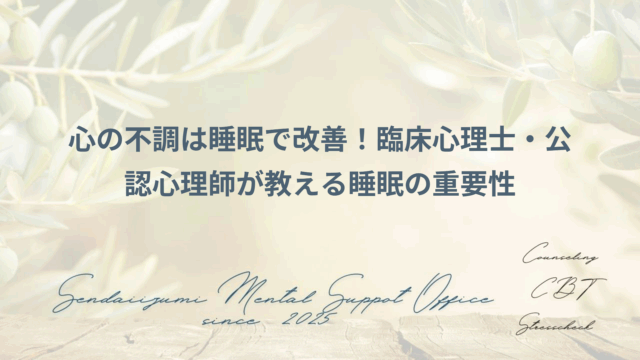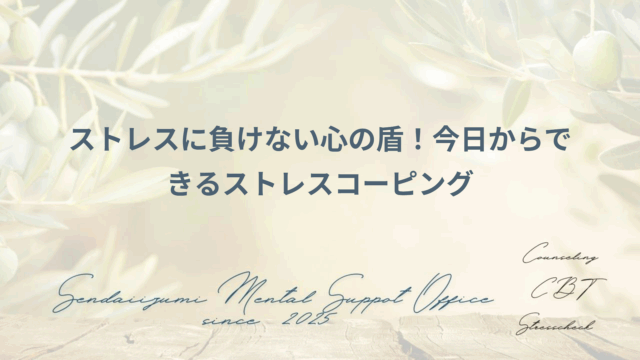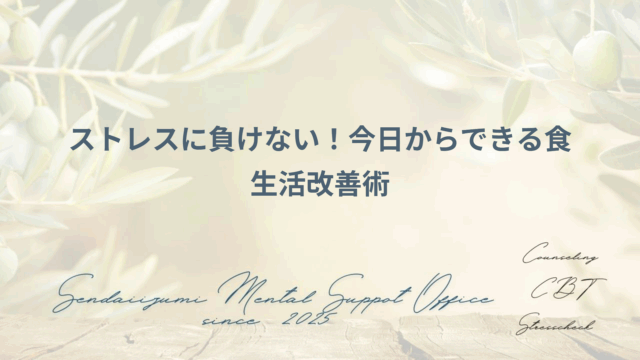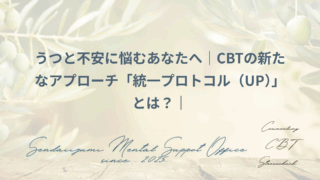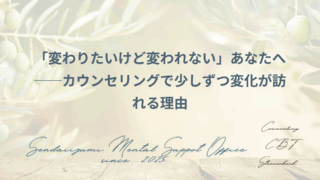どうして不安や落ち込みが続くのか?公認心理師/臨床心理士が解説する“気分のくせ”と対処法
もくじ
「頭の中で同じことを繰り返し考えてしまう」という相談
当オフィスには、不安や落ち込みが続くというご相談がよく寄せられます。
そうしたお話を丁寧に聴いていくと、共通して見られるのが「頭の中で何度も同じことを考えてしまう」という状態です。
「何度も同じ失敗を思い出してしまう」
「『こうすればよかった』と延々と考えてしまう」
「これから起こる最悪の事態ばかり想像してしまう」
このように、頭の中で否定的な内容をぐるぐると考えてしまう状態を、心理学では「反すう」と呼びます。
反すうは、悩みを解決するどころか、不安や落ち込みを長引かせる要因になります。
「反すう」は気分のくせ——その影響とは?
反すうは、もともと問題を解決しようとする心の働きのひとつです。
ですが、以下のような特徴をもつ反すうは、心の健康に悪影響を与えやすくなります。
- 過去の失敗や嫌な出来事を繰り返し思い返す
- 抽象的で終わりのない問い(「なぜ自分はダメなのか?」など)を繰り返す
- 思考が堂々巡りになり、行動が止まる
このような反すう思考が続くと、現実の問題解決から離れ、エネルギーを消耗し、自分への批判が強くなる傾向があります。
その結果、ますます行動ができなくなり、社会との関わりも減ってしまい、気分の落ち込みが強まるという悪循環に陥ってしまうのです。
「考えることをやめられない」自分を責めないために
「考えすぎてしまう」ことをコントロールできないと感じる方は多いです。
ですが、それは意志の弱さや性格の問題ではありません。
実は、反すうには「脳のくせ」「気分のくせ」としての側面があることが、心理学の研究でわかってきました。
特に落ち込んでいるときや不安が強いときは、自動的に反すうが起こりやすくなるのです。
「なぜ自分はこうなのか?」と考え込んでしまうとき、
その“問い”に答えようとするほど、ますます堂々巡りの思考に陥ってしまうことがあります。
反すう焦点化認知行動療法(RFCBT)とは?
この「反すう」に焦点を当てて開発されたのが、反すう焦点化認知行動療法(RFCBT: Rumination-Focused Cognitive Behavioral Therapy)です。
このアプローチでは、内容ではなく思考のあり方そのものに着目していきます。
RFCBTが重視するポイント:
- 「なぜこうなったのか」よりも、「今、何ができるか」を考える
- ネガティブな思考に“巻き込まれすぎない”距離感を育てる
- 具体的で目の前の行動に意識を向ける
- 思考のスタイル(抽象的/具体的)を切り替える練習
RFCBTでは、「思考を止めよう」と無理にするのではなく、
反すうが始まったときに、“そこから離れる技術”を身につけていくことを目指します。
これは、心の筋トレのようなもの。少しずつ繰り返すことで、思考のパターンに変化が生まれてきます。
反すうから抜け出すためにできること
ここでは、RFCBTの視点を取り入れたシンプルな対応例を3つご紹介します。
①「なぜ」ではなく「どうすれば?」と考えてみる
×:「なぜ自分はいつもこうなんだろう」
〇:「どうすれば今日は少し気分が楽になるかな?」
② “考えモード”から“行動モード”へ切り替える
反すうが始まったら、まずは立ち上がる/場所を変える/体を動かすなど、
体を使った行動で脳のギアを切り替えましょう。
③ 「今・ここ」に注意を向ける練習
マインドフルネスの考え方を取り入れて、
目の前にある音や感覚(飲み物の温度や光の色など)に意識を向けてみることも、思考の渦からの脱出に役立ちます。
反すうは“直せるくせ”です
長年、考えすぎに苦しんできた方でも、
反すうを減らす方法を身につけることで、気分が安定し、意欲や集中力が戻ってくるケースが多くあります。
心理療法は、そうした“こころのくせ”を誰かと一緒に見直しながら、少しずつ変えていく作業でもあります。
一人では難しいことも、専門家と協力すれば、より柔軟に乗り越えられるかもしれません。
お悩みの方へ
仙台泉メンタルサポートオフィスでは、反すうや不安、気分の落ち込みに焦点を当てた心理療法を行っています。
「頭の中がぐるぐるして止まらない」
「考えすぎて疲れてしまう」
「何をしても気分が晴れない」
そんなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
こころのくせに気づくことから、回復は始まります。
仙台でカウンセリングをお探しの方は、当オフィスのご利用を是非ご検討ください。