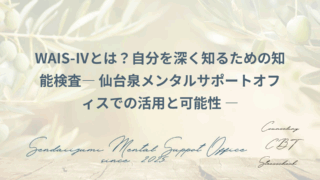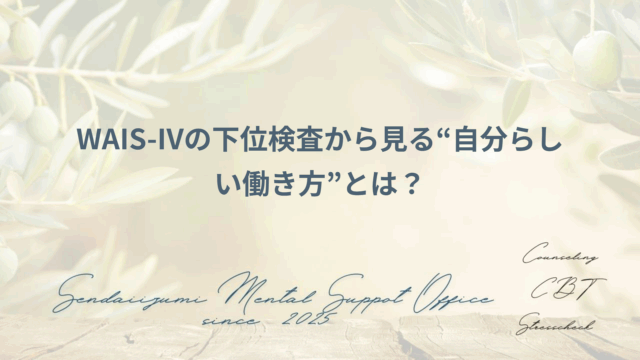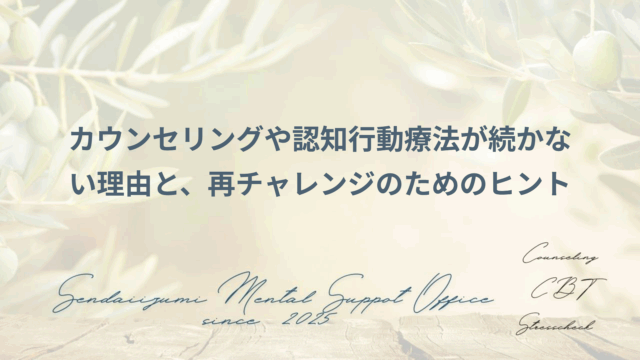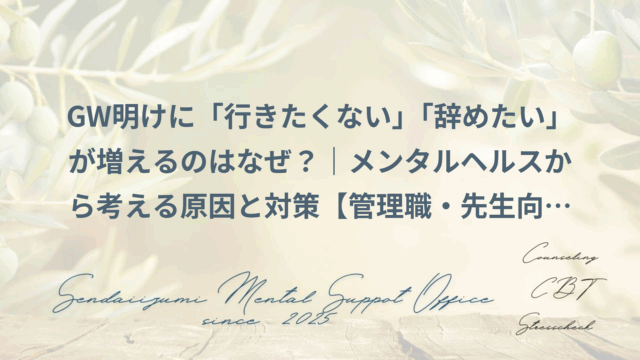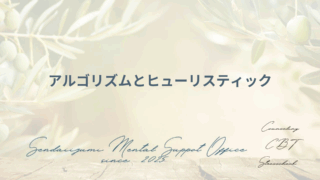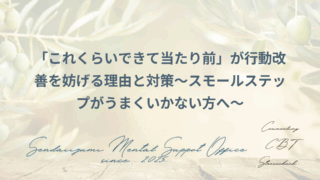今、なぜ「発達障害」が注目されるのか
ここ数年、「発達障害」という言葉を耳にする機会が急増しています。テレビやSNS、書籍や職場など、さまざまな場面で「発達障害」という言葉が使われ、時に自分や身近な人に当てはめて考える人も少なくありません。しかし、その一方で、発達障害の理解が十分に深まっていないまま、安易なラベリングや誤解が広がってしまうリスクもあります。
本記事では、発達障害が注目される背景や、正しい理解のために押さえておきたいポイントを整理していきます。
DSM-5-TRにおける発達障害の定義と診断基準
発達障害は、アメリカ精神医学会が定めた「DSM-5-TR(精神疾患の診断・統計マニュアル 改訂第5版・改訂版)」に基づき、以下のように定義されています。
発達障害とは、幼少期から現れる脳の発達に関わる特性に起因し、日常生活や社会生活において困難が生じる状態を指します。主に以下のような診断カテゴリーが含まれます。
主な発達障害の分類(DSM-5-TRより)
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 知的発達症(知的障害)
- 限局性学習症(学習障害)
- 運動障害(発達性協調運動障害など)
特にASDやADHDは、知名度が高まり、診断の相談を希望する方が増えています。ただし、診断には専門的な評価が必要であり、単なる自己判断やチェックリストだけで結論づけることはできません。
現代社会における発達障害の理解の広がり
発達障害が社会的に注目される背景には、いくつかの理由があります。
① 働き方・学び方の多様化
社会の多様化が進む中で、従来の画一的な環境が合わず、困りごとを感じやすい人が目立つようになっています。その結果、「生きづらさ」の背景に発達障害の特性が関わっている可能性が指摘されるケースが増えています。
② 障害理解と合理的配慮の推進
学校や職場における合理的配慮の必要性が浸透しつつあります。そのため、特性理解や診断の有無を問わず、個々の特性に合わせた支援を求める声も強まっています。
③ 情報の氾濫と自己理解のニーズ
インターネットやSNSで、発達障害に関する情報が簡単に手に入る時代です。自己理解を深めたい、困りごとを整理したい、というニーズから検査やカウンセリングを希望する方も増えています。
安易なラベリングや「発達障害ブーム」への冷静な視点
一方で注意が必要なのは、「発達障害」という言葉が一人歩きし、必要以上にラベルを貼ってしまう風潮です。
例えば…
- 少し不器用だからといって「発達障害かもしれない」と決めつける
- 苦手なことが目立つ子どもにすぐ「発達障害」と結論づける
- 「発達障害=個性」という極端な解釈に走る
このような偏った見方は、かえって自己理解や支援の妨げになる場合があります。
発達障害の診断や特性理解は、あくまで「自分らしく生きるためのヒント」として捉えることが重要です。診断名そのものがゴールではなく、自分の得意・不得意を客観的に把握し、日常や仕事で活かせる工夫を見つけていくことが本質です。
まとめ:特性理解を生きやすさにつなげる
発達障害が注目される背景には、社会の多様化や自己理解のニーズがあります。しかし、表面的な情報だけで結論を出したり、必要以上に「障害」にこだわりすぎるのは本来の目的から外れてしまいます。
仙台泉メンタルサポートオフィスでは、WAIS-Ⅳ(知能検査)を活用し、自分の特性や思わぬ困りごとを客観的に把握するサポートを行っています。診断を求めるのではなく、「自分らしい工夫」や「生きやすさのヒント」を一緒に見つけていくことを大切にしています。
発達障害という言葉にとらわれすぎず、一人ひとりの特性に目を向けた、しなやかな自己理解を目指していきましょう。