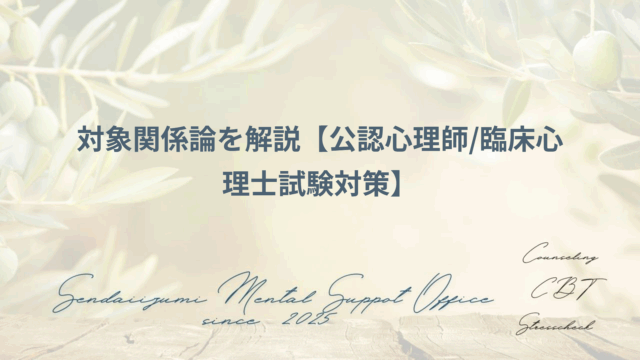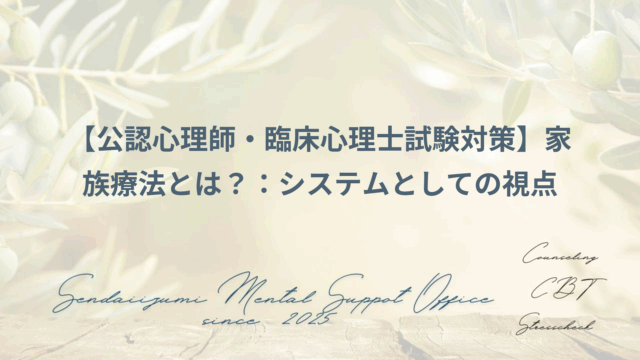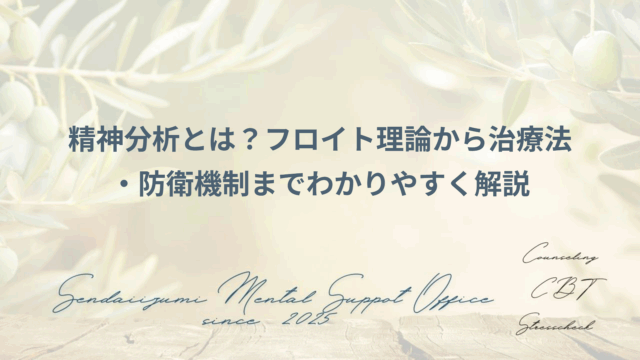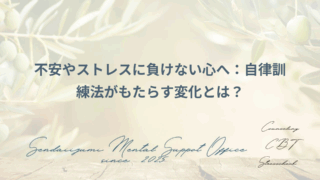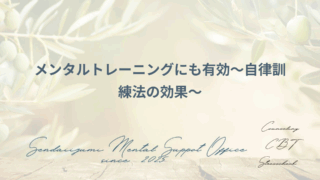認知行動療法(CBT)の基本用語を解説
もくじ
- 1 認知行動療法(CBT)とは?
- 2 CBTの基本用語集
- 2.1 1. 認知 (Cognition)
- 2.2 2. スキーマ (Schema)
- 2.3 3. 自動思考 (Automatic Thoughts)
- 2.4 4. 認知の歪み (Cognitive Distortions)
- 2.5 5. 認知再構成 (Cognitive Restructuring)
- 2.6 6. 行動実験 (Behavioral Experiment)
- 2.7 7. 行動活性化 (Behavioral Activation)
- 2.8 8. アサーション・トレーニング (Assertion Training)
- 2.9 9. リラクセーション法 (Relaxation Techniques)
- 2.10 10. ホームワーク (Homework)
- 3 学習のポイント
認知行動療法(CBT)とは?
CBTは、私たちの「気分(感情)」「行動」「思考(認知)」の3つは相互に関連しており、特に認知(考え方や物事の捉え方)と行動に焦点を当て、それらを変化させることで心理的な問題の解決を目指す心理療法です。
うつ病、不安障害、パニック障害、強迫性障害など、幅広い精神疾患や心の問題に効果があるとされており、エビデンスに基づいた心理療法として知られています。
CBTの基本用語集
1. 認知 (Cognition)
物事をどのように捉え、解釈するかという心の働き全般を指します。CBTでは、この認知が感情や行動に大きな影響を与えると捉えます。
2. スキーマ (Schema)
過去の経験に基づいて形成された、個人が世界や自分自身、他者を理解するための基本的な「枠組み」や「信念」のことです。深いレベルの認知であり、普段は意識されにくいものですが、私たちの感情や行動に強い影響を与えます。 例: 「私は誰からも認められない存在だ」「世の中は常に危険に満ちている」
3. 自動思考 (Automatic Thoughts)
特定の状況において、自動的に頭に浮かんでくる思考やイメージのことです。意識しないうちに瞬間的に生じるため、「無意識のつぶやき」とも呼ばれます。CBTでは、この自動思考を特定し、吟味することが治療の第一歩となることが多いです。 例: (プレゼンテーション中に)「どうせ失敗する」「バカにされる」
4. 認知の歪み (Cognitive Distortions)
自動思考やスキーマの中に含まれる、現実を不正確に、あるいは非論理的に解釈してしまう思考パターンのことです。多くの種類があり、それぞれの歪みに特徴があります。
- 全か無か思考 (All-or-Nothing Thinking / Dichotomous Thinking): 物事を完璧か、そうでなければ完全に失敗か、という極端な二択で捉える思考。「白か黒か思考」とも呼ばれます。 例: 「少しでもミスしたら、私の人生は完全に失敗だ」
- 過剰な一般化 (Overgeneralization): 一つのネガティブな出来事から、全てが同じように悪い結果になると結論づける思考。 例: 「一度デートに失敗したから、もう一生誰ともうまくいかない」
- 心のフィルター (Mental Filter): ポジティブな情報を無視し、ネガティブな情報ばかりに焦点を当てる思考。 例: 褒められたことは忘れ、一つだけ指摘された欠点ばかりを気にする。
- 結論の飛躍 (Jumping to Conclusions): 根拠がないのに、ネガティブな結論に飛びついてしまう思考。
- 心の読みすぎ (Mind Reading): 相手が何を考えているかを勝手に決めつける。 例: 「あの人は私を嫌っているに違いない」
- 先読みの誤り (Fortune-telling): 未来をネガティブに決めつける。 例: 「どうせ試験に落ちるに決まっている」
- 拡大解釈と過小評価 (Magnification and Minimization): 自分の失敗や他人の成功を過剰に大きく捉え、自分の成功や他人の失敗を過小に評価する思考。 例: 「私の失敗は取り返しがつかないほど大きい」「あの人が成功したのは運が良かっただけ」
- 感情的推論 (Emotional Reasoning): 自分が感じる感情をそのまま現実と捉える思考。 例: 「不安だから、きっと危険なことが起きるに違いない」
- べき思考 (Should Statements): 自分や他人が「~すべき」「~ねばならない」という厳しいルールに縛られる思考。 例: 「常に完璧に仕事をこなすべきだ」
- レッテル貼り (Labeling): 自分の行動や他人の行動を、否定的な固定概念やレッテルに当てはめて捉える思考。 例: 「私は怠け者だ」「彼は最低な人間だ」
- 個人化 (Personalization): 外部の出来事や他人の行動の原因を、自分に責任があると過剰に捉える思考。 例: 「あの人が不機嫌なのは、きっと私が何か悪いことをしたせいだ」
5. 認知再構成 (Cognitive Restructuring)
自動思考やスキーマに含まれる「認知の歪み」を特定し、それが現実と合っているかを吟味し、より現実的で適応的な認知へと修正していくプロセスです。CBTの中心的な技法の一つです。
6. 行動実験 (Behavioral Experiment)
「もし〇〇したら、きっと××になるだろう」というクライエントの仮説(予測)を、実際に具体的な行動を通して検証する技法です。現実の経験を通して、非適応的な信念を修正することを目指します。 例: 「人前で話すと必ず笑われる」という自動思考に対し、実際に短時間だけ話してみて、どうなるか試してみる。
7. 行動活性化 (Behavioral Activation)
うつ状態などで活動量が低下しているクライエントに対し、意図的に活動を増やすことで、ポジティブな感情や達成感を体験させ、抑うつ気分を改善する技法です。
8. アサーション・トレーニング (Assertion Training)
相手の権利や感情を尊重しながら、自分の意見や要求、感情を適切に表現するコミュニケーションスキルを身につけるトレーニングです。自己主張が苦手な方に効果的です。
9. リラクセーション法 (Relaxation Techniques)
不安やストレスによって生じる身体的な緊張を緩和するための技法です。漸進的筋弛緩法や呼吸法などが含まれます。
10. ホームワーク (Homework)
セッション中に学んだことや、目標とした行動を、次のセッションまでに日常生活で実践してもらう課題です。CBTでは、セッション外での実践が治療効果を高める上で非常に重要だと考えられています。
学習のポイント
- 用語の定義を正確に覚える: 試験では用語の定義そのものが問われることもあります。
- 具体例と結びつける: それぞれの用語がどのような状況で現れるのか、具体的な例をイメージしながら学習しましょう。
- 自分の経験に当てはめる: 自身の日常で起こる感情や思考をこれらの用語に当てはめて考えてみると、理解が深まります。
- 理論と実践の繋がりを意識する: 各用語が、CBTのどのようなプロセスや技法に活用されるのかを理解することが重要です。
CBTは非常に実践的な心理療法であり、その基本用語を習得することは、試験対策だけでなく、将来の臨床実践においても不可欠な土台となります。