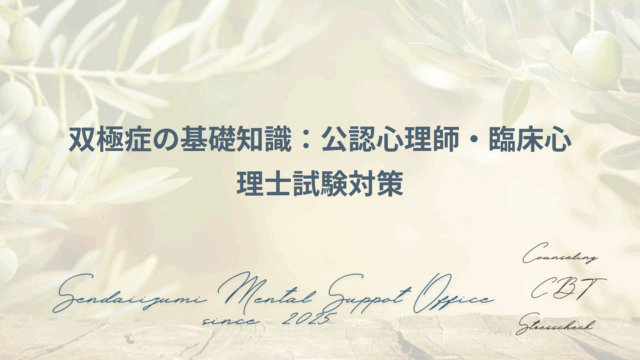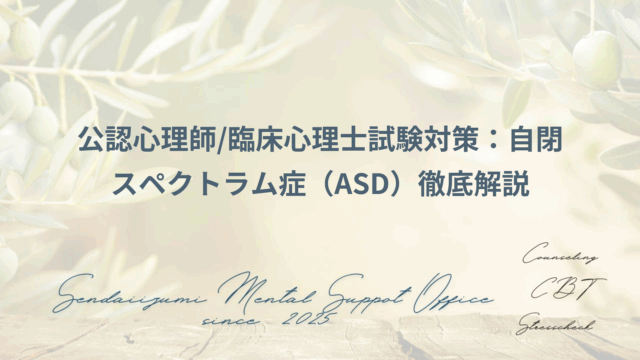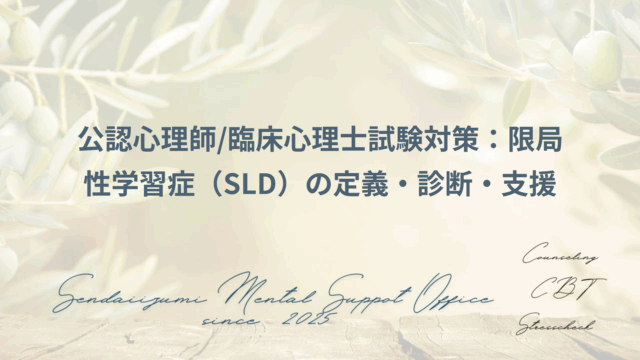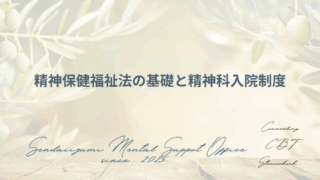公認心理師/臨床心理士試験対策:統合失調症
もくじ
1. 統合失調症の概要と疫学
- 概要: 以前は「精神分裂病」と呼ばれていましたが、現在は「統合失調症」という名称が使われています。この名称変更は、偏見をなくし、病気への理解を深めることを目的としています。
- 疫学: 日本を含め、世界中の**人口の約1%**が罹患するとされています。これは決して珍しい病気ではなく、誰もがなりうる可能性のある疾患だということを理解しておきましょう。
2. 統合失調症の主要な症状
統合失調症の症状は、大きく分けて「陽性症状」「陰性症状」「中間症状」の3つに分類されます。
(1) 陽性症状
「無いはずのものがある」状態を指します。現実にはないものを体験したり、ありえないことを信じ込んだりする症状です。
- 幻覚: 最も多いのは「幻聴」(悪口や命令が聞こえる)。
- 妄想: 証拠がないにも関わらず、訂正不能な誤った確信を持つこと。
- 自我障害: 自分が操られているように感じたり、自分と外界の境目が曖昧になったりする感覚。
(2) 陰性症状
「あるはずのものが無い」状態を指します。健常者であれば持っているはずの意欲や感情の表現が乏しくなる症状です。
- 意欲低下
- 感情の平板化: 喜怒哀楽の感情が鈍くなること。「感情鈍麻」とも呼ばれます。
- 注意力低下
- 自発性減少
(3) 中間症状
思考の連続性が途切れたり、話がまとまらなくなったりする症状です。
- 連合弛緩: 思考のまとまりがなくなること。
- 滅裂言語: 言葉が支離滅裂になること。
- 言葉のサラダ: まったく意味をなさない言葉の羅列になること。
3. ブロイラーの4A(統合失調症の基本症状)
統合失調症の基本的な症状として、ブロイラーが提唱した以下の4つ(4A)も試験では重要です。
- 連合弛緩 (Association): 思考のまとまりのなさ。
- 感情の平板化 (Affective Disturbance): 喜怒哀楽の感情が鈍い。
- 自閉性 (Autism): 外界との接触を避け、殻に閉じこもる傾向。
- 両価性 (Ambivalence): 同一の対象に、相反する感情を同時に抱くこと。
4. シュナイダーの1級症状
シュナイダーが提唱した1級症状は、統合失調症の診断において特に重要とされる陽性症状です。全てを暗記する必要はありませんが、代表的なものを覚えておきましょう。
- 考想化声: 自分の考えが声になって聞こえるという特殊な形の幻聴。
- 対話形式の幻聴: 複数の声が自分について話している幻聴。
- 思考吹聴: 自分の考えが他人に知れ渡っていると感じる妄想。
5. 統合失調症の薬物療法(抗精神病薬)
統合失調症の治療において、薬物療法は非常に重要な位置を占めます。特に、幻覚や妄想といった陽性症状の改善には、抗精神病薬が用いられます。
(1) ドーパミン仮説
統合失調症の発症には、脳内の神経伝達物質である**ドーパミン(Dopamine)**の過活動が関与しているという説が有力です。
- 陽性症状の改善: 抗精神病薬の多くは、このドーパミンの過活動を抑制することで、幻覚や妄想といった陽性症状の軽減を目指します。
(2) 主な抗精神病薬の分類
抗精神病薬は、主に以下の2種類に分けられます。
- 定型抗精神病薬(第一世代抗精神病薬)
- 主にドーパミンD2受容体を遮断することで陽性症状を抑制します。
- 副作用: 錐体外路症状(パーキンソン病に似た手足の震え、体のこわばり、じっとできないアカシジアなど)が出やすい傾向があります。
- 非定型抗精神病薬(第二世代抗精神病薬)
- ドーパミンだけでなく、セロトニンなど他の神経伝達物質にも作用することで、陽性症状・陰性症状の両方に効果があるとされます。
- 副作用: 定型薬に比べて錐体外路症状は出にくいですが、代謝系(体重増加、血糖値上昇など)や心血管系の副作用に注意が必要です。
臨床心理士や公認心理師は薬を処方することはできませんが、クライエントがどのような薬を服用し、どのような副作用の可能性があるかを理解しておくことは、多職種連携や心理支援を行う上で不可欠です。
6. 試験対策のポイント
- 症状の分類を正確に覚える: 陽性、陰性、中間症状のどれに分類されるかを確実に覚えましょう。
- 4Aと1級症状を理解する: ブロイラーの4Aとシュナイダーの1級症状は、統合失調症を特徴づける重要な概念です。それぞれの定義を正確に理解しましょう。
- ドーパミン仮説と抗精神病薬の作用機序: 陽性症状とドーパミンの関係、そして定型/非定型抗精神病薬の作用の違いや副作用の傾向を理解しておきましょう。
- 統合失調症の歴史的経緯: 名称変更の背景や、過去の呼び名も覚えておきましょう。
- 他の精神疾患との鑑別: 幻覚や妄想は、他の精神疾患でも見られることがあります。統合失調症に特徴的な症状を理解することで、鑑別問題に対応できるようになります。
統合失調症は、クライエントの生活に大きな影響を与える疾患であり、心理職としてその理解は不可欠です。この解説を参考に、知識を整理し、今後の学習に役立ててください。