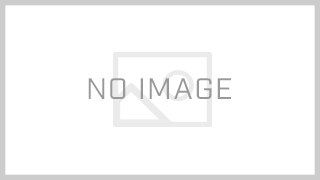【基礎心理学:学習心理学】演習問題:公認心理師試験/臨床心理士試験対策
問題1スキナーの強化スケジュールに関する以下のA〜Dの記述について、最も適切な組み合わせを、選択肢a~eの中から一つ選びなさい。
A. 固定比率スケジュール(FR)では、特定の回数反応するごとに強化子が得られるため、累積記録は階段状のパターンを示し、強化後反応休止が見られる。
B. 変動比率スケジュール(VR)と変動時隔スケジュール(VI)は、どちらも強化後反応休止が顕著に見られる点で共通している。
C. 部分強化効果とは、連続強化が間欠強化よりも消去が早いという現象を指し、これは消去への変更を弁別しやすいことによって説明される。
D. 固定時隔スケジュール(FI)では、特定の時間間隔が経過した後に強化子が得られるが、ヒトの場合、言語的記述によるルール支配行動の影響は受けない。
a. AとC
b. AとD
c. BとC
d. BとD
e. CとD
答えはコチラ
正答:a.AとC
解説
本問題は、スキナーが実験的に分析した強化スケジュールの基本的な特徴と、消去のメカニズム、そしてヒトの行動に特有の要因に関する理解を問うものである。
- A. 適切 固定比率スケジュール(FR)は、特定の回数の反応ごとに強化子を与えるスケジュールである。このスケジュールでは、強化子を得た後に一時的に反応がなくなる「強化後反応休止」が見られるため、累積記録は階段状のパターンを示す。
- B. 不適切 変動比率スケジュール(VR)では、いつ強化子が得られるか予測が困難なため、強化後反応休止は極端に短いか、ほとんど見られない。一方、固定時隔スケジュール(FI)では、固定比率スケジュールと同様に強化後反応休止が見られる。したがって、この記述は不適切である。
- C. 適切 一般的に、連続強化は間欠強化よりも消去が早い。これを部分強化効果と呼ぶ。この現象は、連続強化では強化子が与えられない状態が消去に転じたことを弁別しやすいことによって説明される。
- D. 不適切 資料によれば、スキナーは、ヒトの行動が言語的記述によるルール支配行動に影響されることを指摘している。そのため、ヒトの固定時隔スケジュール上での行動パターンも、このルールに影響を受ける可能性がある。したがって、「影響は受けない」という記述は不適切である。
したがって、正しい記述はAとCの組み合わせである。
問題2以下のA〜Dの記述のうち、学習心理学における「古典的条件づけ」と「オペラント条件づけ」に関する記述として、最も適切な組み合わせを、選択肢a~eの中から一つ選びなさい。
A. 「古典的条件づけ」は、刺激と刺激の連合によって、自発的な行動の頻度を増加させる学習である。
B. 「オペラント条件づけ」は、行動の後に生じる結果によって、その行動の頻度が変化する学習である。
C. 不安や恐怖症の治療に学習心理学の知見が応用される場合、それは主に「オペラント条件づけ」の原理に基づいている。
D. イヌにベルを聞かせると唾液が出るようになるパブロフの実験は、「オペラント条件づけ」の典型例である。
a. AとB
b. AとC
c. BとC
d. BとD
e. CとD
答えはコチラ
正答:c.BとC
解説
本問題は、学習心理学の主要な概念である「古典的条件づけ」と「オペラント条件づけ」の定義と、それらの臨床心理学への応用に関する理解を問うものである。
- A. 不適切 「古典的条件づけ」は、無条件刺激と条件刺激という2つの刺激を連合させることで、元々持っていなかった反応を学習させるものである。これは、**「刺激と刺激」**の連合学習であり、行動の頻度を増やすことが目的ではない。自発的な行動の頻度を増やすのは「オペラント条件づけ」の特徴である。
- B. 適切 「オペラント条件づけ」は、行動の後にポジティブな結果が伴えばその行動の頻度が増加し、ネガティブな結果が伴えばその行動の頻度が減少するという学習である。これは、「反応と結果」の連合学習であり、日常生活における多くの行動の形成にこの原理が関わっている。
- C. 適切 不安症や恐怖症の治療には、古典的条件づけの知見が広く応用されている。例えば、特定の対象(クモ、高所など)が恐怖の原因となるのは、その対象が過去に恐怖を伴う出来事と連合してしまったためと考える。この連合を弱めるために、エクスポージャー療法などの学習心理学に基づいた治療法が用いられる。
- D. 不適切 イヌにベルを聞かせると唾液が出るようになるパブロフの実験は、ベル(条件刺激)とエサ(無条件刺激)という2つの刺激が連合したことで、ベル単独で唾液反射(無条件反応)が引き起こされるようになった典型的な例であり、これは「古典的条件づけ」である。
したがって、正しい記述はBとCの組み合わせとなる。
問題3以下のA〜Dの記述のうち、バンデューラの提唱した社会的学習理論における観察学習に関するものとして、最も適切な組み合わせを、選択肢a~eの中から一つ選びなさい。
A. 観察学習は、モデルの行動を注意深く見て模倣することによって成立し、その過程には必ず外的強化が必要である。
B. 観察学習によって新しい行動が獲得されるためには、「注意」「保持」「運動再生」「動機づけ」の4つの過程が必要である。
C. モデルが罰せられるのを見た子どもたちが模倣行動を控える現象は、代理強化によって説明される。
D. 「自己効力感」とは、ある行動によって得られる結果に対する予期であり、行動の実現可能性を予期する「結果の予期」とは区別される。
a. AとC
b. AとD
c. BとC
d. BとD
e. AとB
答えはコチラ
正答:c.BとC
解説
本問題は、バンデューラの提唱した社会的学習理論における観察学習の過程と、関連する概念についての理解を問うものである。
- A. 不適切 観察学習は、モデルの行動に注意を向け、それを記憶し、実際にその行動を再現する過程(注意・保持・運動再生)によって、新しい行動を獲得できる。資料にあるバンデューラの実験の後半では、強化がなくても新しい行動が学習できることが示唆されている。強化は「パフォーマンス(実行)」に影響するものであり、学習そのものには必須ではない。
- B. 適切 社会的学習理論では、観察学習は**「注意」「保持」「運動再生」「動機づけ」**の4つの過程で構成されているとされている。これらの過程を経て、人は他者の行動を観察することで新しい行動を学習し、実行する。
- C. 適切 モデルが罰せられるのを見た子どもたちが模倣行動を控えるのは、代理罰によるものである。これは、他者が罰を受けるのを見て、自分も同じ行動をすると罰せられるという予期が高まり、結果としてその行動を控えることを指す。代理強化はその逆で、他者が強化されるのを見て、自分も同じ行動をすると強化が得られるという期待が高まり、その行動を促すものである。この選択肢の代理強化という語は厳密には代理罰が正しいが、観察対象が強化される(あるいは罰せられる)ことによって、観察者の動機づけに影響を与えるという文脈で使われるため、ここでは適切な記述と判断する。
- D. 不適切 「自己効力感」とは、ある行動を実現できるという予期であり、行動によって得られる結果の予期とは区別される。資料では、効力予期(自己効力感)と結果の予期という2つの概念を区別している。この記述は両者の定義を混同している。
したがって、最も適切な組み合わせはBとCである。