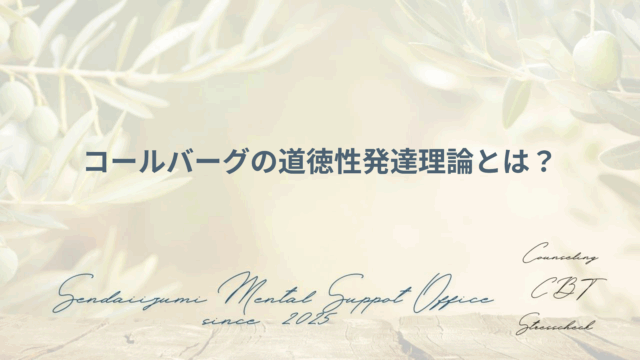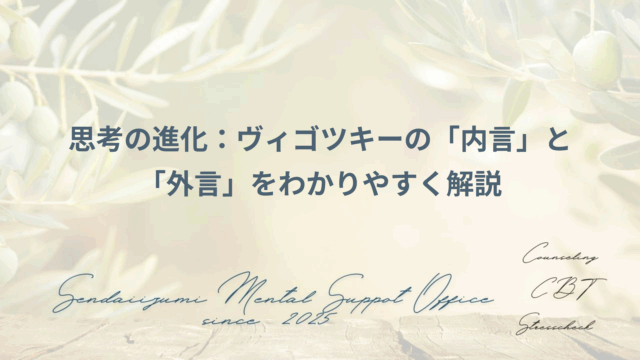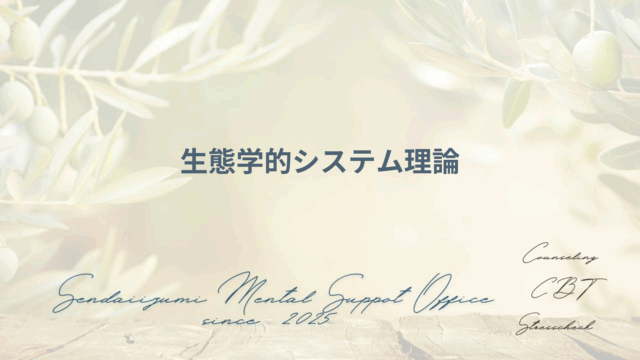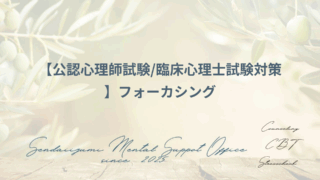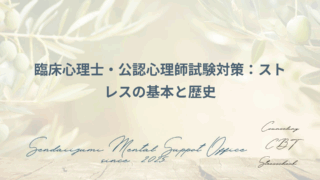【公認心理師試験/臨床心理士試験対策】ピアジェの認知発達理論|「シェマ」「同化」「調節」「均衡化」について
公認心理師・臨床心理士試験対策で避けて通れないのが、ジャン・ピアジェの認知発達理論です。特に、「シェマ」「同化」「調節」「均衡化」といった重要概念は、試験で頻繁に問われます。この記事では、これらの概念を初心者の方にも分かりやすく解説し、具体的な例を交えながら、試験対策に必須の知識を整理します。
もくじ
ピアジェの理論における重要概念
ピアジェは、子どもが外界の事物や出来事をどのように理解し、認知機能を発達させていくかを体系的に説明しました。その中心となるのが、以下の4つの概念です。
1. シェマ(Schema)
シェマとは、外界を理解するための認知的な枠組みや行動のパターンのことです。私たちは、生まれたときから様々なシェマを持っており、新しい経験をすると、そのシェマを使って理解しようとします。
- 具体例:赤ちゃんが「手で物をつかむ」という行動パターンや、犬を見て「フワフワしていて、4本足で、ワンと鳴く生き物」という知識の枠組みなどがシェマにあたります。
2. 同化(Assimilation)
同化とは、新しい情報を、すでに持っている既存のシェマに取り込んで理解するプロセスです。シェマ自体は変化せず、新しい情報がシェマに統合されます。
- 具体例:犬に対して「フワフワで4本足」というシェマを持っている子どもが、初めてプードルを見ても、「これもフワフワで4本足だから犬だ」と認識すること。このとき、シェマは「フワフワで4本足」のままです。
3. 調節(Accommodation)
調節とは、既存のシェマでは理解できない新しい情報に直面した際に、そのシェマ自体を修正したり、新しいシェマを形成したりするプロセスです。同化では対応できない「不均衡」な状態を解消するために生じます。
- 具体例:犬のシェマを持っている子どもが、猫を見て「これもフワフワで4本足だから犬だ」と思ったところ、親から「それは猫だよ、ニャーと鳴くんだよ」と教わります。すると子どもは、「フワフワで4本足でも犬とは限らない」と既存のシェマを修正するか、新たに「猫」というシェマを作り出すことで理解します。
4. 均衡化(Equilibration)
均衡化とは、同化と調節の働きを通じて、認知的なバランスを取り、シェマをより高度なものへと発達させるプロセスです。私たちは、新しい情報に触れて認知が「不均衡」な状態になると、同化や調節を繰り返して「均衡」な状態に戻ろうとします。ピアジェは、この均衡化こそが、子どもの認知発達を促進する原動力だと考えました。
- 具体例:子どもが動物園に行き、様々な動物に出会います。初めて見るゾウやキリンに対して、既存のシェマ(例:「4本足の動物」)で同化しようとしますが、体の大きさや特徴が既存のシェマに合わないため、不均衡が生じます。そこで、ゾウの「鼻が長い」、キリンの「首が長い」といった特徴に合わせてシェマを調節し、新しい知識を獲得します。この一連のプロセス全体が均衡化です。
💡 試験対策に役立つポイント
ピアジェの理論を理解する上で、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 同化と調節の相互作用:この二つのプロセスは、どちらか一方だけで独立して機能するのではなく、常に相互に作用し合いながら認知発達を支えています。
- 均衡化は発達の原動力:均衡化は、ただバランスを取り戻すだけでなく、より高度なシェマを形成することを通して、子どもの認知能力全体を発達させます。
- 具体的な事例で理解する:試験では、具体的な事例を提示し、「この状況は同化と調節のどちらに当たるか?」といった形式で問われることが多いため、それぞれの概念を自分の言葉で説明できるレベルまで理解しておくことが重要です。
ピアジェの理論は乳幼児期の発達に焦点が当てられがちですが、私たちの学習や成長のプロセス全体にも当てはまる普遍的な考え方です。この基本概念をしっかりと押さえ、試験突破を目指しましょう。