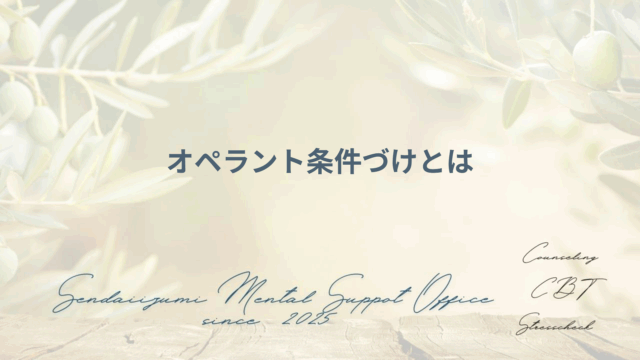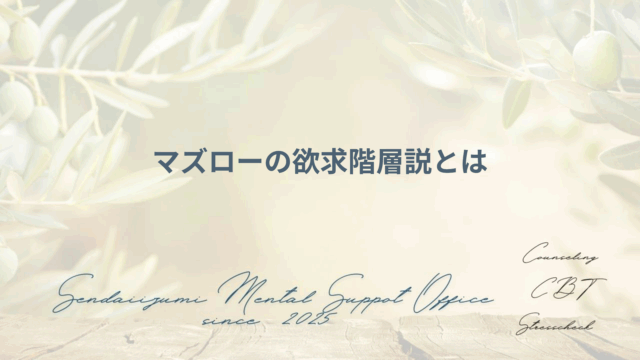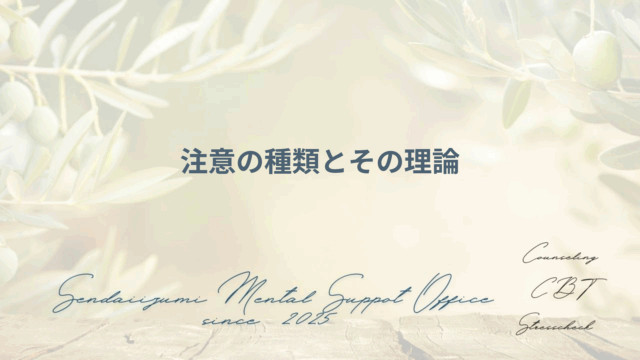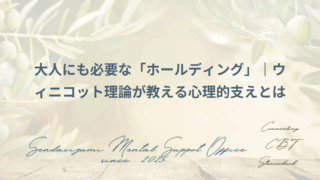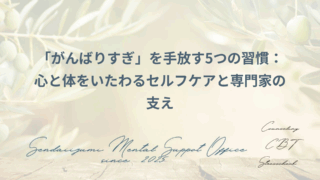記憶の種類|アトキンソンとシフリンのモデルと近年の理解
人間の記憶の仕組みは、心理学の基礎知識として公認心理師や臨床心理士試験でも頻出です。本記事では、代表的な「二重貯蔵モデル」や最新の「ワーキングメモリー理論」をわかりやすく整理します。
もくじ
1. 記憶の基本モデル|多重貯蔵モデル
アトキンソンとシフリン(Atkinson & Shiffrin, 1968)は、以下のように人間の記憶を三段階に分けて説明しました。これが「多重貯蔵モデル」と呼ばれるものです。
| 記憶の種類 | 特徴 | 保持時間 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 感覚記憶 | 五感を通じて瞬間的に保持 | 1秒前後 | 非常に大きい |
| 短期記憶 | 意識にのぼる情報を保持 | 約15~30秒 | 7±2個(ミラーの法則) |
| 長期記憶 | 理論上、無制限・半永久的に保持 | 非常に長い | 上限なし |
2. 感覚記憶(Sensory Memory)
五感を通じて得た膨大な情報を、一瞬だけ保持するシステムです。
- アイコニックメモリー(視覚刺激の記憶):約1秒
- エコーイックメモリー(聴覚刺激の記憶):数秒
※ スパーリング(Sperling)の実験により、感覚記憶の容量と持続時間が示されました。
👉 注意が向けられた情報のみが次の短期記憶へ送られます。
3. 短期記憶(Short-Term Memory)
意識的に情報を保持・処理する領域で、保持時間は約15~30秒。容量には限界があります(7±2の法則/ミラー)。
短期記憶を長く保つ方法
- 維持リハーサル
繰り返し唱えるなどして一時的に保持時間を伸ばす(例:電話番号を覚える) - 精緻化リハーサル
既存の知識と結びつけて意味付けし、長期記憶への転送を促す
4. 長期記憶(Long-Term Memory)
半永久的に保持される記憶。情報は次のように分類されます。
| 分類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 宣言的記憶 | 言語で説明できる記憶 | 意味記憶・エピソード記憶 |
| 非宣言的記憶 | 言語化が難しい技能や感覚の記憶 | 手続き記憶・プライミング |
宣言的記憶
- 意味記憶:知識、概念、常識(例:首都の名前、数学の公式)
- エピソード記憶:個人の体験や出来事(例:昨日の食事、旅行の思い出)
非宣言的記憶
- 手続き記憶:運動技能や習慣(例:自転車の乗り方)
- プライミング:先行情報が後続の判断に影響(例:前に見た広告が購買行動に影響)
5. ワーキングメモリー(作動記憶)
単なる短期記憶ではなく、情報処理の「作業場」としての機能を重視する考え方です。
バドリーのワーキングメモリーモデル
| 構成要素 | 役割 |
|---|---|
| 中央実行系 | 注意の制御、情報の統合 |
| 音韻ループ | 言語的情報の保持・処理(例:心の中の繰り返し) |
| 視空間スケッチパッド | 視覚・空間情報の保持・処理 |
| エピソードバッファ | 長期記憶との結びつき、情報の統合 |
👉 読解、計算、推論など、複雑な認知活動を支える重要なシステムです。
まとめ|記憶理解は試験対策・実生活にも役立つ
記憶の仕組みは、公認心理師・臨床心理士試験はもちろん、学習法や仕事の効率化にも直結します。ぜひ基本モデルを理解し、効果的な記憶法に活用してください。