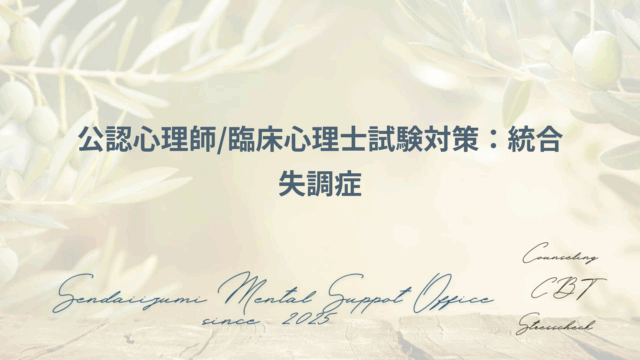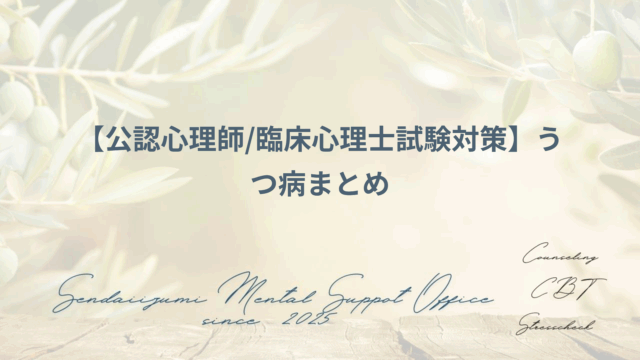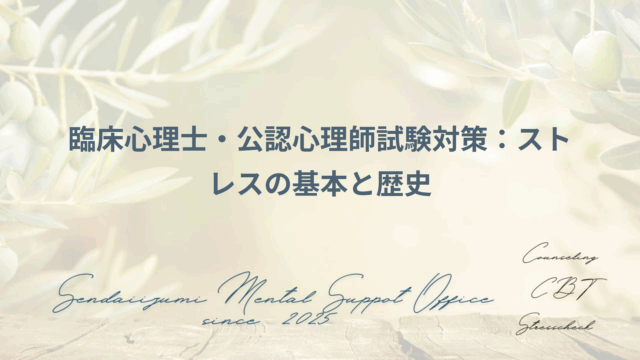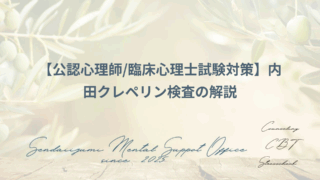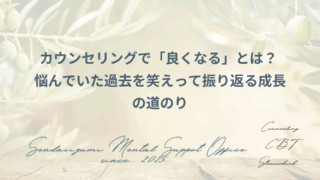【公認心理師/臨床心理士試験対策】ADHD(注意欠如多動症)の特性、診断基準、原因を解説
もくじ
はじめに
注意欠如多動症(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder:ADHD)は、神経発達症(発達障害)の一つであり、不注意と多動性・衝動性を主な特性とする神経発達症です。小児期に発現し、成人期まで持続することが多く、日常生活や社会生活に大きな支障をきたす場合があります。試験対策としては、その特性の現れ方や、DSM-5-TRに基づく診断基準を正確に理解することが重要です。
1. ADHDの主要な特性と臨床像
ADHDの特性は、「不注意」と「多動性・衝動性」の二つの領域に分類されます。どちらか一方が顕著な場合と、両方が併存する場合があり、臨床像は個人によって大きく異なります。
| 特性分類 | 特徴の例 | 成人期における現れ方 |
| 不注意(Inattention) | 集中できない、気が散りやすい、物をなくしやすい、順序立てて活動に取り組めない(計画性の欠如)。 | 成人期でも持続しやすい。遅刻、予定忘れ、書類の紛失、仕事でのケアレスミス、見立ての甘さなどとして現れる。 |
| 多動性・衝動性(Hyperactivity and Impulsivity) | じっとしていられない(多動)、静かにすることができない、待つことが苦手(衝動性)、衝動的な感情・行動を抑えられない。 | 大人になるにつれて目立たなくなる傾向がある(多動は内的な落ち着きのなさとして残ることがある)。衝動買い、不用意な発言、感情の爆発などとして現れる。 |
【注意点】
- 特性から派生する苦手さがある一方で、アイデアが豊富であったり、高いコミュニケーション能力を持つなど、強みを発揮できる側面も多くあります。
- ADHDは、自閉スペクトラム症(ASD)や限局性学習症(SLD)などの他の発達障害特性を併せ持つ併存症が多い点も重要です。
- 小児期に気づかれなかった特性が、社会生活で求められるタスクの複雑化や増加に伴い、成人になってから顕在化することもあります。
2. ADHDの原因論
ADHDの正確な原因は特定されていませんが、生まれつきの脳の性質や働き方の偏りによって生じると考えられており、複数の要因が相互に関連しています。
- 生物学的要因:
- 神経伝達物質の機能不全: 脳内のドパミンやノルアドレナリンといった神経伝達物質の分泌量調節が不十分であったり、機能不全を起こしたりすることで特性が現れると考えられています。
- 脳の機能障害: 特に前頭前皮質(実行機能、注意制御を司る部位)の機能障害が指摘されています。
- 遺伝的要因: ADHDは遺伝子と環境因子の相互作用で起こると考えられていますが、「必ず遺伝する」という明確な法則性は確認されていません。
3. 診断基準とプロセス(DSM-5-TRに基づく)
ADHDの診断は、世界保健機関(WHO)のICD-11や、アメリカ精神医学会(APA)のDSM-5-TRに記載された臨床基準に基づいて行われます。
DSM-5-TRの主な診断基準(要約)
以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 不注意と多動性・衝動性の特性が、同程度の年齢の発達水準に比べてより頻繁に強く認められること。
- 症状のいくつかが12歳以前より認められること。
- 症状による障害が、2つ以上の状況(例:家庭と職場、学校など)において認められること。
- 発達に応じた機能(対人関係、学業的・職業的機能)が障害されていること。
- その症状が、統合失調症や他の精神病性障害では説明されず、他の精神疾患ではうまく説明されないこと。
診断プロセスで使用されるツール
ADHDの診断は、問診(生育歴、現在の生活状況)を基に、以下の評価ツールを併用して総合的に判断されます。
- 診断・評価尺度:
- ASRS (Adult ADHD Self-Report Scale):成人のADHDスクリーニングに用いられる自己記入式尺度。
- CAARS™ (Conners’ Adult ADHD Rating Scales)
- CAADID™ (Conners’ Adult ADHD Diagnostic Interview for DSM-IV)
- 認知機能検査:
- IQ測定(WISC、WAISなど):全体的な認知能力の把握と、実行機能(ワーキングメモリ、処理速度など)のプロファイルの分析。
- 画像検査・脳波測定: てんかんなどの他の脳疾患の併存や鑑別が必要な場合に併用されることがあります。
4. 対応と対処法
ADHDの困りごとを軽減し、社会適応を促進するためには、多角的な対処法が取られます。
- 環境調整(Environmental Accommodation): 苦手な部分をカバーするための環境やシステムの変更(例:整理整頓しやすい配置、デジタルツールによるリマインド)。
- 心理社会的治療:
- ソーシャルスキルトレーニング(SST): 対人関係や社会生活に必要な技能を学習する。
- 認知行動療法(CBT): 不適切な思考パターンや衝動的な行動パターンを修正する。
- 薬物治療: 脳内のドパミンやノルアドレナリンの機能を調節する薬(例:中枢神経刺激薬、非中枢神経刺激薬など)が用いられ、不注意や衝動性の特性の軽減に効果を示します。
これらの対処法は、個人の特性や困りごとの内容に応じて組み合わせて実施されます。