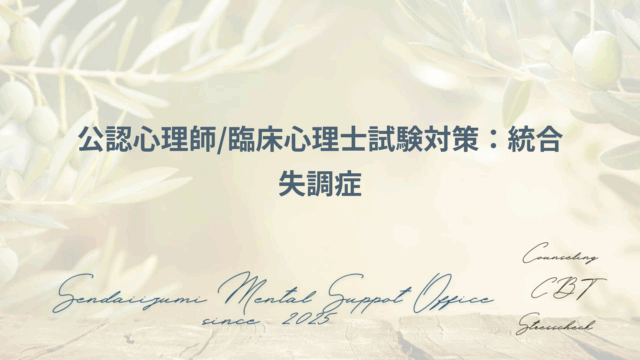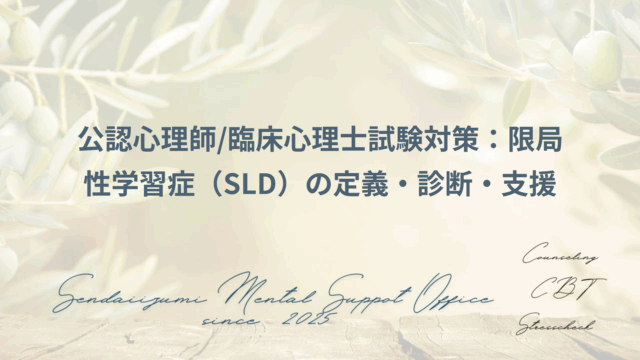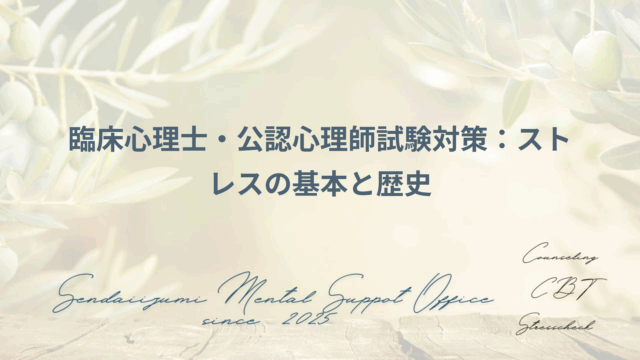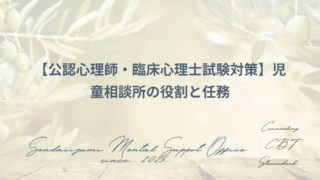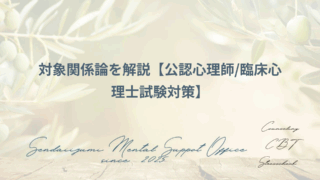公認心理師/臨床心理士試験対策:自閉スペクトラム症(ASD)徹底解説
もくじ
1. 自閉スペクトラム症(ASD)とは?:基本概念と特性
自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder: ASD)は、生涯にわたる発達障害であり、その名の通り、症状の現れ方が個人によって大きく異なる連続帯(スペクトラム)として捉えられます。
ASDの核となる困難は、以下の2つの主要領域にわたる行動特徴です。
- 社会的コミュニケーションおよび対人関係における持続的な障害
- 言葉や非言語的手段(表情、ジェスチャー)でのコミュニケーションの困難。
- 相手の気持ちを理解することの困難、他者との人間関係を継続することの困難。
- 限定的で反復的な行動、興味、または活動のパターン
- 自分のやり方への強いこだわり、特定の行動や身体の動きの反復(常同行動)。
- 特定の対象に限定した異常な関心(過剰な執着)。
- 感覚過敏または感覚鈍麻といった感覚処理の異常。
これらの特徴が日常生活に明らかに支障をきたすレベルである場合にASDと診断されます。
知能レベルと病因・割合
- 知能レベルの多様性: ASDの診断があっても、知能レベルは重度の遅れから優秀知能まで非常に幅広いです。必要な支援の程度も多様なため、一律に捉えられません。
- 病因: 遺伝的要因を主とし、出生前のさまざまな環境要因が複雑に関わり合って発症すると考えられています。病因はASD内でも様々です。
- 割合と男女比: 全人口の1~2%とされ、伝統的に男児に多い(約4:1)と考えられてきましたが、近年は女児のケースも診断されることが増え、男女比の差は縮小傾向にあります。これは診断概念の変化や社会全体の気づきの高まりによると見解が一般的です。
2. 診断基準(DSM-5-TR)の詳細
ASDの診断は、いまだバイオマーカーは未確立であるため、行動特徴から判断されます。国際的に使用されるDSM-5-TR(精神障害の診断と統計マニュアル第5版 改訂版)の診断基準は以下の通りです。
A. 社会的コミュニケーションと社会関係の障害(すべて満たすこと)
様々な場面における社会的コミュニケーションと社会関係の障害で、以下の特徴のすべてが現在ある、あるいは過去にあったことがある必要があります。
- 社会的・情緒的相互作用の障害
- 異常な対人的接近、通常の会話のやり取りができない。
- 関心や情緒、愛情を他人と共有できない。
- 社会的相互の関係を開始したり、応答したりすることができない。
- 対人的やりとりにおいて使用する非言語的コミュニケーション行動の障害
- 貧弱な言語的あるいは非言語的コミュニケーション。
- 異常なアイコンタクトやボディランゲージ。
- 身振り手振りの理解や使用の困難、表情による感情表現や非言語コミュニケーションの完全な欠如。
- 対人関係の開始、維持と理解の障害
- 様々な社会的場面にふさわしく行動を調整することの困難。
- 想像的な遊びの共有や友人を作ることの困難。
- 友人への関心の欠如など。
B. 制限されたあるいは反復する行動様式、関心、活動(2つ以上満たすこと)
以下の例のうち2つ以上が現在ある、あるいは過去にあったことがある必要があります。
- 型にはまった、あるいは反復的な動きや、物の扱い方、あるいは話し方
- 単純な常同運動、おもちゃを並べること、物をぺらぺらと振ること、反響言語、決まり言葉など。
- 同じであることへの固執、ルーチンへの頑ななこだわり、儀式的な言語的あるいは非言語的行動
- 小さな変化による強い苦痛、行動を移行することの困難。
- 固い思考パターン、儀式的な挨拶、毎日同じ道筋や同じ食べ物にこだわることなど。
- 非常に制限され、程度や対象が異常な関心
- 奇妙な対象物への強い愛着や執着、過剰なもの。
- 感覚刺激への過敏あるいは鈍感、環境への感覚面での異常な関心
- 痛みや温度への明らかな無関心、特別な音や手触りの嫌悪。
- 物の匂いを過剰にかいだり、触ったりすること、光や動き回ることに視覚的に幻惑されるなど。
C. 発症時期と機能障害
- C. 症状は初期の発達過程で見られなければならない。(ただし、社会からの期待が本人能力を超えるまで発現しないことや、対応方略によって隠蔽されることがある。)
- D. これらの症状によって、社会生活、職場、あるいは現在の生活における重要な領域において臨床的に有意な機能障害を起こしている。
- E. これらの障害は知的障害や全体的な発達の遅れでは説明できない。(ただし、知的障害とASDは往々にして併存するが、社会的コミュニケーション能力は発達レベルから期待されるより低くなければならない。)
重症度の指定
診断時には、重症度を「社会的コミュニケーションの困難の度合」および「制限された反復する行動パターン」によって明確に指定します。
診断の手順
ASDの診断は2歳前後から可能ですが、言語や知能の発達が良好な場合、就学後や青年期以降になることもあります。
診断は、単一の検査結果ではなく、複数場面(家庭、学校/園、診察場面)での行動観察、質問紙、親面接、全般的な発達検査、適応行動の評価など、多角的な評価を参考に専門家チーム(児童精神科医、小児科医、言語聴覚士、心理士など)によって行われることが推奨されます。
3. 年齢別の症状と支援のかかわり方
ASDの症状は生涯を通して続きますが、発達段階によって現れ方や必要な支援が異なります。
■ 乳幼児期(1~2歳くらい)
| 症状の特徴 | かかわり方のポイント |
| 社会的コミュニケーションの欠如(定型発達児が示す社会的行動:指さし、視線を用いた興味の共有、名前への応答、微笑み返しなどがほとんどない)。 | 視覚化(見てわかりやすい環境づくり)を徹底する(写真、絵、文字、具体物を使用)。 |
| 感覚過敏による偏食、入浴・睡眠への困難。 | 構造化により見通しを持たせ、行動の切り替えに伴う激しいかんしゃくを少なくする。 |
| 一人遊びの傾向、おもちゃの扱い方への強いこだわり。 | 環境の流れを構造化することで、想定外の出来事へのストレスを減らす。 |
■ 就学前幼児期(3~5歳くらい)
| 症状の特徴 | かかわり方のポイント |
| 仲間関係の問題(集団遊びを好まない、自分のやり方を押し付けて遊びが続かない)。 | コミュニケーションや対人行動の発達を促す療育プログラムを選定し、支援目標に合わせる。 |
| 会話のやり取りが続かない(関心のある話題については一方的に話し続ける)。 | 応用行動分析(ABA)などの行動的アプローチが有効であると示唆されている。 |
| 強いこだわりが邪魔された際のかんしゃく(長時間化、自傷行為や攻撃的行動への発展)。 | ペアレントトレーニングを通して、家庭でも一貫したかかわりを続けられるよう親への助言を行う。 |
■ 学童期(6~13歳くらい)
| 症状の特徴 | かかわり方のポイント |
| 集団ルールの非自明性による学校生活での戸惑い。周囲との違和感の自覚、いじめのターゲット、不登校。 | ASD特性や程度を学校に伝え、教育上の配慮を受けることが重要。 |
| ASD特性(こだわり)が「~ねばならない」という偏った考えに結びつき、生活に余裕がなくなる。 | インクルーシブ教育か特別支援教育か、その子の学業的能力や特性を総合的に判断し、無理のない要求水準を設定する。 |
| 高率な併存症(ADHD、読み書き障害、不安、うつなど)の合併。 | 他に治療を要する問題がないか見逃さないように、包括的な評価を継続する。 |
■ 青年期・成人期(13歳くらい以降)
| 症状の特徴 | かかわり方のポイント |
| 社会的スキルの向上があっても、暗黙のルールや社会的複雑さが増し、孤立感や社交不安に苦しむ。 | 児童期からの特性理解を通じた自己理解を深められるようなかかわりが大事。 |
| 仕事での複雑な社会的判断の負担、作業の進め方へのこだわりによる共同作業の困難。 | 進路選択・就職先の決定時に障害特性を念頭に置き、就労移行支援や大学の支援体制を利用する。 |
| 精神的な不調(パニック、うつ)をきたし、初めて背景にASDが気づかれるケース(学業成績が良い場合に多い)。 | 社会的常識の欠如が原因となる対人トラブルに対し、対人技能、リラクゼーション、自己モニタリングを含む小集団でのワークが有用な場合がある。 |
| 親しい人間関係が作れない、コミュニケーションが一方的など、不器用さによる対人トラブルやいじめ経験。 | 不安症やうつ病などには、ASD特性を踏まえた精神科的治療や心理治療を提供する。構造化や視覚化といったASD特性に応じた対応の基本は、成人になっても負担減につながる。 |