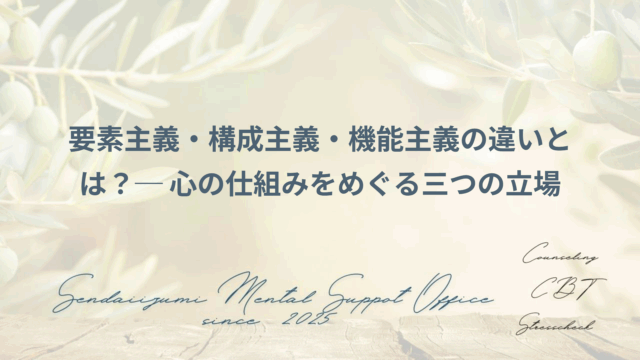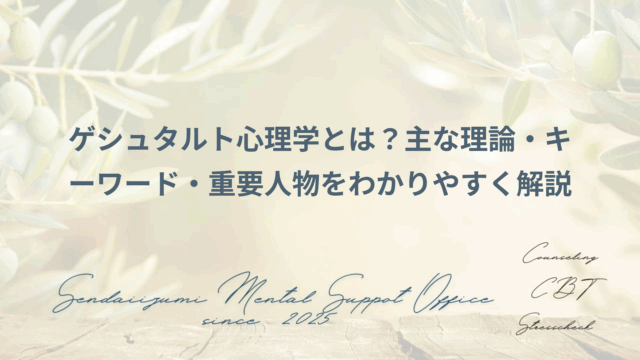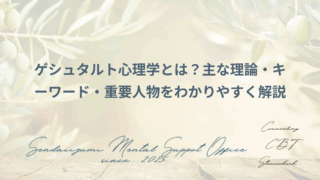行動主義とは?主要理論・代表的な人物・重要キーワードを徹底解説
もくじ
行動主義とは
行動主義(Behaviorism)は、アメリカの心理学者ジョン・B・ワトソン(J.B. Watson)によって提唱された心理学の学派です。
ワトソンは「心理学が科学であるためには、客観的に観察可能な現象だけを対象にすべきである」と考え、観察可能な行動に着目しました。これにより、それまで内省や無意識に依拠していた心理学を、科学的な立場から再定義しようとしました。
行動主義の基本的な枠組みは、S-R理論(刺激-反応)です。これは、「特定の刺激(S)が特定の反応(R)を引き起こす」という直線的な因果関係に基づいています。
また、ワトソンは有名な「アルバート坊やの実験」(小児への恐怖条件付け実験)を通じて、人間の行動・情動・性格は生得的なものではなく、環境によって形成されるという環境主義を提唱しました。
この実験では、生後8か月の男児アルバートにネズミを見せ、それに触れたタイミングで大きな音を鳴らすという条件づけを繰り返しました。その結果、アルバートはネズミを見るだけで恐怖反応を示すようになりました。
行動主義は、20世紀前半の心理学の三大潮流(精神分析、ゲシュタルト心理学、行動主義)の一つとされ、特にアメリカにおいて強い影響力を持ちました。その後、ワトソンによる初期のS-R理論では複雑な学習や動機づけを十分に説明できないとされ、行動主義はさらに新行動主義(Neo-behaviorism)へと発展していきました。
行動主義・新行動主義の重要人物
- J.B.ワトソン(John B. Watson)
古典的行動主義の創始者。観察可能な行動に基づく心理学を提唱し、「12人の乳児がいれば、どんな職業にも育てられる」とした環境決定論の立場が有名。 - C.L.ハル(Clark L. Hull)
S-R理論を発展させ、刺激と反応の間に媒介変数(O)=有機体を導入したS-O-R理論を提唱。動因低減説や習慣強度の理論でも知られる。 - E.C.トールマン(Edward C. Tolman)
潜在学習やサイン=ゲシュタルト理論を提唱し、後の認知心理学にも影響を与えた。学習の背景にある心的構造としての認知地図の概念を提案。 - B.F.スキナー(Burrhus F. Skinner)
オペラント条件づけの提唱者。レスポンデント反応とオペラント反応を区別し、**徹底的行動主義(Radical Behaviorism)**の立場から行動の制御原理を追究した。
行動主義の重要キーワード
・古典的条件づけ(Classical Conditioning)
レスポンデント条件づけとも呼ばれます。無条件刺激(例:食べ物)と条件刺激(例:ベルの音)を対提示することで、条件刺激だけで条件反応(唾液分泌など)を引き出すようになる学習形態です。
この理論はパブロフの犬の実験で有名であり、ワトソンの「アルバート坊やの実験」もこれに基づいています。
・オペラント条件づけ(Operant Conditioning)
スキナーによって提唱されました。自発的なオペラント行動に対して、報酬(強化)や罰を与えることで、行動の頻度を変化させる手続きです。
例:褒められた子どもが同じ行動を繰り返す → 正の強化。
・動因低減説(Drive Reduction Theory)
ハルによって提唱された理論で、行動の動機づけは内部の欲求(動因)によって生じ、これを低減することで行動が強化されるとします。
例:空腹という動因 → 食事 → 動因の低減 → 「空腹のときは食事をとる」という行動が強化。
繰り返し報酬が与えられることで、その行動の強さが高まることを習慣強度と呼びます。
・潜在学習(Latent Learning)
トールマンが提唱した概念で、「行動として表れないが、実は内的に学習されている状態」を指します。
彼はネズミに迷路学習の実験を行いました。
- A群:ゴールするとすぐに報酬(餌)が与えられる
- B群:ゴールしても報酬なし
- C群:最初の5日間は報酬なし → 6日目以降は報酬あり
その結果、C群のネズミは報酬が与えられるようになると、急激にゴールまでの時間が短縮されました。
つまり、報酬がなくても迷路の構造(認知地図)を学習していたことが示されました。
このように、潜在学習は行動に表れなくても、内的に知識や構造が形成されている学習を意味します。
また、トールマンはこの内的構造を「認知地図(Cognitive Map)」と呼び、空間的な情報を図式的に捉える心的表象として後の認知心理学にも影響を与えました。