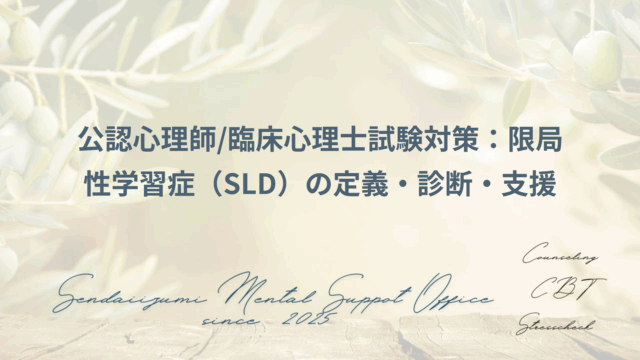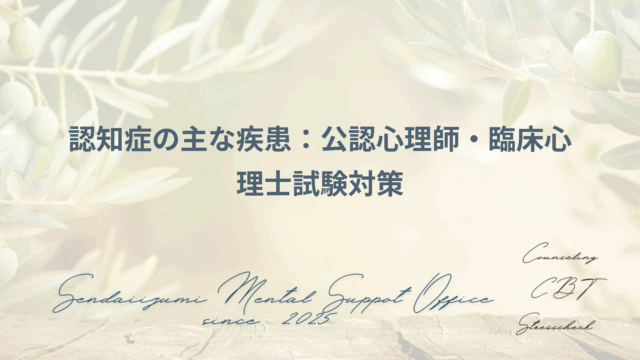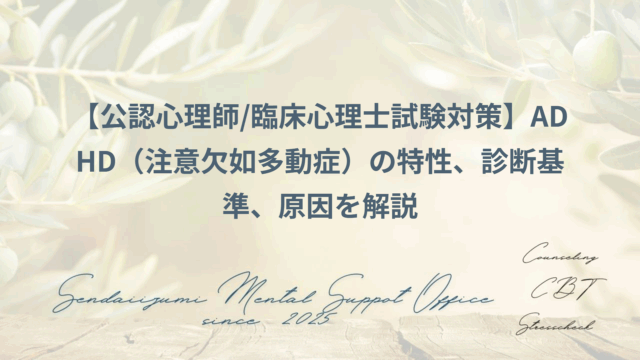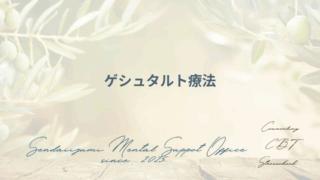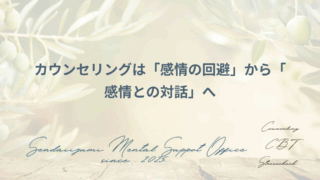双極症の基礎知識:公認心理師・臨床心理士試験対策
双極症は、気分障害の一つであり、公認心理師や臨床心理士の試験でも頻出のテーマです。このブログでは、双極症の基本概念から、DSM-5-TRの診断基準、そして治療における重要なポイントを解説します。
1. 双極症の基本概念とDSM-5-TRの診断基準
双極症は、気分が「躁(または軽躁)」と「抑うつ」の間で大きく変動する精神疾患です。これは、健常者が経験するような気分の波とは異なり、著しい機能障害(学業や仕事、対人関係などにおける支障)を伴うことが特徴です。
双極症の種類
DSM-5-TRでは、双極症を主に以下の2つのタイプに分類しています。
- 双極症I型: 人生で少なくとも1回、躁病エピソードを経験したことがある場合に診断されます。通常は、うつ病エピソードも伴いますが、診断には必須ではありません。躁病エピソードは、日常生活に著しい支障をきたすほどの気分の高揚や活動性の亢進が見られます。
- 双極症II型: 軽躁病エピソードと抑うつエピソードの両方を経験した場合に診断されます。双極症I型のような重度の躁病エピソードは経験しません。このタイプは、うつ病と誤診されやすく、注意が必要です。
2. 躁状態・抑うつ状態の症状と鑑別の重要性
双極症の診断では、躁状態(または軽躁状態)と抑うつ状態のそれぞれの症状を正確に把握することが重要です。
- 躁状態(軽躁状態も共通)の主な症状
- 誇大性: 根拠のない自信に満ち、気分が高揚します。
- 活動性・エネルギーの亢進: 睡眠時間が極端に減っても疲れを感じず、常に動き回ります。
- 多弁・観念奔逸: 次々とアイデアが浮かび、話が途切れません。
- 注意散漫: 気が散りやすく、一つのことに集中できません。
- 無謀な行動: 買い物や投資での浪費、危険な運転など、後先を考えない行動をとります。
- 抑うつ状態の主な症状
- 通常のうつ病エピソードと同様の症状が見られます。抑うつ気分、興味や喜びの喪失、睡眠障害、食欲の低下・増加などが挙げられます。
特に双極症II型は、うつ病エピソードの期間が長く、軽躁病エピソードが見過ごされがちであるため、うつ病と誤診されるケースが多々あります。躁病/軽躁病エピソードの見落としは、適切な治療(特に薬物療法)を妨げるため、正確な鑑別診断が極めて重要です。
3. 病因と治療:薬物療法の役割
双極症は、単一の原因で発症するものではありません。遺伝的要因や環境要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
- 遺伝的素因: 遺伝率は約50%とされ、一卵性双生児間での高い一致率が報告されています。
- 神経伝達物質: 神経伝達の調節異常が関与していると考えられています。
双極症の治療の中核は薬物療法であり、症状の安定と再発予防に不可欠です。
- 気分安定薬: 炭酸リチウムやバルプロ酸ナトリウムなどが代表的な薬剤で、気分の波を抑える最も重要な役割を担います。
- 非定型抗精神病薬: 躁状態やうつ状態の治療にも用いられます。
試験対策として特に押さえておくべきは、薬物療法の重要性だけでなく、アドヒアランス(服薬遵守)の課題です。躁状態の時には病識が低下しやすく、「治った」と感じて自己判断で服薬を中断するリスクが高まります。しかし、自己中断は再発のリスクを大幅に高めるため、心理士としてはクライエントに対して、服薬の継続がいかに重要かを丁寧に説明し、支援していく姿勢が求められます。