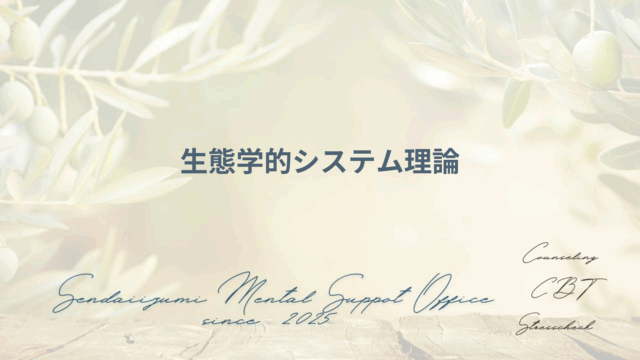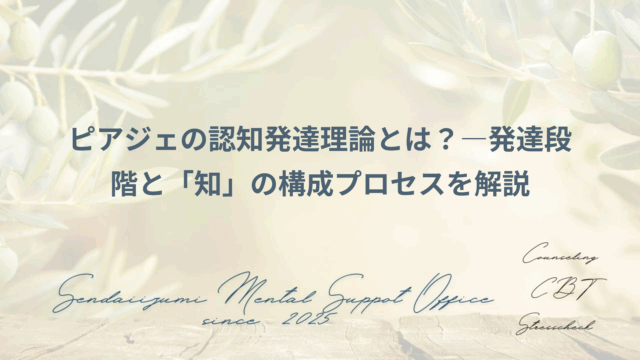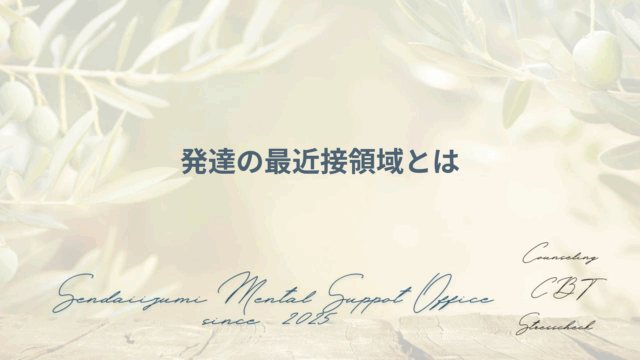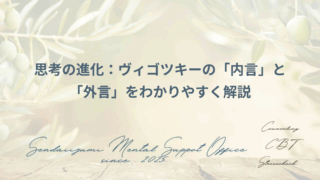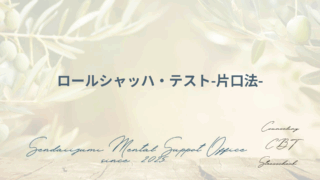言語の獲得:チョムスキーが提唱した「生成文法」と「普遍文法」をわかりやすく解説
私たちは幼い頃、特別な努力をすることなく自然と言葉を習得します。この驚くべき能力の背景には何があるのでしょうか? 「言語の獲得」というテーマを語る上で避けて通れないのが、現代言語学に革命をもたらしたノーム・チョムスキーです。
今日は、チョムスキーが提唱した「生成文法(せいせいぶんぽう)」と「普遍文法(ふへんぶんぽう)」という二つの重要な概念を通じて、私たちがどのように言葉を身につけるのかを、わかりやすく解説していきます。
もくじ
ノーム・チョムスキーとは?
ノーム・チョムスキー(Noam Chomsky)は、アメリカ合衆国の言語学者、哲学者、政治活動家です。彼の言語学における最大の功績は、それまでの行動主義的な言語観(言語は単なる模倣や習慣によって獲得されるという考え方)を批判し、人間が言語を操る生得的な能力を持っていることを強く主張した点にあります。
1. 生成文法(Generative Grammar)とは?
チョムスキーが提唱した「生成文法」とは、私たちが無限の数の文を生成し、理解できるという事実を説明しようとする言語理論です。
私たちが話す言語の文は、一つ一つ記憶しているわけではありません。文法規則を組み合わせることで、聞いたことのない新しい文を理解したり、自分で作り出したりできますよね。生成文法は、これらの文を作り出す(生成する)ための、有限で明確な規則のシステムを追求します。
【ポイント】
- 文法の規則性: 個々の文ではなく、文を生み出す「規則」に注目します。
- 無限性: 有限な規則の組み合わせから、無限の数の文を生み出すことが可能であると考えます。
- 深層構造と表層構造: 文には、表面的な音や単語の並び(表層構造)だけでなく、その文が持つ本来の意味や関係性を示す抽象的な構造(深層構造)があると考え、両者の関係を説明しようとしました。
2. 普遍文法(Universal Grammar: UG)とは?
生成文法の考えをさらに深めたのが、「普遍文法(Universal Grammar: UG)」という概念です。これは、すべての人間が生まれつき持っている、言語の根源的な設計図のようなものだと理解すると分かりやすいでしょう。
チョムスキーは、「刺激の貧困(Poverty of the Stimulus)」という有名な議論を展開しました。これは、子どもが周りから耳にする言語の刺激(インプット)は非常に限られているにもかかわらず、その文法を完璧に習得してしまうのはなぜか?という問いです。例えば、私たちは親が話す言葉をそのままオウム返しするだけでなく、その言葉の規則を応用して、聞いたことのない新しい文を正しく作ることができます。この能力は、単なる模倣や経験だけでは説明できない、とチョムスキーは主張しました。
【ポイント】
- 生得性: 普遍文法は、後天的に学ぶものではなく、人間の脳に「生得的に備わっている」と考えられています。
- 共通の設計図: 世界中の様々な言語は表面上は異なって見えても、この普遍文法という共通の基盤を持っているため、人間なら誰もが言語を習得できると考えます。
- 「言語獲得装置(Language Acquisition Device: LAD)」: チョムスキーは、子どもが普遍文法を元に言語を習得するメカニズムを、脳内に備わった「言語獲得装置」と表現しました。
言語の獲得とチョムスキー理論の関連
チョムスキーのこれらの理論は、「言語の獲得」プロセスを大きく見直すきっかけとなりました。
【チョムスキー理論から見る言語獲得】
- 生まれつきの言語能力: 人間は、経験だけで言語を習得するのではなく、普遍文法という生まれつきの言語能力を持っている。
- インプットとチューニング: 子どもは、この普遍文法という「設計図」を基に、周りから与えられる具体的な言語のインプット(外言)をフィルターとして使い、自分自身の言語の文法規則(生成文法)を構築していく。
- 急速な習得: 限られた環境からの言語刺激でも、驚くほど短期間で複雑な文法規則を習得できるのは、この生得的な普遍文法があるからこそ、と説明されます。
まとめ
ノーム・チョムスキーが提唱した「生成文法」と「普遍文法」は、言語の獲得が単なる学習や模倣ではないことを示し、人間の言語能力が生得的なものであるという画期的な視点を提供しました。
- 生成文法:文を生み出すための普遍的な規則体系。
- 普遍文法:人間が生まれつき持っている、言語の根源的な設計図。
これらの概念は、私たちが当たり前のように使っている「言葉」の不思議と、人間の認知能力の深遠さを教えてくれます。心理学や言語学を学ぶ上で、避けて通れない重要なテーマと言えるでしょう。