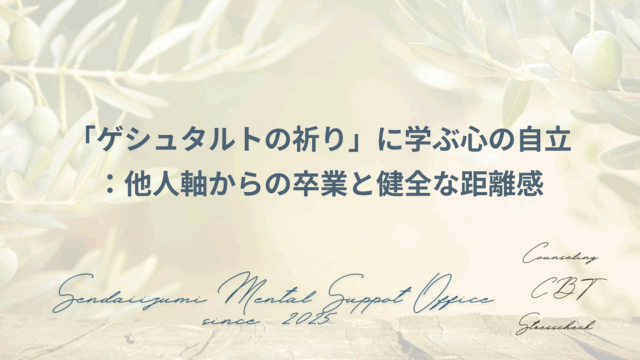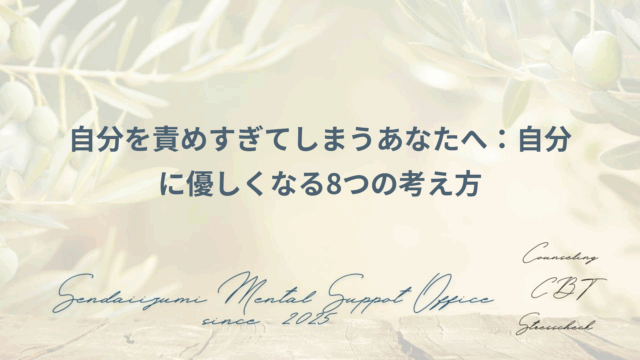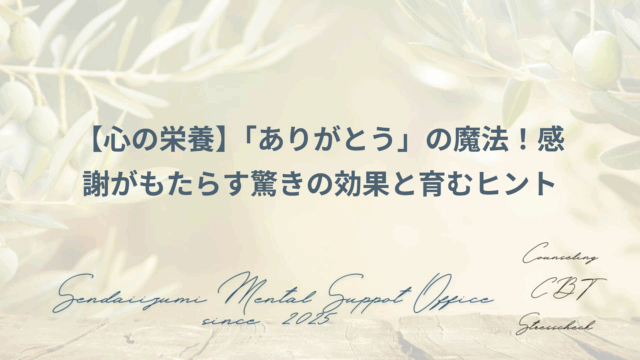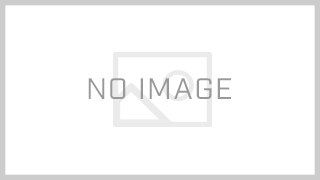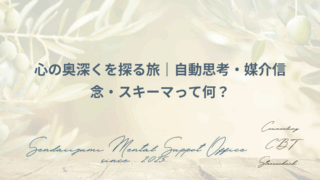認知の歪みチェック結果の説明と対処方法
当オフィスオリジナルの「認知の歪みチェック」の結果説明と対処方法についてまとめいてます。実際にチェックを実施した方もそうでない方もご参考になれば幸いです。
結果を見る前に「認知の歪みチェック」を実施したい方はこちらから↓

【無料】「認知の歪みチェック」ネガティブな思考のクセにお悩みの方へ。その思考、もしかして「認知の歪み」かも? 仙台泉メンタルサポートオフィスの無料チェックで、あなたの考え方の癖を知り、生きづらさを解消するヒントを見つけましょう。...
もくじ
1. 全か無かの思考(白黒思考)
- 説明:物事を極端に「完全に良い」「完全にダメ」と分けてしまう思考。
具体例:
- ダイエット中に一口お菓子を食べて「もう今日は全部無駄」と暴食してしまう。
- テストで90点を取っても「100点じゃないから意味がない」と感じる。
- 恋人と少し口論しただけで「この関係はもう終わりだ」と思ってしまう。
対処法:
- “完全”でないものにも価値があると認識する
- 中間の選択肢を探す:「90点もすごい成果。改善点もあるけど、全体としてよくやった」
- グレーゾーンを受け入れる練習をする
2. 過度の一般化
- 説明:一度の出来事から、将来や他の場面にも当てはめてしまう思考。
具体例:
- 面接に落ちたことで「自分はどこの会社にも受からない」と思う。
- 友達に断られただけで「私は誰からも好かれない」と感じる。
- 一回のミスで「私はいつも失敗ばかり」と結論づける。
対処法:
- 証拠を探す:「それが“いつも”そうだったと証明できる根拠は?」
- 例外や成功体験をリストアップする
- 視野を広げてみていく練習をする(例:「1回の出来事であって毎回ではない」)
3. 心のフィルター
- 説明:ポジティブな事実を無視し、ネガティブな側面だけに注目する思考。
具体例:
- 10人中9人に褒められたのに、1人に否定されたことばかり考える。
- 職場でうまくいったことより、注意されたことだけが心に残る。
- 楽しい旅行の中のトラブルだけが思い出されて嫌な記憶になる。
対処法:
- ポジティブな証拠を意識的に探す習慣を持つ
- 「良かった点は何か?」と自問する
- 1日の終わりに“3つのよかったこと”を書き出す
4. マイナス化思考
- 説明:自分の良い面や成果を過小評価したり無視する思考。
具体例:
- 賞を取ったのに「みんなが辞退したから取れただけ」と考える。
- 友人に感謝されても「誰にでもできることだったし」と受け入れない。
- 課題を早く終えたのに「簡単すぎたんだろう」と努力を認めない。
対処法:
- 過去の成功経験を書き出して可視化する
- 「他の人が同じ成果を出したら、どう思う?」と他者視点で考える
- 自己肯定感を高めるセルフトークを練習する
5. 結論の飛躍
- 説明:根拠なく否定的な結論を出してしまう。読心や未来予測が含まれる。
具体例:
- 同僚が挨拶を返さなかっただけで「嫌われている」と決めつける。
- 恋人の返信が遅いと「もう別れたいと思っているんだ」と思う。
- 上司が忙しそうなだけで「自分の仕事ぶりに怒っている」と考える。
対処法:
- 根拠の有無を検証する:「事実は?思い込みは?」
- 別の可能性を3つ挙げてみる
- 思考日記をつけて、飛躍を客観視する習慣を持つ
6. 過大評価と過小評価
- 説明:自分のミスを過大に捉えたり、他人の長所を過剰に評価する思考。
具体例:
- ちょっとした発言ミスを「とんでもない失言だ」と感じる。
- 他人の業績を「自分には絶対できない」と思ってしまう。
- 自分の努力を「大したことない」と小さく見積もる。
対処法:
- 実際の影響や確率を具体的に数値で考えてみる
- 「小さな成功体験」も記録する
- 自分と他人を比べすぎず、「完璧じゃなくても十分」と考える
7. 感情的理由づけ
- 説明:「不安に感じるから悪いことが起きるに違いない」と感情を事実と混同する思考。
具体例:
- 「緊張してるから、絶対うまく話せない」と感じる。
- 「イライラするから、この仕事は意味がないんだ」と結論づける。
- 「落ち込んでるから、きっと自分は価値がない」と思い込む。
対処法:
- 感情と事実を区別する練習をする:「不安≠現実」
- 「今の気持ちは、現実をどうゆがめている?」と問いかける
- 感情の波グラフで記録し、変動に気づく
8. 「~すべき」思考
- 説明:過剰な義務感を自分や他人に課し、それが守れないと自己否定や怒りに繋がる。
具体例:
- 「親なら子どもにイライラしてはならない」と自分を責める。
- 「部下は常に敬語を使うべき」と考えて苛立つ。
- 「毎日完璧に掃除しなければならない」と疲弊する。
対処法:
- 「〜すべき」を「〜できたらいいな」に言い換える
- 義務的な思考を検出して書き出す
- 他人にも同じ基準を当てはめて不公平さに気づく
9. レッテル貼り
- 説明:1つの行動や結果をもとに、自分や他人に極端なラベルを貼ってしまう思考。
具体例:
- 忘れ物をしただけで「私は本当にだらしない人間だ」と思う。
- 友人が遅刻したことから「この人はいつもだらしない」と決めつける。
- 会話がうまくできなかっただけで「私は社会不適合者だ」と考える。
対処法:
- 人格全体ではなく“行動”にフォーカスする(例:「私はミスした」)
- “一面的”でなく“多面的”に捉えていく
- 自分の中のさまざまな側面を書き出して客観視
10. 自己関連付け
- 説明:自分に関係のないことまで、自分のせいだと考える思考。
具体例:
- 友人の機嫌が悪いのを見て「自分のせいに違いない」と思う。
- チームでプロジェクトが失敗すると、自分だけが悪かったと感じる。
- 職場の雰囲気が悪いのは自分の発言のせいだと考える。
対処法:
- 「他の可能性は?」と第三者視点で考える
- 他人の気分や行動に責任を感じない思考を育てる(例:「他人の考えや感情は、私にはコントロールできない」)
- 「自分の責任と他人の責任」を書き分ける練習をする
認知の歪みについてはコチラでもまとめています。
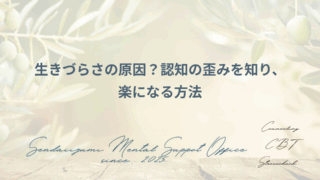
生きづらさの原因?認知の歪みを知り、楽になる方法ネガティブな思考パターンとして10種類の「認知の歪み」ついて解説。自身の思考パターンを知ることが、改善の第一歩です。...
結果の見方と今後のために
このチェックは、あくまで皆さんの思考の傾向を知るためのものです。点数が高かった項目が必ずしも問題であるとは限りませんが、もし日常生活で生きづらさを感じることがあれば、これらの思考パターンが影響している可能性も考えられます。
認知の歪みは、意識することで修正していくことができます。今回の結果を参考に、ご自身の思考パターンを振り返り、より柔軟な考え方を身につけるヒントにしていただければ幸いです。
もし、より詳しくご自身の思考について知りたい場合や、改善に取り組みたい場合は、当オフィスにご相談ください。