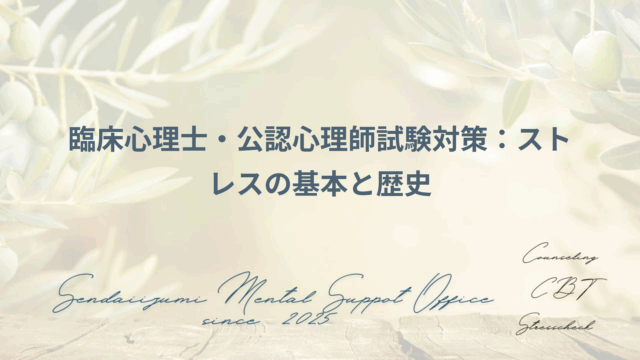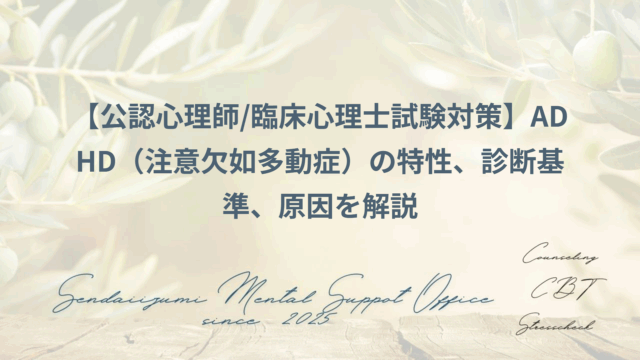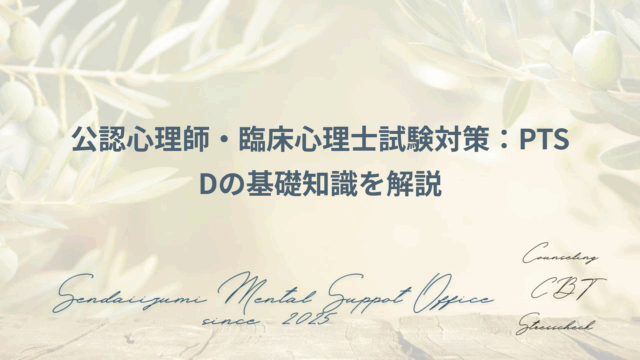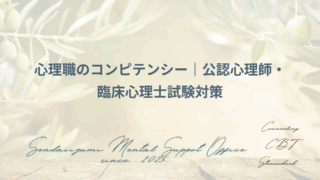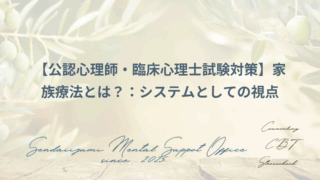認知症の主な疾患:公認心理師・臨床心理士試験対策
今回は、公認心理師/臨床心理士試験の重要テーマである「認知症」について、主要な疾患と関連知識を体系的に解説します。
もくじ
1. 認知症の主な4大疾患
認知症は単一の病気ではなく、さまざまな疾患によって引き起こされる症候群です。その中でも特に頻度が高いのが、アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症であり、これらは「4大認知症」と呼ばれています。
1-1. アルツハイマー病(AD)
認知症の原因で最も多く、全体の過半数を占めます。
- 症状: 進行性の物忘れ(記銘力障害)が主な初期症状です。同じ話を繰り返したり、物の置き場所を忘れたりすることから始まり、徐々に着替えや金銭管理などの日常生活動作が困難になります。
- 病理: 脳内にアミロイドβというタンパク質が異常に蓄積し、老人斑と呼ばれるシミを形成します。このアミロイドβが神経細胞に毒性を与え、神経細胞内のタンパク質を介して神経細胞が死滅することで発症します。この病理変化は、症状が現れる15〜20年前から水面下で始まっていることがわかっています。
- 経過: 正常→軽度認知障害(MCI)→認知症へと、おおむね年単位でゆっくりと進行します。
- 薬物療法:
- 対症療法: 神経伝達物質(アセチルコリン)の働きを活発にするコリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジルなど)や、グルタミン酸の過剰な興奮を抑えるNMDA受容体拮抗薬(メマンチン)が用いられます。これらは症状を一時的に緩和するもので、病気の進行を止める効果はありません。
- 根本治療: 2023年に日本で承認されたレカネマブは、アミロイドβを除去することで病気の進行を遅らせる効果が期待される初の薬です。ただし、アミロイドβの蓄積が確認され、かつ重症度が高くない患者に限定されます。
1-2. 血管性認知症(VaD)
アルツハイマー病に次いで多いタイプの認知症です。
- 病理: 脳卒中(脳梗塞、脳出血)や、慢性的な脳の血流不足が原因で、脳組織が障害されて発症します。特に微小な脳梗塞や微小出血が広範囲に及ぶ場合が多いです。
- 症状:
- まだら認知症: 認知機能の障害が、領域によって差があるのが特徴です。記憶力は保たれているのに、遂行機能や注意機能に障害がみられることがあります。
- 階段状の進行: 脳血管障害が起こるたびに症状が悪化し、一進一退を繰り返す「階段状」の進行が典型的です。
- 身体症状: 構音障害、嚥下障害、パーキンソン病に似た歩行障害などが伴うことがあります。
1-3. レビー小体型認知症(DLB)
認知症の原因の約10〜15%を占めます。
- 病理: 脳の神経細胞内にレビー小体という特殊なタンパク質の塊が蓄積することが原因です。同じレビー小体が原因となるパーキンソン病と病理学的に関連が深いとされています。
- 特徴的な症状:
- 変動する認知機能: 1日の中でも頭がはっきりしている時間と、ぼんやりしている時間が変動します。
- 幻視: 実際にはいない人物や小動物などが、本物のようにリアルに見えます。
- パーキンソン症状: 動作が遅くなる、手足が震える、歩行が困難になるなど。
- レム睡眠行動異常症: 眠っている間に夢と連動した行動(寝言、手足を動かすなど)が出現します。この症状は認知症発症の何年も前からみられることがあります。
- 薬物療法:
- 認知機能・幻視: コリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジルなど)が効果的です。
- パーキンソン症状: L-DOPAなどのパーキンソン病治療薬が用いられます。
- 注意点: 薬に対する感受性が高く、特に抗精神病薬で副作用が生じやすいため、薬物治療には注意が必要です。
1-4. 前頭側頭葉変性症(FTLD)
初老期(65歳未満)に発症することが多いのが特徴です。
- 病理: 大脳の前頭葉や側頭葉が局所的に萎縮します。タウ、TDP-43、FUSなどの異常タンパク質が関与すると考えられています。
- 症状:
- 行動障害: 人格の変化、社会的マナーの逸脱、脱抑制(我慢できない)、無関心などが目立ちます。
- 言語障害: 言葉がスムーズに出てこない、言葉の意味が理解できなくなるなどの症状が出ることがあります。
- 注意点: 物忘れが主症状のアルツハイマー病とは異なり、行動や言語の障害が目立つため、初期はうつ病や統合失調症と誤診されることもあります。
2. その他の認知症と注意すべき病態
2-1. その他の認知症
上記の4大認知症以外にも、超高齢者に多い神経原線維変化型老年認知症や嗜銀顆粒性認知症など、様々な病気があります。また、進行性核上性麻痺やクロイツフェルト・ヤコブ病なども認知症の原因となります。
2-2. 治療可能な認知症
認知症に似た症状(認知機能低下、うつ状態など)を引き起こすものの、適切な治療で回復する可能性がある病態も存在します。
- 慢性硬膜下血腫: 頭部の外傷後に脳と頭蓋骨の間に血液がたまる病気。
- 正常圧水頭症: 脳脊髄液が頭蓋内に過剰に蓄積する病気。
- 高齢期のうつ病: 認知機能の低下を伴う「仮性認知症」と呼ばれる状態。
- 甲状腺機能低下症: 甲状腺ホルモンの不足による代謝機能の低下。
- ビタミンB群欠乏症: アルコール依存症などでビタミンBが不足した場合。
これらの病気を鑑別するために、認知症の診断では画像検査や血液検査などが不可欠となります。
公認心理師/臨床心理士の役割
認知症の診断は医師が行いますが、心理職は認知機能検査(MMSE、長谷川式など)の実施や、本人・家族への心理的支援、生活環境の調整など、多岐にわたる役割を担います。
各疾患の特徴を正確に理解し、適切な支援につなげることが、専門家としての重要な責務です