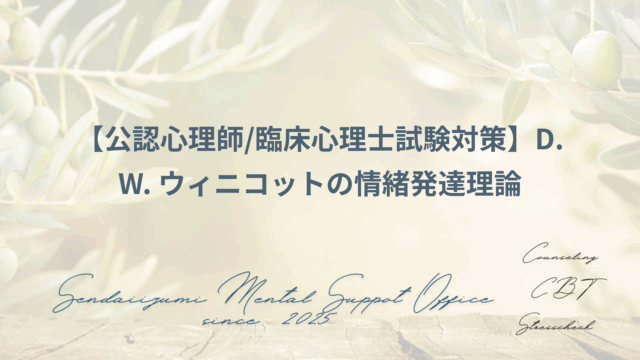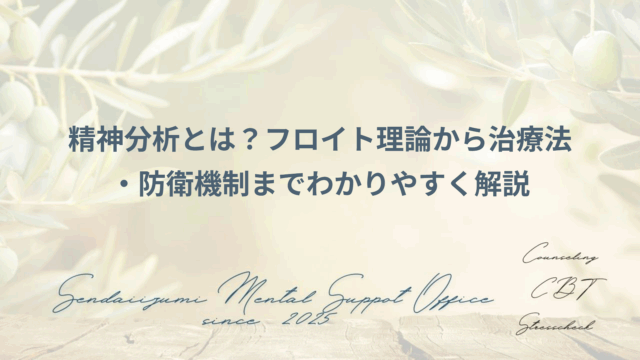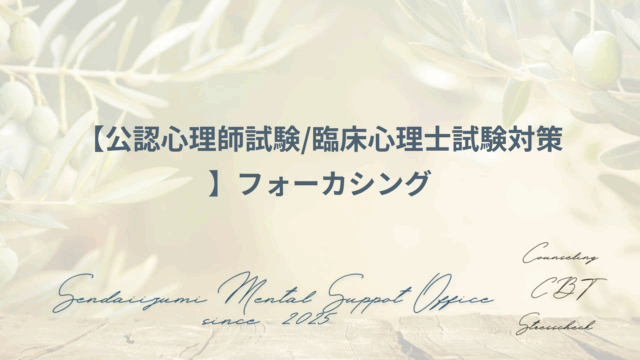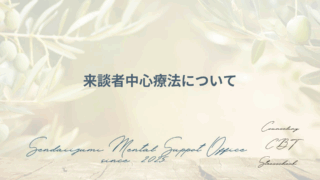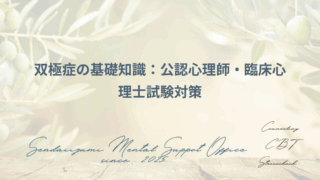ゲシュタルト療法
ゲシュタルト療法は、公認心理師・臨床心理士の試験で出題される可能性のある重要な心理療法の一つです。本ブログでは、ゲシュタルト療法の基本的な概念から、実際の技法までを解説します。
もくじ
1. ゲシュタルト療法の概要と歴史
ゲシュタルト療法は、1950年代初頭に精神科医のフリッツ・パールズとその妻であるローラ・パールズらによって考案された実践的な心理療法です。実存哲学や現象学を基盤とした人間性心理学のアプローチであり、クライエントの主体性を尊重します。
主要な概念
ゲシュタルト療法には、試験で押さえておくべき重要な概念がいくつかあります。
- 今、ここ(here and now): 過去の出来事や未来の不安にとらわれるのではなく、「今、ここ」で何を感じ、何を体験しているかに焦点を当てます。これにより、現実に対する気づきを促します。
- 気づき(awareness): クライエントが、自身の感情、身体感覚、思考、そして周囲との関係性について自覚し、受け入れることを重視します。気づきを通して、自己の全体性を回復することを目指します。
- コンタクト(接触): 自己と外界、あるいは自己の異なる側面との間の相互作用を指します。健全なコンタクトを通して、欲求を満たし、自己を成長させます。
ゲシュタルト療法では、心身一元論に基づき、心と身体は一体であると考えます。そのため、言葉だけでなく、身体の感覚や動きにも注目します。
2. ゲシュタルト療法の主要技法
ゲシュタルト療法では、クライエントの気づきを促すために、さまざまな体験的な技法が用いられます。
エンプティ・チェア(空の椅子)
誰も座っていない空の椅子に、対話したい相手(他者、自己の一部、問題など)が座っていると想定し、対話を行う技法です。2つの椅子を使い、立場を入れ替えて対話をすることで、相手の視点を理解し、未解決の感情に気づくことを目指します。
ファンタジー・トリップ
イメージの中で、過去の出来事や未知の自己、他者に出会い、対話する体験をする技法です。現実では不可能な状況(例:亡くなった家族との再会)を通して、感情を解放し、安心感や気づきを得ることがあります。
夢のワーク
夢に出てきた人物や物、さらには感情や雰囲気そのものになりきり、「夢を生きる」という形で夢を再現する技法です。夢の登場人物や象徴が、自己の異なる側面を表していると捉え、それらを演じることで、統合されていない自己に気づき、全体性を回復することを目的とします。
ボディ・ワーク
言葉に表せない身体感覚や、身体の一部に焦点を当て、それを言語化または行動化する技法です。例えば、「その手が話すとしたら、何と言いますか?」と問いかけたり、弱った胃腸になりきって感情を訴えさせたりすることで、身体が表現している無意識の欲求や感情に気づきを促します。
まとめ
ゲシュタルト療法は、「今、ここ」での体験と気づきを重視し、身体感覚を含む自己の全体性を回復することを目標とする心理療法です。試験対策としては、創始者であるカール・ロジャーズ(来談者中心療法の創始者)と混同しないこと、そして「エンプティ・チェア」「夢のワーク」といった代表的な技法の名称と目的を正確に理解しておくことが重要です。