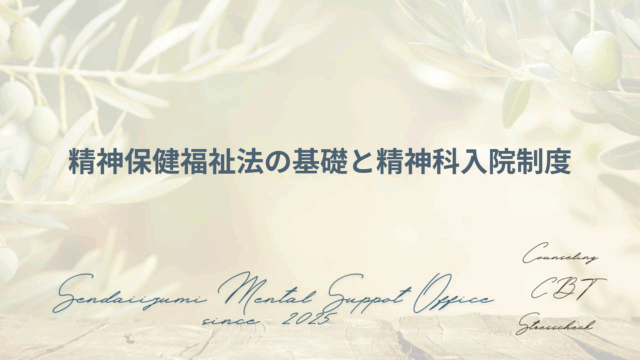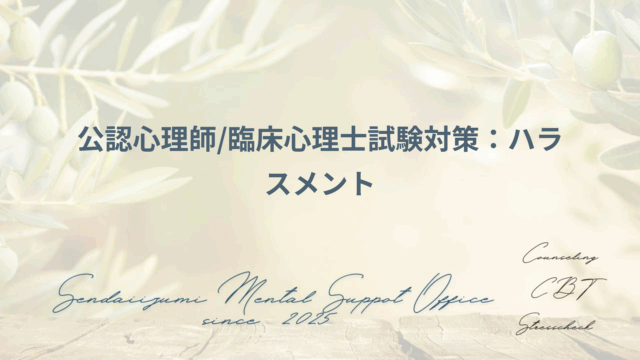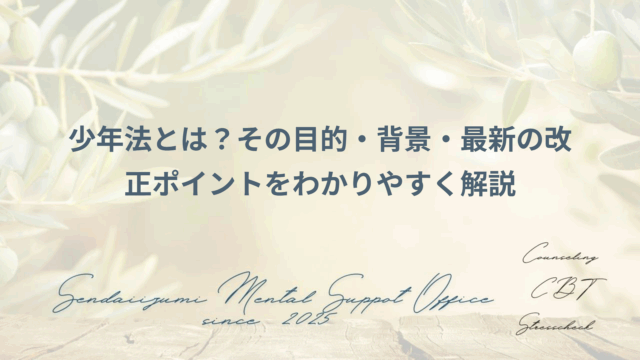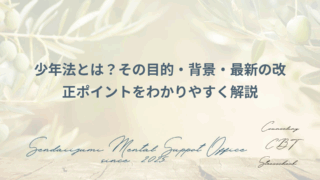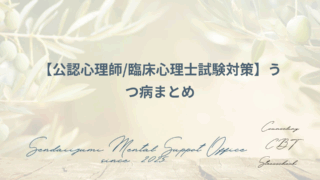虐待関連法規の重要ポイント総まとめ
今回は、試験に出題されやすい虐待関連法規について、これまでの情報をすべて集約し、ポイントを絞って解説していきます。実務でも非常に重要な知識なので、しっかりと押さえておきましょう。
1. 児童虐待防止法の基本
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)は、児童の権利を保護し、健全な心身の発達と人格形成を保障するために制定されました。試験でまず押さえるべきは、以下の点です。
- 「児童」の定義: この法律における児童とは、18歳に満たない者を指します。
- 通告義務: 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに児童相談所または市町村に通告する義務があります。これは国民の義務ですが、特に専門職には重く課せられます。
- 守秘義務との関係: 専門職には守秘義務がありますが、虐待の通告においては守秘義務よりも通告義務が優先されます。
2. 虐待の4つの類型
児童虐待防止法では、虐待を以下の4つの類型に分類しています。これらの定義は、試験でも頻出しますので、それぞれの違いを正確に理解しておくことが大切です。
- 身体的虐待: 身体に外傷が生じる、またはそのおそれのある暴行を加えること。
- 性的虐待: わいせつな行為や性交をすること、またはさせること。
- ネグレクト(養育の怠慢・放棄): 食事、衣類、住居の提供を怠る、就学・医療を受けさせない、そして同居人による虐待を放置することなども含まれます。
- 心理的虐待: 著しい心理的外傷を与える言動や、面前DV(家庭内暴力を子どもに見せること)などが該当します。
また、高齢者や障害者への虐待には、上記に加えて経済的虐待が含まれる場合があることも覚えておきましょう。
| 名称 | 主な行為 / 定義 | 対象 |
|---|---|---|
| 身体的虐待 | 身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行 | 児童、高齢者、障害者 |
| 性的虐待 | わいせつな行為、性交 | 児童、高齢者、障害者 |
| 心理的虐待 | 著しい心理的外傷を与える言動、無視、拒否的態度 | 児童、高齢者、障害者 |
| ネグレクト | 食事、衣類、住居等の保護の怠慢・拒否、就学・医療の不提供など | 児童、高齢者、障害者 |
| 経済的虐待 | 財産の不当な処分、必要な金銭を与えないなど | 高齢者、障害者 |
3. 虐待通告後の児童相談所の対応フロー
通告が行われた後、児童相談所がどのようなプロセスで対応を進めるのか、その流れを理解しておくことは、試験問題の状況設定を読み解く上で役立ちます。
- 通告の受理: 児童相談所は、通告された内容をまず受理します。
- 事実確認(安全確認): 児童相談所の児童福祉司や児童心理司が、原則として48時間以内に子どもの安全確認を行います。これは、児童の生命や心身の安全を最優先にするための緊急対応です。
- 一時保護: 事実確認の結果、児童の安全が脅かされていると判断された場合は、保護者の同意の有無にかかわらず、一時保護を行うことがあります。
- 指導と支援: 一時保護に至らない場合でも、虐待の可能性が認められれば、保護者への指導や助言、児童への心理的支援が開始されます。
- 多職種連携: 虐待の対応は児童相談所だけで完結するものではありません。警察、学校、医療機関など、多職種と連携して支援を進めていきます。
都道府県知事や児童相談所長には、保護者に出頭を求めたり、立入調査を行ったりする権限が与えられていることも重要なポイントです。
4. まとめ:試験対策の最終チェック
最後に、これまで解説した内容を、試験直前でも確認できるよう簡潔にまとめます。
- 法律: 児童虐待防止法、障害者虐待防止法など。
- 定義: 「児童」は18歳未満。虐待の4類型。
- 義務: 国民の通告義務。専門職の守秘義務より通告義務が優先。
- 対応フロー: 48時間以内の安全確認、一時保護、多職種連携。
- 権限: 都道府県知事の出頭命令、立入調査。
これらのキーワードをしっかりと頭に入れて、試験本番に臨んでください。