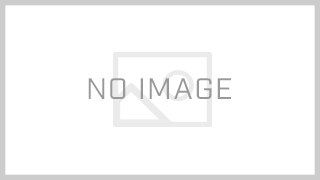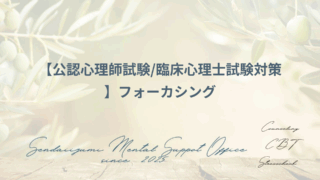【基礎心理学:発達心理学】演習問題:公認心理師試験/臨床心理士試験対策
問題1乳児期の発達に関する以下A~Dの記述のうち、正しいものの組み合わせを、下のa~eの中から最も適切なものを一つ選びなさい。
A.出生直後から見られる原始反射は、生後数ヶ月で消失し、随意運動へと移行していく。
B.運動の発達は、はいはい、お座り、寝返りの順に進み、その後つかまり立ち、つかまり歩きへと移行する。
C.ことばの発達において、喃語(「ウマウマ」「ダダダ」など)は、特定の意味を持つ「初語」として位置づけられる。
D.エリクソンの発達課題「基本的信頼感対不信」は、乳児期に養育者との安定した関わりを通じて「希望(hope)」という活力を獲得することが重要である。
a.A B
b.A C
c.B C
d.A D
e.C D
答えはコチラ
d.A D
【解説】
A.この記述は正しいです。乳児期に見られる原始反射は、神経系の発達に伴い、通常生後数ヶ月で消失し、赤ちゃん自身の意思による随意運動へと変化していきます。
B.この記述は誤りです。運動発達の正しい順序は、一般的に寝返り→お座り→はいはい→つかまり立ち→つかまり歩き→ひとり立ちです。問題文の順序は、初期の段階が逆になっています。
C.この記述は誤りです。喃語は、赤ちゃんが発する「ウマウマ」「ダダダ」といった、特定の意味を持たない発声です。特定の意味を持つ最初の言葉は初語と呼ばれ、喃語とは区別されます。
D.この記述は正しいです。エリクソンの心理社会的発達理論において、乳児期(0~1歳半頃)の主要な発達課題は「基本的信頼感 vs 不信感」です。この時期に養育者との安定した関わりを通して基本的信頼感を獲得することで、「希望」という肯定的な活力が育まれます。
以上の理由から、正しい記述はAとDであり、その組み合わせである選択肢cが最も適切です。
問題2ピアジェの認知発達理論における認知発達の4つの段階について、正しい組み合わせを下記のa~eの中から1つ選びなさい。
a. 感覚運動期 → 具体的操作期 → 前操作期 → 形式的操作期
b. 感覚運動期 → 前操作期 → 形式的操作期 → 具体的操作期
c. 感覚運動期 → 前操作期 → 具体的操作期 → 形式的操作期
d. 前操作期 → 感覚運動期 → 具体的操作期 → 形式的操作期
e. 前操作期 → 具体的操作期 → 感覚運動期 → 形式的操作期
答えはコチラ
c. 感覚運動期 → 前操作期 → 具体的操作期 → 形式的操作期
【解説】
ジャン・ピアジェが提唱した認知発達理論は、子どもの思考力が段階的に発達していくことを説明したものです。この理論では、子どもは単に知識を蓄積するだけでなく、能動的に外界と関わり、思考の「シェマ(枠組み)」を再構築していくと考えます。
発達の段階は、以下の4つに分けられます。
1.感覚運動期(0~2歳頃):感覚や運動を通して外界を理解する時期です。言葉や記号による思考はまだ未発達ですが、物の永続性(目に見えなくても存在することを理解する)を獲得します。
2.前操作期(2~7歳頃):言葉や記号を使い始め、想像力豊かに思考します。しかし、思考はまだ自己中心性(他者の視点に立つことが難しい)や中心化(一つの側面にしか注目できない)といった特徴を持ちます。
3.具体的操作期(7~11歳頃):論理的な思考が可能になります。中心化から脱し、物の量や体積が変化しないという「保存の概念」を理解できるようになります。ただし、思考の対象は、目に見える具体的な事柄に限られます。
4.形式的操作期(11歳頃~):抽象的な思考や、仮説を立てて論理的に考える「仮説演繹的思考」が可能になります。これは、科学的な思考様式に繋がる、より高度な認知能力です。
これらの段階は、普遍的で不変的な順序で進行するとされています。したがって、正しい組み合わせは c となります
問題3以下のA~Dの記述のうち、エリクソンの漸成的発達段階における内容として正しい組み合わせをa~eの中から最も適切な組み合わせを一つ選びなさい。
A. 老年期では、次の世代に残せるものがないと自分の存在意味を見出せず停滞に陥る。
B. 成人期は、次世代を支えていくことに関心を持つ。
C. 前成人期は、信頼できる人とのかかわりを深めることで有能感を獲得することが目的である。
D. 前成人期において、表面的な付き合いしかできないと孤立に陥る。
a. A B
b. A C
c. B C
d. B D
e. C D
答えはコチラ
d. BとD
【解説】
エリクソンが提唱した「漸成的発達段階」は、人が生涯にわたって8つの段階で心理社会的危機を経験し、それを乗り越えることで人格的な活力を獲得していくと考えた理論です。
A. 誤り。老年期の発達課題は「自己統合対絶望」であり、この段階で、次の世代に残せるものがないと自分の存在意味を見出せず「絶望」に陥るとされます。また、「停滞」は壮年期(成人期)の発達課題「生殖性・世代性対停滞」における危機であり、自己の世代だけを考えていると陥るとされています。
B. 正しい。壮年期(成人期)の発達課題は「生殖性・世代性対停滞」です。この時期は、過去に上の世代から学んだことを下の世代に伝え、次世代を支えていくことに関心を持つことが重要とされます。
C. 誤り。前成人期(若い成人期)の発達課題は「親密性対孤立」です。この課題を達成することで得られる活力は「愛」です。一方、「有能感」は、学童期の発達課題である「勤勉性対劣等感」を克服することで得られる活力です。
D. 正しい。前成人期(若い成人期)の発達課題は「親密性対孤立」です。この課題を達成できないと、他者と深く関わることができず、表面的な付き合いしかできなくなり、「孤立」に陥ってしまうとされています。