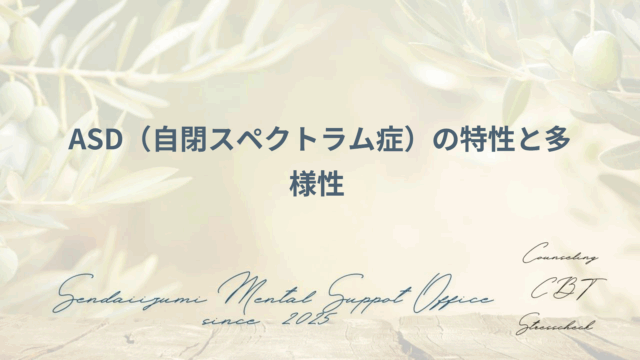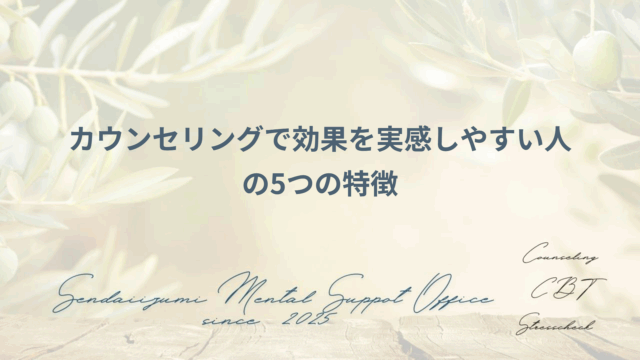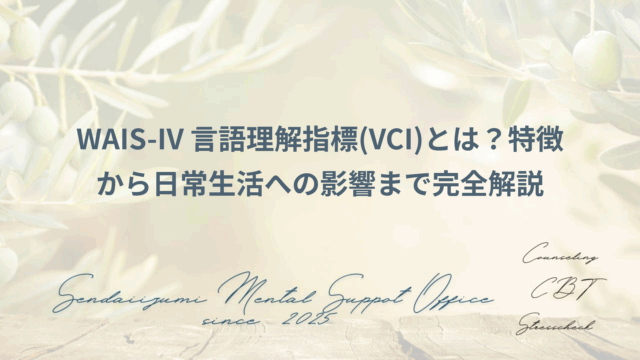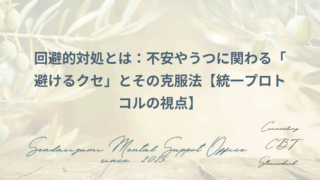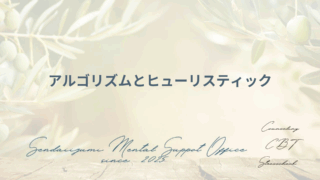発達障害の特性と、自分らしい生きやすさを考える ~診断だけがゴールじゃない~
もくじ
1. 発達障害とは? ~DSM-5-TRに基づく最新の理解~
発達障害は、脳の発達に関連する神経発達症群(Neurodevelopmental Disorders)の一つとして、DSM-5-TR(精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版・改訂版)に分類されています。特に以下の診断カテゴリーが代表的です:
✔ 自閉スペクトラム症(ASD)
✔ 注意欠如・多動症(ADHD)
✔ 学習障害(SLD)
これらは「障害」と呼ばれますが、決して”できない”とか”劣っている”ことを意味するわけではなく、あくまで【脳の特性の違い】が背景にあります。
2. 発達障害の主な特性
それぞれの診断ごとに、以下のような特性が見られることがあります。
自閉スペクトラム症(ASD)
・人とのコミュニケーションの苦手さ(空気の読みにくさ、冗談が理解しづらい など)
・強いこだわりや独自の興味関心
・音や光、感触などに敏感すぎたり、逆に鈍感だったり
注意欠如・多動症(ADHD)
・注意が散りやすく、忘れ物・ミスが多い
・思いついたことをすぐに口に出す、行動してしまう
・じっとしているのが苦手、落ち着かない感覚
学習障害(SLD)
・読み・書き・計算の一部が極端に苦手(例:文字の読み間違い、計算のズレ)
・知的能力は標準以上でも、特定の学習面だけが極端に困難
ただし、これらの特性はあくまで傾向であり、「○○があるから発達障害」と単純に決めつけられるものではありません。
3. 「何でも発達障害」の時代に思うこと
最近、「少し不器用だから発達障害かも」「空気読めない=発達障害」という声をよく耳にします。確かに、発達障害の概念が広く知られることは大切です。しかし一方で、「困りごとのすべてを発達障害で片づける」ような風潮には、少し慎重さも必要だと感じます。
本来、発達障害の診断は、専門的な評価と総合的な見立てのもとで行われるものです。「発達障害っぽいから…」と自分や他人をラベル付けするだけでは、本当の意味での理解や支援につながりにくいこともあります。
4. 診断の先にある「生きやすさ探し」
発達障害の診断は、あくまで一つの目安にすぎません。本当に大切なのは、診断があるかどうかに関わらず自分の特性を深く理解し、自分なりの生きやすさを見つけていくことです。
当オフィスでは、WAIS-Ⅳ(知能検査)を通して、以下のような自己理解のサポートを行っています。
✔ 得意なこと・苦手なことの具体的な傾向を把握できる
✔ 思わぬ困りごとや特性が数値として客観的に見える
✔ 自分に合った目標設定や、無理のない生活の工夫が考えやすくなる
WAISの結果は、「できる・できない」の単純な判定ではなく、自分らしく生活するためのヒントを得るきっかけになります。
「診断をつけるためだけではなく、自分を理解し、少しでも生きやすくする」
そんな視点から、必要に応じて検査やカウンセリングを活用していきましょう。
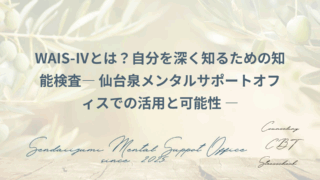
5. 最後に ~ラベルより、理解と工夫を~
発達障害の診断がつくかどうかは、一つの目安でしかありません。大切なのは、自分自身や身近な人の「特性」に目を向け、それを否定せず、工夫しながらより良い生活を目指していくこと。
「なんでも発達障害」ではなく、「自分を知り、自分に合った方法を探す」
そんな視点を大切に、一緒に考えていきませんか?
必要であれば、仙台泉メンタルサポートオフィスでも自己理解や生きづらさの相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。