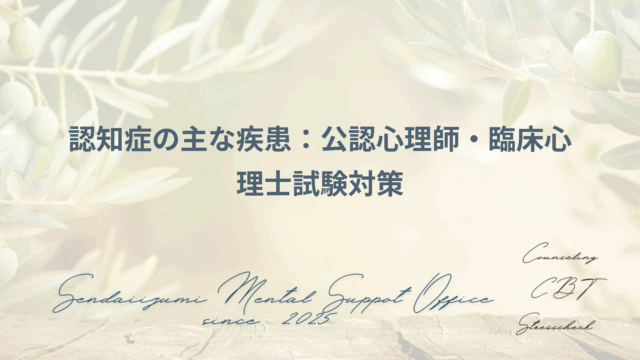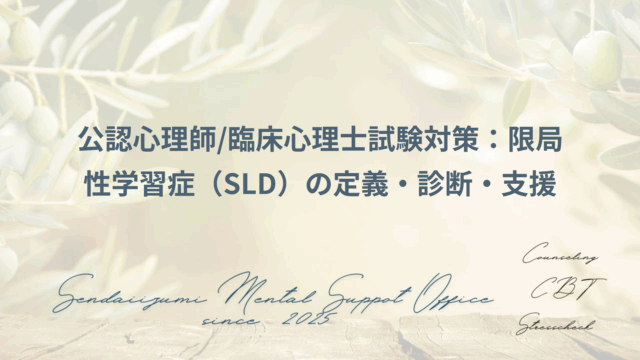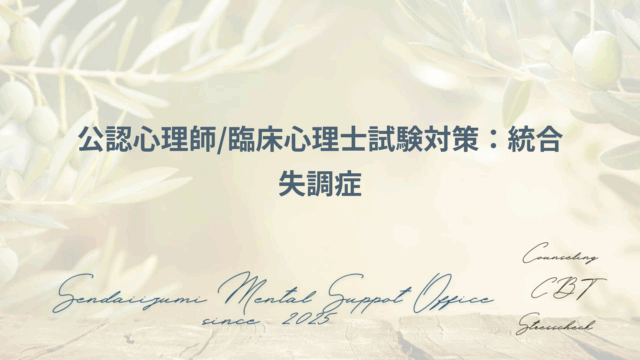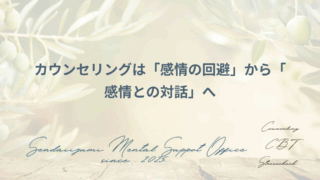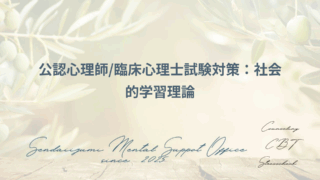公認心理師/臨床心理士試験対策:不安症群の理解と治療
この記事は、公認心理師・臨床心理士の国家試験対策として、不安症群の基礎知識から、特に重要となる薬物療法について詳細に解説するものです。
不安と恐怖の定義
心理学と精神医学の文脈において、「不安」と「恐怖」は異なる概念として区別されます。
- 恐怖 (Fear): 特定の対象や状況が直ちに認識可能な脅威である場合に生じる、情動的、身体的、行動的な反応です。例えば、目の前に蛇がいるときに感じるのは「恐怖」です。
- 不安 (Anxiety): 原因が不明確で不快な感情状態であり、脅威が予期されるときに生じたり、持続したりします。明確な脅威がないにもかかわらず生じることがあります。
ポイント: 不安症群は、この不安が過剰かつ持続的で、日常生活や社会機能に機能障害を伴う場合に診断される精神疾患群です。
不安症群の疫学と主な分類
不安症群は、生涯有病率が約3分の1と非常に高く、他の精神疾患よりも頻繁にみられます。
DSM-5-TRにおける主な不安症群: 発症年齢によって傾向が異なります。
- 小児期に多い: 分離不安症、場面緘黙
- 成人期に多い: 限局性恐怖症、社交不安症、パニック症、広場恐怖症、全般不安症
鑑別が重要: 他の医学的状態や物質・医薬品によって不安症状が引き起こされる場合があるため、診断時にはこれらを除外することが必須です(例:甲状腺機能亢進症、カフェイン過剰摂取、アルコール離脱など)。
不安症の症状と病因
不安症の症状は心理的なものだけでなく、身体症状が顕著に現れるのが特徴です。
主な症状:
- 持続性: 症状が6ヶ月以上続くこと、過剰さ、消耗性、不快さで正常な不安と区別されます。
- 身体症状:
- 消化管: 悪心、嘔吐、下痢
- 呼吸器: 息切れ、窒息感
- 自律神経: めまい、発汗、ホットフラッシュ、コールドフラッシュ
- 心臓: 動悸、心拍数増加
- 筋骨格: 筋緊張、胸痛、胸部圧迫感
病因:生物心理社会的要因:
- 遺伝的要因: 「行動抑制」気質(小児期)や家族内での伝播が関連します。
- 神経伝達物質: GABA、グルタミン酸、セロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどが複雑に関与しています。特に、GABAは抑制性の、グルタミン酸は興奮性の神経伝達物質であり、このバランスの崩れが不安の病態に関わるとされています。
- 環境要因: 早期の心的外傷体験(例:虐待)や、成人期のストレス因子が発症のリスクを高めます。
- 身体疾患・物質・薬剤: 前述の通り、これらが不安を直接引き起こす可能性があります。
不安症の治療法:精神療法と薬物療法
治療は精神療法と薬物療法の併用が最も効果的とされています。
精神療法
精神療法は、不安に対する認識や行動パターンを根本的に変えていくことを目指します。
- 心理教育: 不安症の病態を正しく理解し、治療への動機づけを高めます。
- リラクゼーション法: 不安の身体症状(動悸、筋緊張など)を軽減するために、筋弛緩法、呼吸管理法、瞑想法などが用いられます。
- 認知行動療法 (CBT): 不安症に対する最もエビデンスが確かな治療法です。
- 認知再構成法: 「危険の過大評価」や「自己能力の過小評価」といった不正確な思考パターンを特定し、より現実的な思考へと修正していきます。
- 曝露療法: 不安の対象を回避する行動を特定し、それを段階的に、安全な状況下で克服していく治療法です。例えば、閉所恐怖症の患者には、まず狭い部屋の写真を眺めることから始め、徐々に実際に小さな空間に身を置く練習をします。
薬物療法
薬物療法は、不安症状の軽減を通じて精神療法の効果を高める役割を果たします。
- SSRI (選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
- 作用: シナプス間隙のセロトニン濃度を増加させ、不安を軽減します。不安症治療の第一選択薬です。
- 特徴: 効果が現れるまでに通常6週間以上かかります。少量から開始し、副作用(吐き気、下痢など)に注意しながら徐々に増量します。
- 代表的な薬剤: パロキセチン(パキシル)、セルトラリン(ジェイゾロフト)、エスシタロプラム(レクサプロ)など。
- SNRI (セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)
- 作用: セロトニンとノルアドレナリンの両方の再取り込みを阻害することで、SSRIと同様の効果に加え、意欲低下や疼痛にも効果を発揮することがあります。
- 代表的な薬剤: デュロキセチン(サインバルタ)、ベンラファキシン(イフェクサー)など。
- ベンゾジアゼピン系薬剤
- 作用: 脳内のGABA受容体に作用し、GABAの神経抑制作用を強めることで、即効性の高い抗不安作用を発揮します。
- 特徴: パニック発作時など、不安の速やかな緩和に非常に有用ですが、依存性や耐性の形成、ふらつき、眠気などのリスクがあります。そのため、短期的な使用に限定されるのが一般的で、症状改善後に漸減(徐々に減らす)していきます。
- 代表的な薬剤: アルプラゾラム(コンスタン)、ロラゼパム(ワイパックス)、ジアゼパム(セルシン)など。
- その他の薬剤
- βブロッカー: 動悸や発汗などの身体症状の軽減に用いられることがあります。
- 抗精神病薬・気分安定薬: 重度の不安症状や、他の治療抵抗性のケースで、増強療法として少量投与されることがあります。
最後に 公認心理師・臨床心理士試験では、精神療法だけでなく、薬物療法に関する基本的な知識も問われます。薬物の種類と作用機序、注意点などを正確に理解しておくことが重要です。