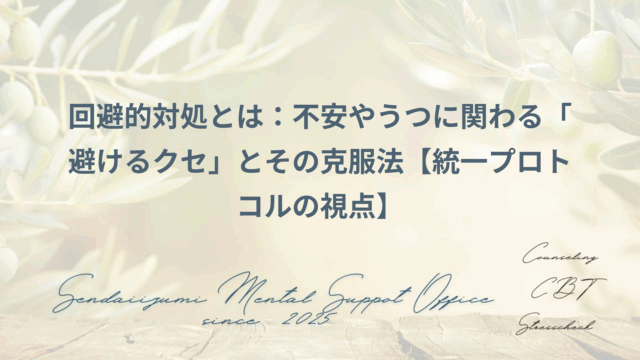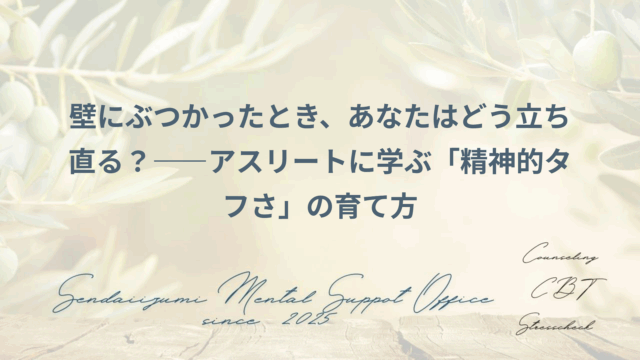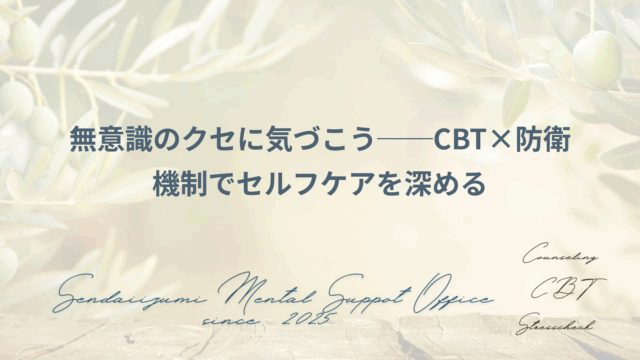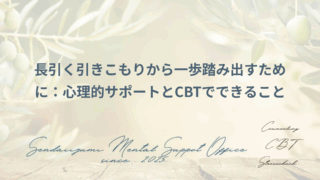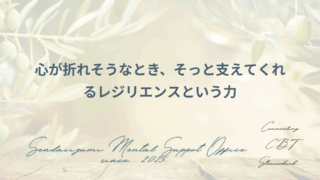理想の自分と現実の自分のギャップに悩んだときの対処法
私たちが心の中で思い描く「理想の自分」と、今ここにいる「現実の自分」との間にギャップを感じて苦しくなることは、誰にでもあるものです。
「もっと〇〇できる自分でいたいのに」「本当はこんな仕事をしていたはずだったのに」――そんな思いが積もっていくと、自分に対する不満や自己否定感が強まり、メンタルヘルスに影響を及ぼすこともあります。
今回は、理想と現実のギャップに悩んだとき、どのように向き合えばよいかを考えていきましょう。
もくじ
「理想自己」と「現実自己」──カール・ロジャースの理論から
心理学者カール・ロジャースは、人間の「自己」を以下の2つに分けて捉えました。
- 理想自己:自分が「こうありたい」と願う自己イメージ
- 現実自己:現在の自分の姿や状態
この2つの自己がある程度一致していると、人は自分自身に満足し、充実した生活を送りやすいとされています。
一方で、このギャップが大きいと、自分に対する不満や葛藤が強くなり、心の不調に繋がることもあります。
【事例1】性格面での理想と現実のズレ
Aさんは「自分は正直でありたい」という理想自己を持っていました。
ある日、帰宅が遅くなった理由を両親に聞かれたとき、Aさんは「飲み会が楽しくて帰れなかった」と正直に話しました。
結果として怒られたとしても、Aさんは「正直な自分でいられた」という充実感を感じたかもしれません。
もしこのとき、場を取り繕うために嘘をついていたら、「自分は正直者であるべきなのに」という葛藤から、罪悪感や自己否定感を抱えてしまったかもしれません。
【事例2】キャリア面での理想と現実のズレ
Bさんは大学時代から「安定した職に就きたい」と思い、公務員を目指して努力していました。
しかし、新卒では合格できず、現在は民間企業で働いています。
周囲からは「よい会社だね」と言われても、Bさんの中には「本当は公務員になっていたはずだったのに」という未練が残っており、現在の仕事にやりがいを見出せずにいます。
このように、将来像に強くこだわっていた分だけ、その理想に届かなかったときの落差は大きくなりやすいのです。
理想と現実のギャップに悩んだときの3つの対処法
1.理想に近づくために努力を続ける
理想を持ち、それに向かって努力をすることは人としての成長につながる大切な力です。
特に「努力家」や「ストイックな性格」の方は、ギャップを埋めようと頑張り続ける傾向があります。
ただし、無理を重ねすぎると、疲弊してしまい、バーンアウト(燃え尽き)に繋がる可能性もあります。
努力する過程で、心や体に負担がかかりすぎていないかを時々立ち止まって振り返ることも大切です。
2.理想の水準を柔軟に見直す
子どもが「プロのサッカー選手になりたい」と夢見るのは自然なことですが、成長とともに自分の適性や現実を知り、別の道を見つけていくことがあります。
このように、「別の目標を立て直す」ことも、自分を責めるのではなく、今できる選択肢に目を向ける柔軟さの表れです。
理想を下げるというよりも、“現実に即した理想を再設定する”ことが、自分らしく生きる手助けになります。
3.今の自分を受け入れる
「このままでもいい」と思えるようになることも、大きな心の支えになります。
理想を追い求めることに疲れたとき、「今の自分にOKを出す」「何かを成し遂げなくても、自分には価値がある」と感じられることは、深い安心感に繋がります。
もちろん、それだけで満足してしまえば、成長の機会は少なくなるかもしれません。
ですが、「今の自分を受け入れる」ことと「成長をあきらめる」ことはイコールではありません。
まずは、自分を責めず、優しく認めることから始めてみてはいかがでしょうか。
最後に
理想と現実のギャップは、誰にとっても悩みの種になり得るものです。
大切なのは、そのギャップをどう捉え、どう向き合っていくかです。
「今の自分も、理想に向かう自分も、どちらも大切にする」そんなバランス感覚が、心の健やかさを保つカギになるかもしれません。
つらさを感じたときには、ひとりで抱え込まず、専門家に相談してみることも選択肢の一つです。悩みが少しでも楽になれるよう、仙台泉メンタルサポートオフィスはサポートを続けています。