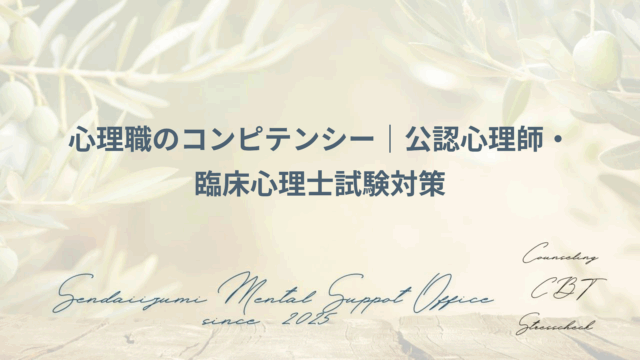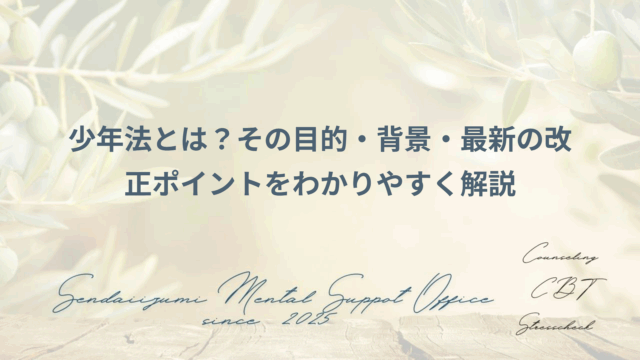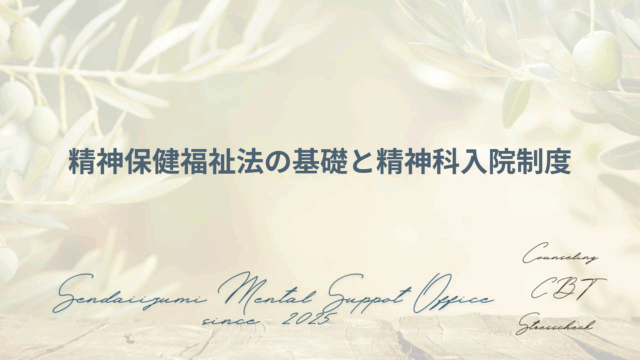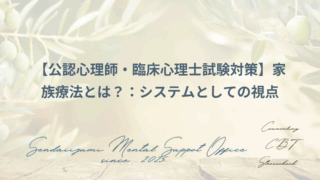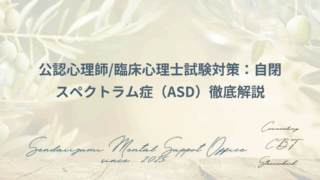【公認心理師・臨床心理士試験対策】児童相談所の役割と任務
児童相談所は、子どもに関するあらゆる相談に応じ、子どもの福祉を図り、その権利を擁護することを主たる目的として設置される行政機関です。近年、児童虐待の増加や家庭問題の複雑化に伴い、その役割はより専門的かつ重要になっています。
児童相談所の基本的な任務
児童相談所は、以下の3つの条件を満たすことが求められています。
- 児童福祉に関する高い専門性を有していること:児童福祉司、児童心理司、医師などの専門職が連携し、多角的な視点から援助を行います。
- 地域住民に浸透した機関であること:早期発見・早期対応のため、地域住民や関係機関への情報提供や啓発活動を積極的に行います。
- 児童福祉に関する機関・施設等との連携が十分に図られていること:市町村や学校、医療機関、警察、児童福祉施設など、多様な機関とのネットワークを構築し、一体的な援助活動を展開します。
市町村との連携:役割分担の明確化
平成16年の児童福祉法改正により、児童家庭相談における市町村と児童相談所の役割分担がより明確になりました。これは、住民に身近な市町村が、虐待の未然防止や早期発見を中心にきめ細かな対応を行い、児童相談所がより専門的な対応に特化するためです。
| 機関 | 役割 |
| 市町村 | 育児不安などの身近な相談、実情の把握、情報の提供。専門的な知識や技術を要する相談については、児童相談所への援助や助言を求める。 |
| 児童相談所 | 専門的な知識や技術を必要とする相談への対応、市町村への後方支援。具体的には、医学的・心理学的・教育学的・社会学的・精神保健上の判定や、一時保護・措置などを行う。 |
児童相談所の設置と管轄
- 中核市規模の市も設置可能(平成18年以降)
- 設置義務:都道府県・指定都市(児童福祉法第12条、第59条の4)
- 設置目安:人口50万人に1か所程度
- 管轄区域を設定し、連絡調整のため中央児童相談所を指定可能
- 原則として一時保護所を併設
児童相談所の機能と業務
児童相談所は、相談援助活動を展開するために、以下の5つの基本機能を担っています。これらの機能は、各専門職がチームを組んで協議し、援助指針という形で具体的な支援計画に落とし込まれます。
- 相談機能:子どもや家庭からの相談を受け付け、専門的見地から問題を把握します。
- 調査・診断(アセスメント)・判定機能:児童心理司による心理診断、医師による医学診断、児童福祉司による社会診断などを通して、子どもの状況や家庭環境を総合的に評価し、援助方針を策定します。
- 一時保護機能:子どもを家庭から離す必要がある場合、安全を確保するために一時的に保護します。
- 措置機能:子どもの福祉を図るため、児童福祉司による指導、児童福祉施設への入所、里親への委託といった措置を決定し、実施します。
- 市町村援助機能:市町村の児童家庭相談の実施に対し、技術的な援助や助言、情報提供などを行います。
相談の種類と対応
児童相談所が扱う相談は多岐にわたりますが、大きく以下の5つに分類されます。
- 養護相談:保護者の養育放棄(ネグレクト)、虐待など、保護者の監護能力に問題があるケース。
- 障害相談:身体的、知的、精神的な障害に関する相談。
- 非行相談:盗み、家出、虞犯行為など、非行傾向にある子どもに関する相談。
- 育成相談:性格や行動、しつけ、不登校など、子どもの心身の発達や養育に関する相談。
- その他の相談:里親希望に関する相談など、上記に分類されない相談。
- いじめ相談:子供本人や保護者への対応の他、学校や教育委員会との連携、医療機関や警察への協力依頼などに対応。
援助指針の重要性
援助指針は、児童相談所が子どもと家族に対して行う援助の羅針盤です。多職種による専門的なアセスメント(調査・診断)に基づき、具体的な援助目標、方法、連携する機関などを明確に定めます。援助が開始された後も、定期的に再検討が行われ、常に子どもの最善の利益が図られるよう柔軟に見直されます。この援助指針は、児童相談所と子ども、保護者、そして関わるすべての関係機関をつなぐ重要な役割を果たしています。