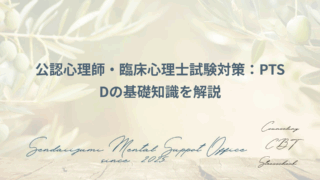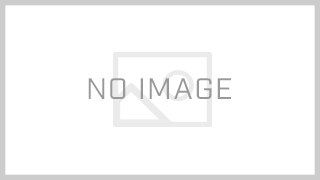【基礎心理学:心理学史】演習問題:公認心理師試験/臨床心理士試験対策
臨床心理士試験の問題様式に則っていますが、公認心理師試験対策にも活用できると思います。
問題1 次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。
a. W. Wundt は、ヴュルツブルク学派の中心人物であり、思考の構造を内観法によって研究した。
b. J. B. Watson は、人間行動を客観的に測定・観察できるものに限定し、意識や心という概念を研究対象から除外した。
c. G. S. Hall は、アメリカで精神分析を広めた人物であり、フロイトを講演に招聘した。
d. M. Wertheimer は、行動を要素に還元して分析することを主張し、精神物理学を確立した。
e. Witmerは、世界初の「心理学的クリニック」を創設し、入院患者のベッドサイド面接に関心を示していた。
答えはコチラ
正答: b
J. B. Watson は、人間行動を客観的に測定・観察できるものに限定し、意識や心という概念を研究対象から除外した。
解説
この問題は、主要な心理学派とその創始者、およびその理論的特徴に関する基本的な知識を問うものです。
a. 不適切
W. Wundtは実験心理学の創始者であり、ライプチヒ大学に世界初の心理学実験室を設立しました。彼が用いたのは要素主義的な内観法です。ヴュルツブルク学派は、思考の構造を研究しましたが、これはWundtの要素主義に反するものでした。
b. 適切
J. B. Watsonは行動主義(Behaviorism)の創始者です。彼は、意識や内的な精神状態は科学的な研究対象にはなり得ないと主張し、客観的に観察・測定可能な行動のみを心理学の研究対象としました。
c. 不適切
G. S. Hallは、アメリカで実験心理学の発展に貢献し、アメリカ心理学会(APA)の初代会長を務めた人物です。彼は、フロイトをクラーク大学の講演に招聘し、アメリカに精神分析を紹介する上で重要な役割を果たしました。
d. 不適切
要素に還元して分析することを主張したのはWundtの要素主義です。M. Wertheimerは、知覚が全体として組織化されることを主張したゲシュタルト心理学の創始者の一人です。精神物理学は、G. T. FechnerとE. H. Weberによって確立されました。
e. 不適切
Witmerは、世界初の「心理学的クリニック」を創設したことは事実であるが、主として読字障害などにより学校に適応できない子どもたちに関心を示していた。
問題2 次の心理学者とその概念の組み合わせとして、最も不適切なものを一つ選びなさい。
a. A. Freud – 防衛機制
b. K. Lewin – プレグナンツの法則
c. D. Winnicott – 移行対象
d. K. Rogers – 無条件の肯定的配慮
e. E. Erikson – 心理社会的発達理論
答えはコチラ
解答: b
K. Lewin – プレグナンツの法則
解説
この問題は、主要な心理学者と彼らが提唱した概念との関連性を問うものです。臨床心理士試験では、個々の概念だけでなく、それがどの心理学者のどの理論に属するのかを正確に理解しておく必要があります。
a. 適切
A. Freud(アンナ・フロイト)は、自我心理学の創始者の一人であり、父親であるS. Freud(ジークムント・フロイト)の理論を発展させ、防衛機制の概念を体系化しました。
b. 不適切
K. Lewin(クルト・レヴィン)は、場(field)の理論を提唱した人物で、ゲシュタルト心理学の影響を受けて社会心理学を確立しました。一方、プレグナンツの法則は、ゲシュタルト心理学の創始者の一人であるM. Wertheimerが提唱した概念で、人間が知覚をできるだけ簡潔で規則的な「よい形」としてまとめる傾向を説明するものです。
c. 適切
D. Winnicott(ドナルド・ウィニコット)は、対象関係論の理論家であり、乳幼児が母親から分離していく過程で重要となる移行対象の概念を提唱しました。
d. 適切
K. Rogers(カール・ロジャーズ)は、来談者中心療法の創始者です。彼は、セラピストがクライエントに対して示すべき3つの基本的態度の一つとして、無条件の肯定的配慮を強調しました。
e. 適切
E. Erikson(エリク・エリクソン)は、S. Freudの精神分析を社会文化的な側面から再解釈し、人の発達を生涯にわたる8つの段階で捉える心理社会的発達理論を提唱しました。
問題3次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。
a. René Descartes の提唱した心身二元論において、心と身体は相互作用しないとされた。
b. Hippocrates の4気質説は、科学的根拠に基づくものであり、現代のパーソナリティ心理学に直接的な影響を与えた。
c. Weber-Fechnerの法則は、心理学を科学として確立する上で重要な役割を果たし、感覚と刺激の大きさが直線関係にあることを証明した。
d. Weberの法則によれば、刺激の弁別閾は、標準刺激の大きさに対する絶対的な差によって決まる。
e. Aristotleは『霊魂論』の中で、心は脳に宿るものとし、感覚や思考を神経系と関連付けて論じた。
答えはコチラ
正答:d. Weberの法則によれば、刺激の弁別閾は、標準刺激の大きさに対する相対的な差によって決まる。
この選択肢が最も適切です。
ヴェーバーの法則は、心理学を科学として確立する上で重要な役割を果たした「精神物理学」の法則の一つです。この法則は、刺激の弁別閾(ちょうどの違いがわかる最小の差)は、刺激の絶対的な大きさではなく、標準刺激の大きさに対する一定の比率(相対的な差)で決まることを示しています。
具体的な例: あなたが手に40gのおもりを持っているとします。このおもりにさらに重りを加えて「重くなった」と感じる最小の差が1gだった場合、ヴェーバーの法則によれば、200gのおもりの場合は「重くなった」と感じるために5gの差が必要になります。これは、どちらの場合も、追加された重りの大きさが元の重さの2.5%(1g/40g = 5g/200g = 0.025)だからです。
この法則は、人間の感覚が刺激を絶対的な量でなく、相対的な比率で判断することを示しています。
各選択肢の解説
a. デカルトの提唱した心身二元論において、心と身体は相互作用しないとされた。
デカルトは心と身体を全く異なる実体と考えましたが、両者は完全に独立しているわけではなく、脳の松果腺という部位で相互作用すると提唱しました。
b. ヒポクラテスの4気質説は、科学的根拠に基づくものであり、現代のパーソナリティ心理学に直接的な影響を与えた。
ヒポクラテスの4気質説は、人間の性格を血液・粘液・黒胆汁・黄胆汁という4つの体液のバランスで説明するもので、科学的な根拠はありません。現代のパーソナリティ心理学に直接的な影響を与えたとは言えませんが、人間の性格を類型化しようとした歴史的な試みとして重要です。
c. ヴェーバー-フェヒナーの法則は、心理学を科学として確立する上で重要な役割を果たし、感覚と刺激の大きさが直線関係にあることを証明した。
ヴェーバー-フェヒナーの法則は、心と体の関係を数量的に示した点で画期的でしたが、感覚と刺激の大きさの関係は対数関係(曲線)であり、直線関係ではないことを示しました。
e. アリストテレスは『霊魂論』の中で、心は脳に宿るものとし、感覚や思考を神経系と関連付けて論じた。
アリストテレスは、心(魂)は身体全体に宿るものと考え、特に心の働きの中枢は心臓にあると論じました。脳が心の座であるという考え方は、それよりも後の時代に広まりました。
問題4以下の記述に関する記述として、最も適切な組み合わせを、下のa~eの中から一つ選びなさい。
A. 要素主義は、ヴントによって提唱され、意識を感覚や感情などの基本要素に分解し、その組み合わせを研究対象とした。
B. 構成主義は、意識の機能や適応的な役割を重視し、「意識の流れ(stream of consciousness)」という概念を提唱した。
C. 機能主義は、ティチェナーによってアメリカに広められ、内観法によって意識の構造を明らかにすることを目的とした。
D. 機能主義は、なぜ人間が特定の行動をとるのかという問いに答えようとし、プラグマティズムの思想を背景に持つ。
a. AとB
b. AとD
c. BとC
d. CとD
e. BとD
答えはコチラ
正答: b. AとD
解説
この問題は、実験心理学の黎明期に登場した3つの主要な学派、要素主義、構成主義、機能主義の特徴と関係性を問うものです。
- A. 適切
- 要素主義は、心理学の父とされるW. Wundt(ヴント)が提唱しました。彼は、化学が物質を元素に分解するように、人間の意識も感覚や感情といった基本的な要素に分解できると考え、これを研究の主眼としました。
- B. 不適切
- 意識の流れや過程を重視し、「意識の流れ(stream of consciousness)」という概念を提唱したのは、W. James(ジェームズ)が提唱した機能主義です。構成主義の記述ではありません。
- C. 不適切
- 構成主義は、ヴントの弟子であるE. B. Titchener(ティチェナー)によってアメリカに広められました。彼は内観法を厳密に用い、意識の構成要素を分析することで、その構造を明らかにしようとしました。この記述は構成主義の特徴であり、機能主義の特徴ではありません。
- D. 適切
- 機能主義は、W. Jamesによって提唱され、「心は何のためにあるのか」という問い、つまり意識の機能や適応的な役割を重視しました。彼らは、意識が環境に適応し、人間が生存していく上でどのように役立つかを研究しました。この思想の背景には、プラグマティズム(実用主義)という哲学がありました。
したがって、要素主義と機能主義の特徴を正しく述べたAとDの組み合わせが正解となります。
問題5次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。
a. E. C. Tolmanは、オペラント条件づけの理論を確立し、学習には反応の後に強化が伴うことが必要だと主張した。
b. J. B. Watsonは、環境刺激と行動の間に「動因低減」を導入し、目的的な行動の研究を重視した。
c. C. L. Hullは、学習を「近接性」の法則だけで説明しようとし、強化の反復は必ずしも必要ではないと考えた。
d. B. F. Skinnerは、観察可能な行動のみを研究対象とし、「アルバート坊やの実験」による恐怖条件づけを実証した。
e. E. C. Tolmanは、期待や認知地図といった媒介変数(O)を導入し、S-O-Rという理論モデルを提唱した。
答えはコチラ
正答:e
E. C. Tolmanは、期待や認知地図といった媒介変数(O)を導入し、S-O-Rという理論モデルを提唱した。
この選択肢が最も適切です。
E. C. Tolman(トールマン)は、ワトソンの単純なS-R(刺激-反応)モデルに対し、環境と行動の間に媒介変数(O:Organism、有機体)を導入しました。彼は、ラットの迷路学習実験などを通して、行動の背後には期待や認知地図といった内的プロセスがあることを示し、S-O-Rという理論モデルを提唱しました。この考え方は、その後の認知心理学の成立に大きな影響を与えました。
各選択肢の解説
- a. 不適切
- オペラント条件づけの理論を確立し、学習には反応の後に強化が伴うことが必要だと主張したのはB. F. Skinner(スキナー)です。
- b. 不適切
- J. B. Watson(ワトソン)が提唱した古典的行動主義は、観察可能な行動のみを研究対象とし、内面的な心的プロセスを完全に排除しました。「動因低減」を導入したのはC. L. Hull(ハル)です。また、行動に目的があることを重視したのはE. C. Tolman(トールマン)です。
- c. 不適切
- 学習を「近接性」の法則だけで説明しようとし、強化の反復は必ずしも必要ではないと考えたのはE. R. Guthrie(ガスリー)です。
- d. 不適切
- 「アルバート坊やの実験」は、J. B. Watson(ワトソン)によって行われたものです。この実験は、恐怖という情動反応が古典的条件づけによって学習されることを示しました。したがって、人物と研究内容の組み合わせが間違っています。