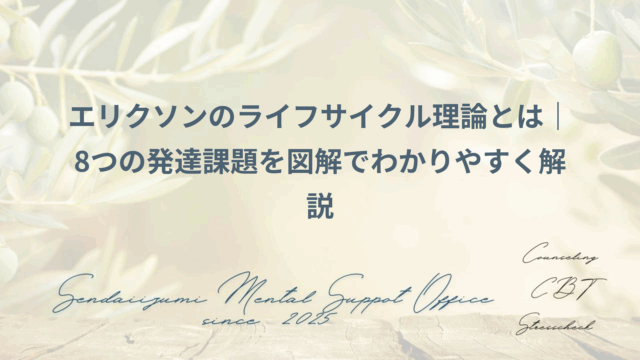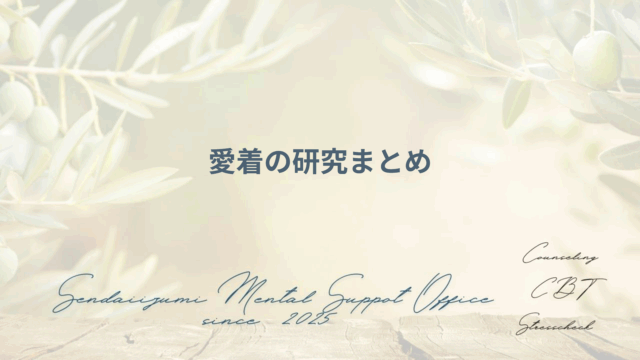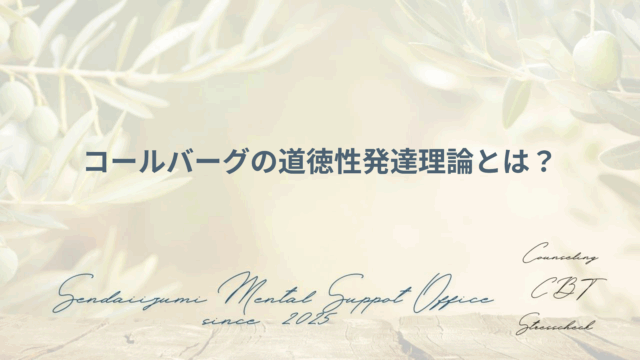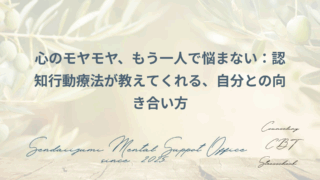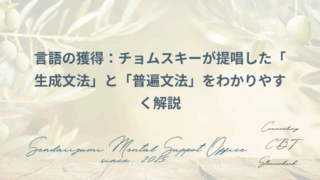思考の進化:ヴィゴツキーの「内言」と「外言」をわかりやすく解説
私たちは普段、頭の中で様々なことを考えています。この「考える」という行為は、どのように発達し、どのような形をとっているのでしょうか?
今日は、ソビエトの心理学者レフ・ヴィゴツキーが提唱した、思考と言葉の関係性を示す重要な概念である「外言(がいげん)」と「内言(ないげん)」について、わかりやすく解説していきます。
1. 外言(がいげん)とは?
「外言」とは、読んで字のごとく「外に出る言葉」のことです。具体的には、私たちが他人とコミュニケーションを取るために使う、声に出る話し言葉や、文字に書かれる書き言葉を指します。
ヴィゴツキーは、子どもの思考の発達において、まずこの「外言」が先行すると考えました。
【具体例】
- 幼い子どもが、遊びながら「これ、こうするんだよ」「もっと大きいのがほしいな」と独り言を言う。
- 友達と「あのね、これこうするんだよ!」と話す。
これらは、思考を直接的に、声に出して表現している状態です。子どもは、最初は思考と行動が一体になっており、言葉も思考の道具として外に表れています。しかし、この外言が、やがて内的な思考へと変化していきます。
2. 内言(ないげん)とは?
「内言」とは、「心の中の言葉」と考えると理解しやすいでしょう。これは、声に出さずに頭の中で行われる思考の言語です。独り言が声に出なくなったり、頭の中で黙々と計画を立てたり、問題を解決しようとしたりする際に使われる、私たち自身の「心の声」のようなものです。
ヴィゴツキーは、この内言が、外言が発達した後に形成される、より高度な思考の形態であるとしました。子どもが成長するにつれて、外に向かって発していた言葉が徐々に短縮され、意味が凝縮され、最終的には声に出さずに思考するための道具となるのです。
【具体例】
- テスト中に、声には出さずに頭の中で「この問題はこう解くべきだ」「こっちの公式を使うかな」と考える。
- 買い物リストを見ながら、「まずは野菜コーナーに行って、それから肉だな」と頭の中で順序立てる。
- 誰かに何かを話す前に、頭の中で「どう説明すれば一番伝わるかな」とシミュレーションする。
内言は、私たちの思考を整理し、計画を立て、問題を解決するために不可欠なプロセスであり、より効率的で抽象的な思考を可能にします。
3. 外言から内言への発達の過程
ヴィゴツキーによれば、この移行は一方向的でなく、以下のような段階を経て進みます。
- 社会的言語(外言):初期段階。子どもは他人とのコミュニケーションのために言葉を使う。
- 自己中心的言語(外言の一種):他人とのコミュニケーションを目的としながらも、自分自身に向けて発される独り言。思考と行動を調整する役割を持つ。
- 内言:自己中心的言語が「声に出ない」形へと移行し、思考そのものの道具となる。
つまり、最初はコミュニケーションのための「外言」があり、それが自分自身の思考を整理するための「独り言」のような形(自己中心的言語)を経て、最終的に声に出さない「内言」として心の内に取り込まれていく、とヴィゴツキーは考えました。この過程で、言葉は単なる伝達手段から、思考の道具そのものへと進化するのです。
まとめ
ヴィゴツキーの「外言」と「内言」の概念は、私たちがどのように言葉を獲得し、それがどのように思考と結びついていくのかを理解する上で非常に重要です。
- 外言:他人とのコミュニケーションに使われる、声に出る言葉。
- 内言:声に出さずに頭の中で行われる、思考のための言葉。
この二つの概念を理解することで、子どもの発達過程はもちろん、大人である私たちが日々どのように思考を巡らせているのかについても、新たな視点が得られるのではないでしょうか。