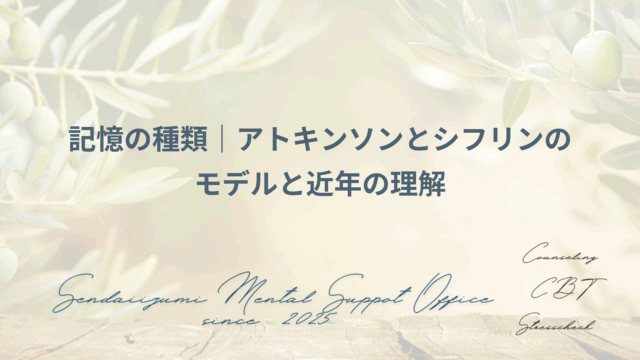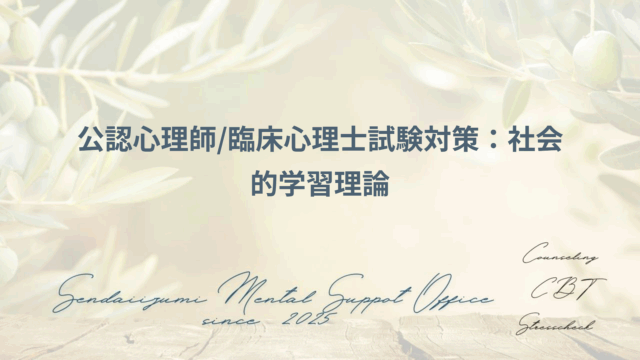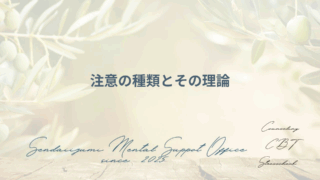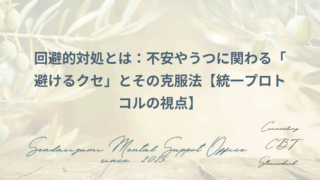プロスペクト理論|人は「損失」に敏感?心理学が解き明かす意思決定のゆがみ
もくじ
1.プロスペクト理論とは?
プロスペクト理論(Prospect Theory)は、ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーが1979年に提唱した、不確実な状況下での意思決定に関する心理学モデルです。
この理論は、人間の意思決定が常に合理的とは限らず、「損失の回避」や「確率のゆがんだ認知」に大きく影響されることを示しています。
特に、以下のような特徴がプロスペクト理論のポイントです。
- 客観的には同じ結果でも、**表現方法(フレーミング)**によって選択が変わる
- 損失を過大に評価し、得を過小評価する傾向(損失回避性)
- 実際の確率とは異なる主観的な確率判断(確率加重)
この理論は、臨床現場の相談支援や、社会心理学・経済行動の理解、心理系試験対策にも重要な知識です。
2.有名な「アジア疾病問題」の実験
カーネマンとトヴェルスキーが行った「アジア疾病問題(Asian Disease Problem)」は、プロスペクト理論を裏付ける代表的な実験です。
【実験内容】
600人が死亡すると予測される未知の病気が流行。以下の2パターンの説明を被験者に提示し、選択を求めました。
▶ パターン1(ポジティブフレーム:生存に焦点)
- 対策A:確実に200人が助かる
- 対策B:3分の1の確率で600人全員が助かるが、3分の2の確率で全員が死亡する
この場合、多くの人が「リスク回避的」な対策A(確実に助かる選択)を選びました。
▶ パターン2(ネガティブフレーム:死亡に焦点)
- 対策C:確実に400人が死亡する
- 対策D:3分の1の確率で誰も死亡せず、3分の2の確率で全員が死亡する
この場合、同じ内容にもかかわらず、多くの人が「リスク選好的」な対策D(不確実だが全員助かる可能性)を選びました。
【ポイント】
客観的には、A=C、B=D であり、内容は同じです。しかし、表現の違い(ポジティブフレーム/ネガティブフレーム)が意思決定を大きく左右しました。これを「フレーミング効果」といいます。
3.プロスペクト理論の構成要素
プロスペクト理論では、人間の意思決定に影響する要素を以下の2つで説明しています。
① 価値関数(損失回避性)
- 得よりも損の影響が大きく感じられる
- 利得が増えても主観的価値の増加は鈍化し、損失は少しでも強く感じる
- 例:5万円当たるくじと、10万円当たるが外れると10万円損するくじ → 多くの人が前者を選ぶ
この「損失回避性」は、人間の不合理なリスク選好を説明する重要概念です。
② 確率加重関数(確率のゆがみ)
- 低確率は過大評価し、高確率は過小評価する傾向
- 例:宝くじは当たる確率が非常に低いが、「当たるかも」と期待する
- 逆に、70%成功する手術でも「失敗するかも」と過度に不安を感じる
私たちは客観的な確率通りに判断せず、主観的な歪みに基づき意思決定をすることが示されています。
4.編集段階と評価段階
プロスペクト理論では、意思決定のプロセスを以下の2段階で捉えます。
- 編集段階:問題の捉え方やフレーミングを決める段階。ここで表現方法により選択が影響される(フレーミング効果が生じやすい)
- 評価段階:選択肢を比較し、実際の意思決定を行う段階
つまり、最初の「問題の枠組み」次第で選択が変わるということが、実証的に示されています。
5.まとめ:実生活と試験対策に活かす
プロスペクト理論は、私たちが「いかに感情や表現方法に影響されて非合理的な判断をするか」を説明しています。
特に、公認心理師や臨床心理士としては、クライアントの意思決定場面でこの理論を理解し、相談支援に活かすことが重要です。