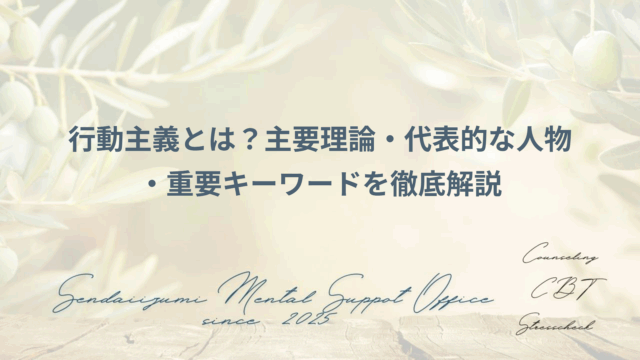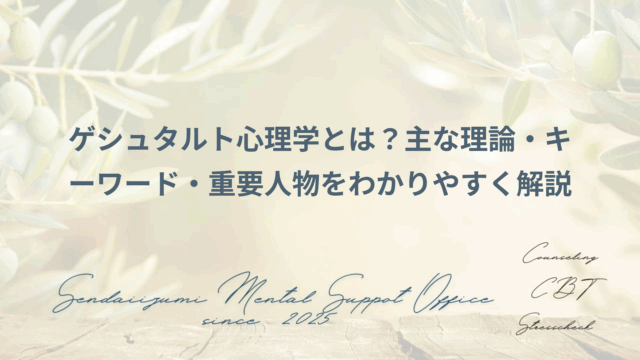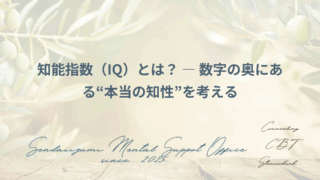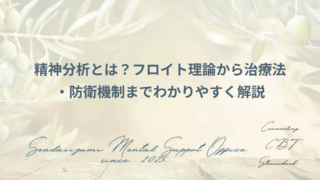要素主義・構成主義・機能主義の違いとは?─ 心の仕組みをめぐる三つの立場
心理学の黎明期において、「心とは何か?」をめぐるさまざまな理論が提唱されました。今回は、近代心理学の出発点となる要素主義・構成主義・機能主義という三つの立場を整理し、それぞれの特徴と相違点をわかりやすく解説します。
もくじ
要素主義・構成主義:心を“構成要素”から理解する試み
要素主義(ヴント)
要素主義は、ドイツの心理学者ヴィルヘルム・ヴントによって提唱されました。
彼は心理学を自然科学的に研究すべきと考え、内観法(introspection)という手法を用いて、人間の意識を構成する「基本的感覚」と「単純感情」という要素の集合体として心を捉えようとしました。
▶︎ 例:「リンゴ」を見た時の要素
- 基本的感覚:「赤い」「丸い」
- 単純感情:「おいしそう」「硬そう」
構成主義(ティチナー)
構成主義は、ヴントの弟子エドワード・ティチナーがアメリカで展開した理論で、要素主義の影響を強く受けています。
彼もまた心を構成要素の組み合わせとして理解しようとし、感覚・イメージ・感情の三つを意識の基本的要素と位置づけました。
▶︎ 要素主義と構成主義の共通点
どちらも「意識は要素の集合で構成されている」という前提を共有しており、基本的には同じ立場とみなされます。
機能主義:心の“働き”に注目する立場
機能主義は、「心とはどのように働くか」「人の意識は環境にどう適応するか」といった機能的側面に注目する心理学の立場です。
思想的背景:プラグマティズムと進化論
機能主義は、ダーウィンの進化論の影響を受けたプラグマティズムの考え方に基づいています。つまり、行動や意識の働きが「環境への適応」においてどのような意味を持つのかを重視します。
ウィリアム・ジェームズの主張
アメリカ心理学の父と称されるウィリアム・ジェームズは、意識は「連続的な流れ(stream of consciousness)」であり、固定的な要素の集合ではないと主張しました。
▶︎ 例:「リンゴ」を見る場面
- 空腹時:「おいしそう」と感じる
- 満腹時:「あまり食べたくない」と感じる
同じ刺激でも、状況や状態によって心の働きが変化する点に注目したのが機能主義の特徴です。
構成主義との対立
構成主義が「心の構造(何でできているか)」に注目したのに対し、機能主義は「心の働き(どのように機能するか)」に注目したため、両者は明確に対立しました。
要素主義・構成主義 vs. 機能主義:比較表
| 観点 | 要素主義・構成主義 | 機能主義 |
|---|---|---|
| 主な人物 | ヴント、ティチナー | ウィリアム・ジェームズ |
| 関心の焦点 | 心の構造(何でできているか) | 心の機能(どう働くか) |
| 方法論 | 内観法 | 行動観察、経験の文脈重視 |
| 思想的背景 | 構成主義的科学観 | プラグマティズム、進化論 |
| 影響を与えた学派 | 構成主義はその後衰退 | 行動主義、学習理論などへ発展 |
補足:ゲシュタルト心理学の台頭
要素主義・構成主義に対して、別の角度から反論を加えたのがゲシュタルト心理学です。
マックス・ヴェルトハイマーらによって提唱されたこの立場では、「人間の心は要素の寄せ集めではなく、全体として捉えられる構造が重要」とされました。
▶︎ 例:メロディの知覚
- 音一つひとつではなく、全体としての旋律を感じ取るという知覚過程を重視
ゲシュタルト心理学は、後の知覚心理学・認知心理学・社会心理学などに大きな影響を与える一方、構成主義は次第に影響力を失っていきました。
まとめ:なぜこの違いが重要か?
心理学の学派の違いは、心の何を問題とするか(構造 or 機能)という観点の違いに起因しています。
要素主義や構成主義の考え方は、心理学の自然科学的アプローチの基礎となりましたが、その後の展開は機能主義やゲシュタルト心理学が主導しました。
大学院受験や公認心理師試験・臨床心理士試験では、こうした学派の特徴や代表的な人物、背景理論の理解が頻出分野となっています。特に要素主義 vs. 機能主義、構成主義 vs. ゲシュタルト心理学といった対比の視点を持つことが、応用力につながるでしょう。