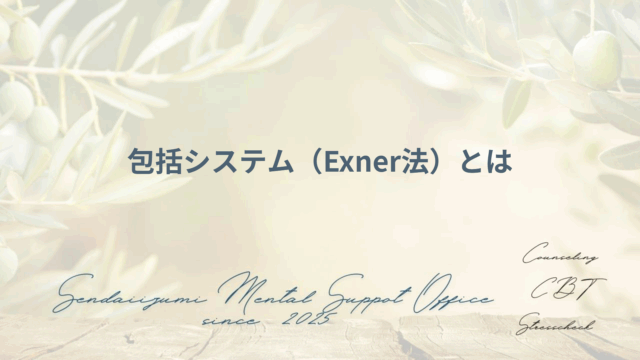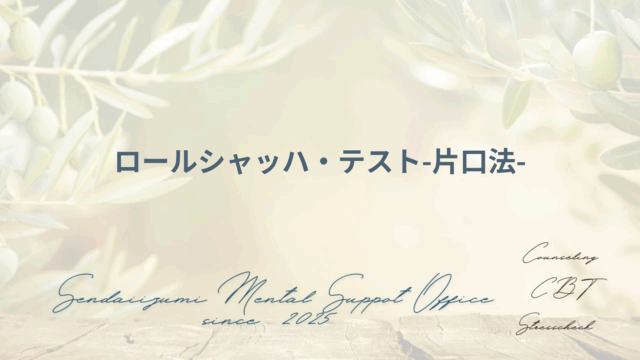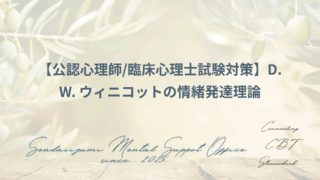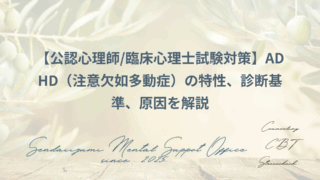【公認心理師/臨床心理士試験対策】内田クレペリン検査の解説
もくじ
はじめに
公認心理師・臨床心理士を目指す皆さん、日々の学習お疲れ様です。今回は、日本で最も長く使われ、現在でも年間70万人以上が受検している**「内田クレペリン検査」**について解説します。これは、採用・適性検査や職場復帰支援など、産業・臨床の幅広い領域で活用される重要な心理検査です。
1. 内田クレペリン検査の概要と方法
内田クレペリン検査は、心理検査の中でも作業検査法に分類されます。
| 項目 | 内容 |
| 概要 | 隣り合う数字の連続加算(下一桁のみ記入)を行う。受検者の作業量の水準と作業曲線の特徴から、性格・行動面の特徴を評価する。 |
| 検査時間 | 合計30分間実施。前半15分(作業)、休憩5分、後半15分(作業)。 |
| 記録方法 | 1分ごとに行を変える。各行の計算が終わった右側の数字を結びつけることで、作業曲線を作成する。 |
| 起源 | ドイツの精神医学者 E. クレペリンの精神作業に関する実験心理学的研究を、日本の心理学者 内田勇三郎が精神検査法として発展させたもの。 |
2. 解釈の中心:「作業曲線」と「定型曲線」
検査結果の解釈は、得られた作業曲線と、健康な人々の平均的な曲線である「定型曲線」とを比較することで行われます。
定型曲線(健康者常態定型)の特徴
心的活動の調和と均衡が保たれている人々に現れる特徴で、性格・行動面で問題がないと見なされます。
- 前期(前半15分)の骨組みがU字型(またはV字型)を示す。
- 後期(後半15分)の骨組みが右下がり(徐々に減少)を示す。
- 前期より後期に作業量が増加し、後期1分目が最高位を示す。(レミニッセンス効果)
- 曲線に適度な動揺がある。
- 誤答がほとんどない。
- 作業量が低すぎない。
非定型曲線(異常型)の特徴
定型曲線から逸脱した特徴を持つ曲線で、性格や行動面、あるいは心身の状態に何らかの問題や偏りが示唆されます。
- 誤答の多発
- 大きい落ち込みや突出、激しい動揺、または動揺の欠如
- 後期初頭の出不足(休憩後の作業量が上がらない)
- 作業量の著しい不足や、後期作業量の下落
3. 評価の軸と重要キーワード
内田クレペリン検査は、「作業量」と「作業曲線」という二つの軸で評価されます。
| 評価軸 | 内容 | 評価される傾向 |
| 作業量(量級段階) | 前半・後半の平均作業量をⒶ〜Dの5段階(量級段階)で評価する。 | 知能、仕事の処理能力、積極性、活動テンポ、意欲など。 |
| 作業曲線 | 曲線全体の特徴や動揺、誤答傾向から評価する。 | 性格・行動面の特徴を見るために用いられる。 |
| 発動性 | 初頭部の作業量から評価。ものごとへの取りかかりの速さや意欲。 | 過度な場合は「素直」「気軽」な長所と「軽はずみ」な短所を持つ。 |
| 可変性 | 作業量の動揺から評価。気分や行動の変化の大きさ。 | 動揺が激しい、または欠如している場合に非定型となる。 |
| 亢進性 | 終末部の作業量から評価。ものごとを進めていく上での強さや勢い。 |
4. 臨床場面での活用と特徴
内田クレペリン検査は、その結果の分かりやすさから、特に産業・医療領域の臨床場面で有用です。
- 職業適応支援: 労働者の能力上・性格上の問題を推測し、職場での態度や行動の傾向を具体的にフィードバックするために活用されます。
- 職場復帰支援(リワーク): 休職者の回復度合いを作業量の回復という形で目に見える指標として測定できます。休職当初の結果と比較することで、回復の状況を本人や関係者に説得力を持って説明できます。
- 自己理解のアセスメント: 検査結果の説明に対し、受検者が都合の悪い点を直視できるか、内省や振り返りが十分に行えるかを見ることで、自己理解の度合いや職場復帰後の安定性をアセスメントする重要な情報が得られます。
- 客観性: 作業検査法であるため、他の質問紙法に比べて受検者の作為的意図(意図的な操作)が入りにくいという特徴があり、客観的な評価が得られやすいとされています。
まとめ
内田クレペリン検査は、単なる計算の速度を測るだけでなく、その過程で現れる作業曲線のパターンから、個人の特性や精神状態の調和度を捉えることができます。
試験対策としては、「定型曲線」の具体的な特徴(U字型、後期初頭の最高位など)と、3つの評価要素(発動性、可変性、亢進性)を、曲線と結びつけて理解しておくことが重要です。