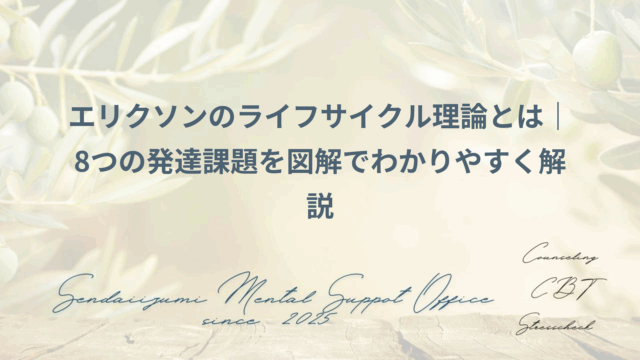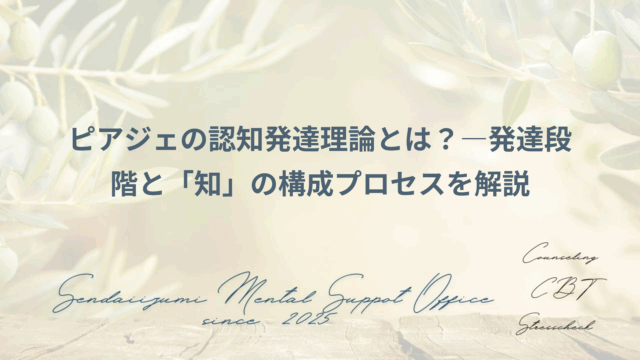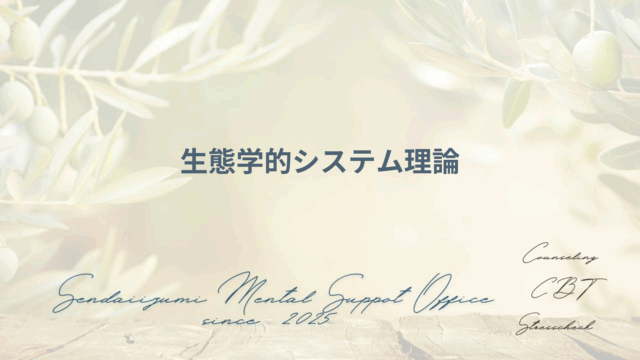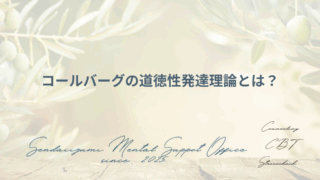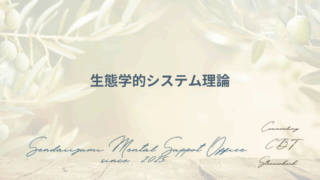愛着の研究まとめ
もくじ
愛着理論とは
イギリスの精神科医ジョン・ボウルビィ(J. Bowlby)は、人間の発達における「愛着(attachment)」の重要性を提唱しました。愛着とは、乳幼児が特定の養育者(多くは母親)に対して形成する情緒的な結びつきのことを指し、この関係性がその後の発達や対人関係に大きな影響を及ぼすとされています。
ボウルビィの愛着形成の4段階
ボウルビィは乳児の愛着行動が発達段階ごとに変化することを示しました。
| 段階 | 年齢目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| ① 誰にでも同じように反応する段階 | 生後0〜8週 | 人見知りせず誰に対しても微笑みや発声などの反応を示す。 |
| ② 特定の対象への愛着の始まり | 生後8〜24週 | 特定の養育者への関心が高まり、人見知りも始まる。 |
| ③ 明確な愛着の形成 | 生後6ヶ月〜2〜3歳 | 特定の対象に対して後追い、分離不安などの行動がみられる。 |
| ④ 目標修正的パートナーシップ | 3歳以降 | 養育者の行動や予定を理解し、身体的接触に執着しなくなる。 |
母性剝奪(マターナルディプリベーション)の影響
ボウルビィは、特定の母性的養育者との持続的な分離が乳幼児の発達に深刻な影響を及ぼすと指摘しました。この概念は【母性剝奪(maternal deprivation)】と呼ばれます。
研究例:
- 【スピッツのホスピタリズム】
スピッツは、乳児が母親から長期間引き離されることで、泣きやすくなり、体重減少、無表情、運動の緩慢といった症状が現れることを報告しました。 - 【ボウルビィの44人の少年泥棒研究】
母性剝奪がある少年ほど「情緒的冷淡」などの反社会的傾向が強いことを報告しました。
内的ワーキングモデル
乳幼児期の愛着経験は、【内的ワーキングモデル】として記憶・再構成されます。
- 養育者との関係から、子どもは「他者」「自己」「関係性」に関する無意識の信念・期待を形成し、これが後の対人関係の基盤となります。
ハーローの代理母実験
心理学の愛着研究で有名なのが【ハーローの代理母実験】です。
- 子猿はミルクが出る針金の代理母よりも、温かく柔らかい布の代理母を選択し、「愛着」は単なる食物供給ではなく、身体的・情緒的な安心感が重要であることが示されました。
ストレンジ・シチュエーション実験(エインズワース)
メアリー・エインズワースは、愛着スタイルの個人差を測定するため【ストレンジ・シチュエーション法】を開発しました。
| 愛着タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 安定型(B型) | 養育者の不在に不安になるが、帰還後はすぐ落ち着く。 |
| 回避型(A型) | 分離・再会時に感情を表さず、他者を避ける傾向。 |
| アンビバレント型(C型) | 分離不安が強く、再会時も不安定な行動を示す。 |
| 無秩序型(D型) | 分離・再会時に矛盾した行動(接近しつつ拒絶など)を示す。虐待歴等が関連することも。 |
愛着理論の試験頻出ポイントまとめ
- 「母性剝奪」→ボウルビィ・スピッツ
- 「内的ワーキングモデル」→ボウルビィ
- 「代理母実験」→ハーロー
- 「ストレンジ・シチュエーション」→エインズワース、4分類
- 試験では愛着行動の発達段階と具体的な実験研究の対応が問われやすい
試験では【エインズワースの分類と特徴】【母性剝奪の影響】【内的ワーキングモデルの意義】が頻出です。
各用語の定義と具体例を押さえて得点源にしましょう。