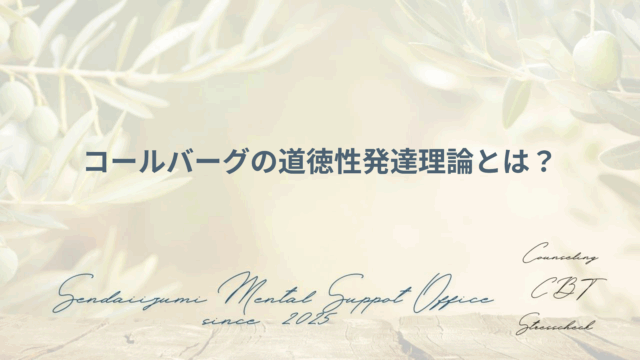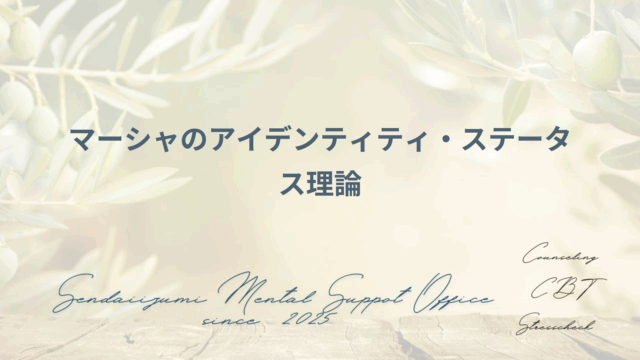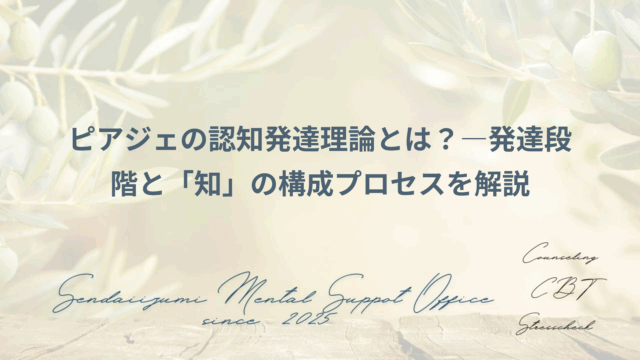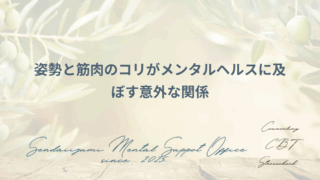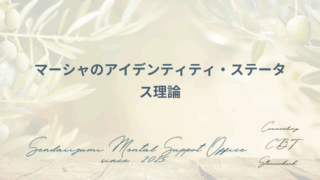エリクソンE・Hは、人生を8つの段階に区分し、それぞれの段階で迎える発達課題(危機)を乗り越え、適切な方向に発達することが健全な発達にとって重要であると主張しました。特に、葛藤を経験したうえで乗り越える点を重要視し、それができることによって「徳」が獲得されるとしています。
| 発達段階 | 発達課題 | 徳 |
| 乳児期 | 基本的信頼 対 基本的不信 | 希望 |
| 幼児期前期 | 自律 対 恥と疑惑 | 意志力 |
| 幼児期後期 | 積極性 対 罪悪感 | 目標 |
| 児童期 | 生産性(勤勉性) 対 劣等感 | 自己効力感 |
| 青年期 | 自我アイデンティティの確立 対 自我アイデンティティ拡散 | 誠実 |
| 初期成人期 | 親密さ 対 孤立 | 愛 |
| 成人後期 | 世代性 対 停滞 | 世話 |
| 老年期 | 統合性 対 絶望 | 知恵 |
乳児期(0~1歳半):基本的信頼 対 基本的不信
赤ちゃんは一人では生きていけません。そのため、母親をはじめとした周囲からの世話を必要としています。適切に世話を受けていれば、赤ちゃんの中で世界への信頼感が構築され「希望」を得られます。反対に、お腹が空いて泣いていても食べ物を与えられないなどの不快な気持ちが続いてしまうと、赤ちゃんは世界に対して不信感を抱くようになり、今後の人生観に悪影響を及ぼすとしています。
幼児期前期(1歳半~3歳):自律 対 恥と疑惑
この頃になると、歩いたり喋ったりできるようになります。また、第一次反抗期が出現するのもこの時期です。
赤ちゃんの頃は、食事や排せつ、着替えなどに周囲の手を借りていましたが、この頃にはしつけや自らのチャレンジによって徐々に自分でできるようになります。親がチャレンジの機会を与え、適切に手伝うことができれば、子どもは自信をつけてさらにやってみようという「意志力」を獲得できます。
しかし、親が先回りして何でもしてあげたり、挑戦した子どもを過度に叱ったりしてしまうと、羞恥心が芽生えてしまい、挑戦する意欲を失ってしまいます。
幼児期後期(3歳~6歳):積極性 対 罪悪感
子どものコミュニティが広がる時期です。保育園や幼稚園などで家族以外の同年代の友達との交流が増えていきます。世の中への関心も強まり、ごっこ遊びや質問が増えたりする時期です。このような振る舞いに対して、親がうっとうしがる態度を見せたり過度にしつけをしてしまうと、子どもは罪悪感を覚えてしまいます。
適度なしつけと自発性のバランスを上手くとることができれば、「目標」を意識する力を身に付けることができます。
児童期(6歳~12歳):生産性(勤勉性) 対 劣等感
小学校に通い始める時期で、学校の勉強や生活を通して新たな学びが増えていきます。このような中で、計画的に課題を仕上げることや学習経験を積み上げていくことで自信がついていき「自己効力感」を獲得することができます。
反対に、勉強が遅れてきたり課題を仕上げられないことが続くと、周囲と比較して自信を無くしてしまいます。
青年期(12歳~18歳):自我アイデンティティの確立 対 自我アイデンティティ拡散
思春期にあたる時期になり将来のことや自分自身について思い悩むことが増えてきます。「自分がこういった人間だ」と自己理解が進んでくると、自分で選んだ価値を信じ、貢献しようとする「誠実性」が得られます。「将来医者になって人を助けたい」、「サッカー選手になりたい」等と自分の中で方向性が決まれば、それに向かって直向きに勉強したりサッカーの練習をするでしょう。
一方でアイデンティティが確立できていないと、「自分とはなにか」について悩み続けることになります。特に目標もなく進学しても中退してしまったり、職を転々としてたり、フリーターとしてその日暮らしのような生活を送ってしまうかもしれません。このような状態をエリクソンは「アイデンティティ拡散」と呼んでいます。
また、エリクソンの「モラトリアム」やマーシャの「アイデンティティステータス」といった青年期の重要な用語がありますので、詳細は別記事で取り上げていきたいと思います。
初期成人期(18歳~40歳):親密さ 対 孤立
生まれ育った家庭や学校を離れ、社会に出て多くの人と関係を築いていく時期になります。結婚したり、新たな友人や家族との長期的・安定的な親密な関係を通して「愛」を獲得していきます。
しかし、積極的に人と関わらなかったり、長期的な人間関係を築くことを怠ったりすると、孤立を招きます。
成人期後期(40歳~65歳):世代性 対 停滞
この時期は、次世代の育成が重要になります。子どもを育てたり、職場の後輩の面倒を見る等、後の世代に貢献していくことです。自分の時間を子どもの世話に充てたりや自分の経験を若者に伝える時間に費やすことで「世話」の力を獲得していきます。
一方で、子育てや次世代の育成に関与せず自分のことだけ考えて生きているような状況を「停滞」としています。
また、ユングはこの時期を「中年の危機」と称し人生の転換時期にあるとしています。この時期は、生産性や社会的活動が活発になる反面、体力や感覚機能の低下が目立つようになります。また、家庭や職場での役割の変化も求められ始めます。このような中で、アイデンティティが再び揺らぎ、新たな生き方や価値観を手に入れることによってアイデンティティを再獲得する必要性が求められるとしています。
老年期(65歳以上):統合性 対 絶望
多くの人が定年退職し、老後の生き方を模索し始める時期です。人生の終わりに差し掛かってきて、これまでの人生を振り返ることが増えてくるでしょう。ある程度満足のいく人生であれば、「知恵」を獲得できます。
反面、自分の人生に満足できず、後悔を抱えた場合、絶望的な気分に支配され、穏やか余生を送ることが難しくなるかもしれません。