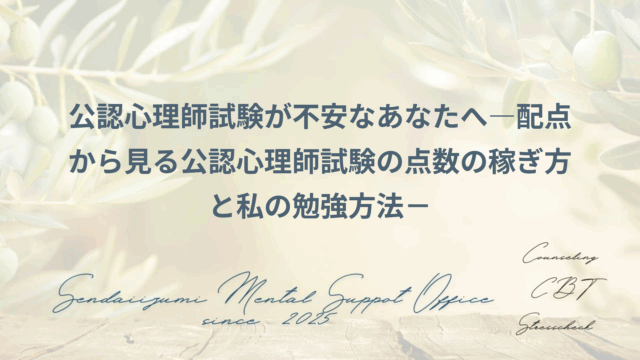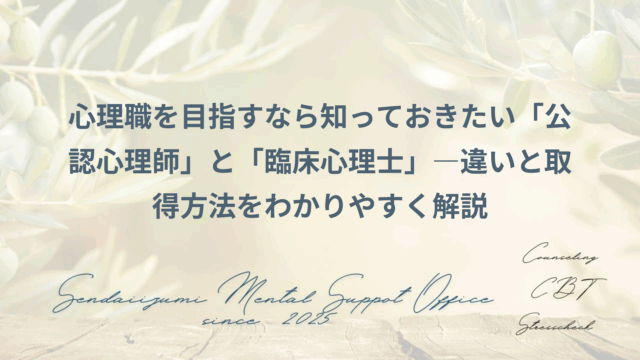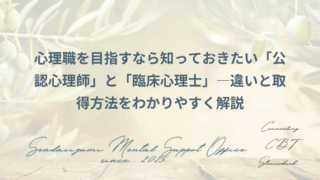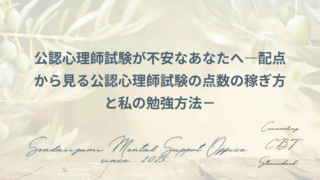公認心理師・臨床心理士を目指すための大学院受験ガイド:受験科目と効果的な対策とは?
もくじ
公認心理師・臨床心理士を目指すには「指定大学院」への進学が必要
臨床心理士および公認心理師の資格取得を目指すには、いずれも臨床心理士指定大学院への進学が前提となります。さらに、公認心理師の資格取得を目指す場合は、公認心理師カリキュラムに対応している大学院である必要があります。
現在、多くの臨床心理士指定大学院では公認心理師カリキュラムにも対応していますが、対応の有無は大学院ごとに異なるため、必ず志望校の公式情報を確認し、直接問い合わせることが重要です。
では、これらの大学院に合格するためには、どのような準備が必要なのでしょうか?
受験科目1:専門科目(臨床心理学)
出題傾向と特徴
臨床心理士指定大学院では、専門科目として臨床心理学が中心に出題されます。各大学院によって出題傾向が異なり、多くは論述形式で行われるため、用語の定義や理論背景、応用場面についての深い理解が求められます。
勉強法の選択肢
① 志望校特化型
志望校がすでに決まっている場合は、過去問を活用して傾向に合わせた対策を行うのが効率的です。ただしこの方法では、知識に偏りが生まれやすく、幅広い領域をカバーするのが難しくなります。そのため、将来的に公認心理師試験や臨床心理士試験も見据えている場合は、以下の②の方法をおすすめします。
② 広域理解型
まずは臨床心理学の基礎から応用まで広く学習し、その後に志望校対策へと移行する方法です。準備には時間がかかりますが、この方法により大学院受験・修士課程中・資格試験対策を一貫して効率よく進めることができます。
なぜ早めの対策が重要か?
大学院在学中は、実習・研究・講義・学会対応に追われ、資格試験対策の時間が十分に確保できないことが多いです。また、修了後に就職すれば、仕事と資格試験勉強の両立という新たなハードルが待っています。だからこそ、大学院受験の段階で専門知識をしっかりと積み上げておくことが、長期的に見て大きなアドバンテージになります。
受験科目2:英語(主に英文和訳)
出題形式と重要性
大学院英語は、長文読解・翻訳問題が中心です。一部の大学院では英作文を課す場合もあります。英語は足切り(最低点以下で不合格)の対象となることもあるため、合否を左右する重要科目です。
勉強法とスケジュール
段階的アプローチ
- ステップ1:基礎文法の復習
- ステップ2:短文→長文の翻訳練習
- ステップ3:心理学英文への対応
代表的な教材には、『ヒルガードの心理学』などがあります。特に心理学専門用語の英訳(例:「投影」=projectionなど)には注意が必要です。
勉強開始時期の目安
英語が苦手な人は、大学2年生の段階から取り組み始めるのがおすすめです。3年生になると専門科目や卒業論文などで忙しくなるため、早めの着手が得策です。
辞書の使用について
大学院によっては、試験中に紙の英和辞書の持ち込みが可能なところもあります。ただし電子辞書は禁止のケースが多く、辞書の使用可否は必ず事前に確認しましょう。いずれにせよ、単語力をつけておくことが試験時間の短縮につながります。
受験要素3:研究計画書と面接
研究計画書とは?
研究計画書は、大学院で行う予定の研究内容を事前にまとめた文書であり、面接試験での質問材料にもなります。基本的には、卒業論文を発展させたテーマで構成するのが無難です。
なお、実際に大学院に進学してから研究テーマを変更することはよくあるため、受験時点では現段階で最も関心があるテーマを明確にしておくことが重要です。
取り組むタイミング
研究計画書の作成は、卒業論文の進捗がある程度進んでから着手すれば問題ありません。指導教員やゼミの教授と相談しながら、実現可能性や先行研究を整理しましょう。
まとめ:大学院受験準備は長期戦。早めの対策が将来の鍵
公認心理師や臨床心理士を目指すには、指定大学院への進学とそのための十分な準備が必要不可欠です。大学院受験対策は、合格だけでなく、その後の資格試験や臨床現場での実践に直結する重要なステップです。
専門科目の理解、英語力の強化、研究計画の策定など、どれも一朝一夕では習得できません。心理職としてのキャリアを見据え、できるだけ早い段階から一つ一つ積み重ねていきましょう。