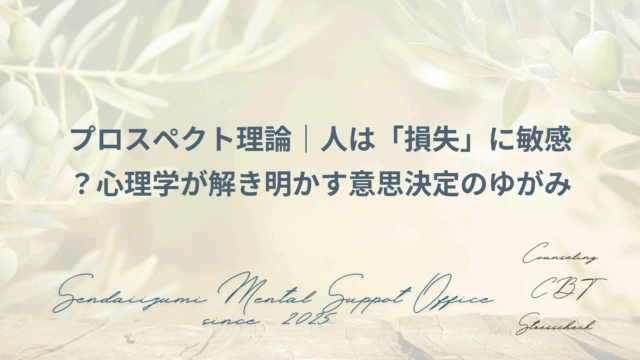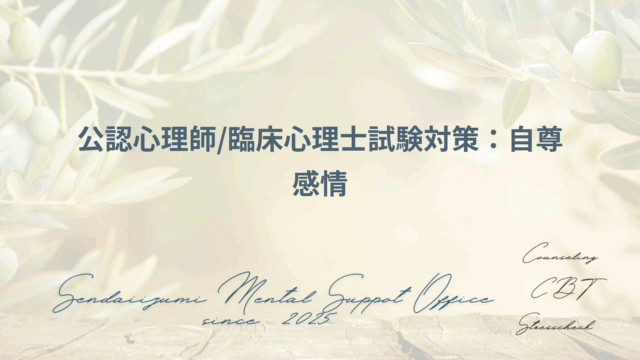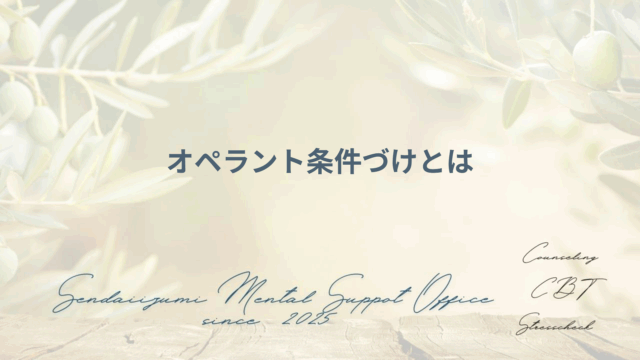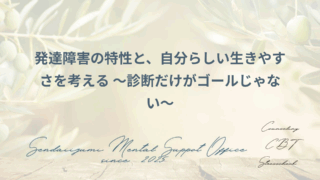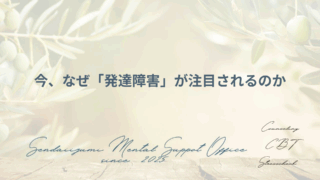アルゴリズムとヒューリスティック
問題を解決するとき、私たちの脳は大きく2つの方法を使い分けています。
ひとつは時間がかかっても確実に正解にたどり着く「アルゴリズム」。
もうひとつは、必ずしも正解にたどり着くわけではないけれど、素早く判断できる「ヒューリスティック」です。
それぞれの特徴を、具体例を交えてわかりやすく解説します。
もくじ
アルゴリズムとは|確実だけど時間がかかる思考法
アルゴリズムとは、決まった手順に従って考えを進めることで、時間や労力はかかりますが、最終的には必ず正しい答えにたどり着く方法です。
例えば、
- 数学の方程式を一つずつ解いていく
- 迷路をすべての道順を試して出口を探す
このようなやり方は時間はかかりますが、確実に正解が見つかる「アルゴリズム的」な考え方です。
ヒューリスティックとは|素早く判断するための近道
一方、ヒューリスティックとは、時間や労力を省き、素早く判断や問題解決を行うための「思考の近道」です。
ただし、必ずしも正しい結論にたどり着くとは限らず、誤った判断につながる場合もあります。
心理学者のトヴェルスキーとカーネマンは、私たちが日常でよく使うヒューリスティックをいくつか分類しました。
よく使われるヒューリスティックの種類
① 代表性ヒューリスティック(ステレオタイプ的判断)
物事を「いかにもそれらしい特徴」で判断してしまうことです。
例:
- 「外国人だから英語が話せるだろう」
- 「A型の人は几帳面だ」
このように、実際の確率や情報を無視して、自分の持つイメージや先入観に基づいて判断する傾向があります。
その結果、「連言錯誤」という誤った推論(もっともらしいけれど実際には確率が低い判断)をしてしまうこともあります。
② 利用可能性ヒューリスティック(思い出しやすさによる判断)
よく目にするもの、印象に残っていることを過大評価しやすくなる思考パターンです。
起こりやすい状況:
- 頻繁に目にする広告やニュース
- 自分や家族が体験した出来事
- 衝撃的な事件・事故
- 具体的な口コミやレビュー
たとえば、ニュースで連日報道されると、実際よりもその出来事が頻繁に起きているように感じてしまいます。
③ 係留と調整ヒューリスティック(最初の情報の影響)
最初に与えられた情報(アンカー)を基準に、その後の判断をしてしまう傾向です。
例:
- 「定価15万円のテレビが今だけ10万円」と言われると、非常にお得に感じる
- セール前の価格表示を見て「安い」と思い込む
このように、最初にインプットされた情報が、冷静な判断をゆがめることがあります。
④ 再認ヒューリスティック(知っているものを評価しやすい)
知っているものに対して、好意的・安心感を持ち、知らないものは低く評価する傾向です。
例:
- 聞き覚えのある都市名の方が「人口が多そう」と思う
- 見たことのあるブランドの商品を選ぶ
これにより、必ずしも正しい情報に基づいていない判断を下してしまうことがあります。
まとめ|ヒューリスティックのメリットと注意点
ヒューリスティックは、私たちが複雑な情報をすばやく処理し、日常のさまざまな選択を効率よく行うために欠かせないものです。
しかし、「思い込み」や「誤判断」につながりやすいため、特に重要な場面ではアルゴリズム的な丁寧な思考も意識することが大切です。
ヒューリスティック=悪いものではなく、「使いどころ」が重要だということを覚えておきましょう。