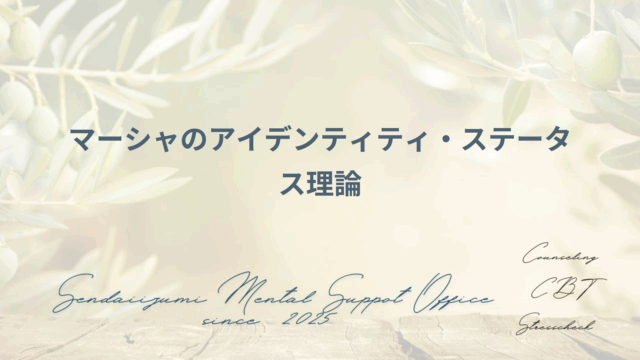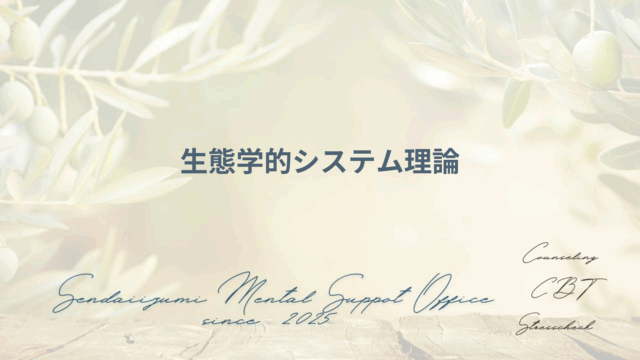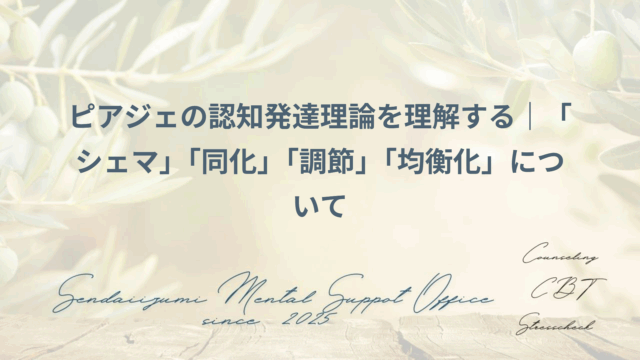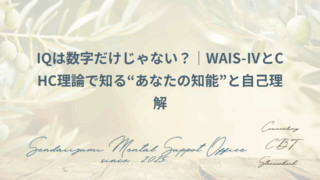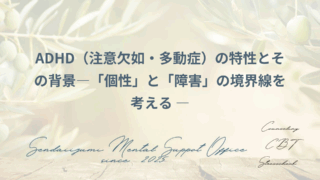ピアジェの認知発達理論とは?―発達段階と「知」の構成プロセスを解説
もくじ
ピアジェ理論の基礎:発生的認識論とシェマ
ジャン・ピアジェは、子どもの「認知の発達」を、生物学的な基盤から捉えた心理学者です。彼は、子どもはただ環境に反応する存在ではなく、自ら積極的に環境へ働きかけ、実験と観察を通して自分の「知」を組み立てていくと考えました。これが「発生的認識論(genetic epistemology)」と呼ばれる理論です。
その中核にあるのが、「シェマ(schema)」という概念です。シェマとは、ものごとの捉え方や行動のパターンといった認知的な枠組みを指します。人は新しい経験をすると、これまでのシェマに取り込もうとする【同化】を行いますが、既存のシェマだけでは対応できないときは、シェマ自体を変化させる【調節】が起こります。
この「同化」と「調節」のバランスを取りながら、より洗練された認知構造を形成していくプロセスを【均衡化】と呼び、ピアジェ理論の根幹をなしています。
ピアジェの認知発達段階:4つのステージ
ピアジェは、子どもの認知発達を以下の4つの段階に分けました。それぞれの段階で、特有の思考スタイルや理解の仕方が見られます。
1.感覚運動期(0~2歳)
赤ちゃんは、見る・聞く・触るなどの感覚と、自らの身体を使った運動を通して、外界を認識し始めます。生後18か月頃には、物が目の前に無くても存在すると理解する「対象の永続性」が獲得されます。
この時期の特徴的な行動には「循環反応」があります。
- 第一次循環反応:偶然に起きた行動を繰り返す
- 第二次循環反応:外部の対象と関わりながら面白さを見出す
- 第三次循環反応:自分の行動で対象がどう変わるかに関心を持つ
また、模倣行動も発達していき、「手や発声の模倣」→「表情の模倣」→「延滞模倣(見たものを後から真似る)」と進展します。
2.前操作期(2~6歳)
この段階では、言葉やイメージを用いた象徴的思考が可能になります。ごっこ遊びなども盛んになります。
この時期に見られる特徴には以下があります:
- 自己中心性:他人の視点で物事を考えられない(例:「三つ山課題」)
- アニミズム:非生物に感情や意志があると信じる
- 人工論:自然現象も人間が作ったと考える
また、「心の理論(ToM)」が発達し、4歳頃には「誤信念課題(サリーとアン課題)」にも対応できるようになります。
この時期はさらに細かく分かれます:
- 象徴的思考期(2~4歳):目の前に無いものを思い浮かべたり、描いたりできる
- 直感的思考期(4~7歳):経験をもとにした直感的な推論が可能になるが、論理性は未熟
3.具体的操作期(7~12歳)
子どもは論理的な思考を獲得し、現実の具体的な事象に対して理論的な推論ができるようになります。
主な発達は以下の通り:
- 保存の概念:形や見た目が変わっても量は変わらないと理解
- 脱中心化:自分以外の視点を取り入れて考えられる
4.形式的操作期(12歳以降)
この段階になると、抽象的な思考や仮説に基づく推論が可能になります。経験に頼らず、論理的な道筋で問題を解決できるようになり、自己や他者を多角的に捉える力が養われます。
子どもの道徳観の発達:ピアジェの視点
ピアジェは、子どもの道徳性についても発達段階があるとし、以下の2段階を示しました。
- 他律的道徳観(5~9歳):大人や社会が決めたルールは絶対で、破れば罰があると信じる。意図よりも結果で善悪を判断。
- 自律的道徳観(9~10歳):ルールは相互理解のうえで変更可能と理解し、他者の視点を考慮して判断ができる。
まとめ
ピアジェの認知発達理論は、子どもが自らの経験をもとに「知識を構成する主体」であることを示しています。彼の理論は、教育現場や発達支援において、子どもの理解の深さに応じた適切な対応を考える際の指針となります。
「均衡化」や「シェマ」の概念は、現代の学習理論や心理療法にも多大な影響を与えており、試験対策としても必須のキーワードです。